【STJ第2号掲載】hitaruこけら落とし公演「アイーダ」2日間全幕レビュー
オペラ夏の祭典 2019-20 Japan⇔Tokyo⇔World「トゥーランドット」の札幌公演を記念して、hitaruこけら落し公演「アイーダ」のレビューをWebで公開しました。さっぽろ劇場ジャーナル第2号の特集だった本記事。2日間の全幕レビューをお楽しみください。指揮はバッティストーニ、オーケストラは札幌交響楽団です。<事務局>
hitaruこけら落し公演「アイーダ」
2018年10月7日(土) 札幌文化芸術劇場hitaru
札幌文化芸術劇場hitaruの幕がついに上がった。一か月前に地震があり、その余震が続きさらに連続で台風が襲来し、本当にアイーダは上演されるのか?という声が聞かれるなかでのオープンだった。様々な憶測が飛び交うなかで、しっかりとした情報を発信し続け無事に終演にこぎつけた関係者に感謝の言葉を贈りたい。上演中に余震がなかったのは幸いだった。そのような状況で、北海道の希望を背負って上演されたアイーダはまさに歴史的なこけら落としとなった。

撮影:武田博治
アイーダという作品は、「戦争」が主題となっていることから、現代では反戦思想を表現するために使われやすい。バレエをいっさい使わず、傷ついた兵士たちが絶え々に帰還する凱旋行進曲などに注目が集まる。現代の演出家たちは、いかにも室内楽的に細やかな世界を描く。このような流れの中でhitaruのオープンを飾ったのは、ミニマムへ結晶化する重唱と膨れ上がる凱旋行進曲の振幅のうちに時代的な制約を超えた普遍的な世界を描きだす、ザ・グランドオペラとしてのアイーダだった。やはりアイーダはこうでなくてはと改めて実感した。

撮影:武田博治
演出はジュリオ・チャバッティ。ローマ歌劇場が野外のカラカラ劇場で上演した舞台のリメイクだった。ローマ歌劇場の上演は映像で観たかぎりでは、セットが散乱したような舞台になっていたが、今回はhitaruの舞台に合わせて一新してきた。巨大な柱を巧みに配置し神殿や宮殿が立ちあらわれる。すっかり無駄がなくなっている。こうなるとただのリメイクとは言えない。ここからも、このこけら落としにかける制作サイドの意気込みが伝わってきた。衣装も趣味がいい。国家の威厳を示すためにキンキラにしすぎて下品になりがちな作品である。だが、豊富に布を使った色彩がコンセプトを持って艶やかだったり野趣に満ちていたりどこにも手抜きがないのだ。
前 奏 曲
それでは、幕順に見てゆこう。まず前奏曲。ここは演出に注目した。今回の演出はオーソドックスなものだったが、オーソドックスな演出に小さな変化球を重ね合わせることで新鮮さが生まれる巧みさが際立った。前奏曲では、一組の男女のバレエダンサーが小さな幸福を愛でるように繊細なダンスを踊る。これだけなら、よくあるパターンだ。だが、今回の舞台では、その男女を神官たちが囲んでいるのだ。しかも、その神官たちは男女に(客席にも)背を向けておりそのまま動かない。冷酷な神官たちの犠牲になる一組の男女を暗示しているのだ。これは前奏曲の内容そのもので物語への見事な導入を果たした。
前奏曲の演奏は初日はポリフォニーの線にやや精度を欠いたが2日目にぐっとよくなった。アイーダのモチーフ(譜例3)の音が丁寧に整理され冷たさを発する。

譜例3:アイーダのモチーフ
まるで石室で眠っている魂が冥界で遊んでいるようだった。神官のモチーフ(譜例4)から音楽が厳しさを帯びると徐々に音に体温が生じる。眠っている魂が呼び出されタイムスリップし物語が動き始めるような感触があった。

譜例4:神官のモチーフ
第 一 幕
続いて第一幕。イタリアオペラでは開幕の合唱が置かれるのが常だが、ヴェルディはここで華やかな合唱を捨て、ごく切り詰めた素材による集中力の高い対話を書いている。聴き手の意識を一気に物語に集中させるためだ。バッティストーニの指揮が結晶化した透明な響きで伸びやかに歌わせる。両日ともに最高の滑り出しだった。ランフィスの「猛々しいエチオピアがまた攻めてくる」は、感情を排して滑らかなレガートで高僧の精神的な高貴さを表現しなくてはならない。初日の妻屋、2日目の斉木ともに立派だったが斉木は本調子ではなかった。やや声に濁りが生じ人間臭さが出てしまった。ランフィスは徹底して冷静沈着に歌われなくてはならない。

譜例5:アムネリスのモチーフ
「清きアイーダ」では初日の福井が、今日は英雄的なラダメス像で行くという意思表示をした。2日目の城はもっと繊細で「弱さ」のある歌唱。濁りのない清らかな歌が若々しい。ロマンツァ最後のppppは両者ともにフォルテだった。こけら落としに相応しいザ・グランドオペラとしてのアイーダをやるのだという意図があったのだろう。第3曲に入ると、3連符を伴ったアムネリスのモチーフ(譜例5)が1st.Vn.のG線のユニゾンで骨太に聴こえてくる。優雅なのだが札響の弦にいかにも威厳がある。「なんという喜びが」は、初日の清水には脆弱な疑いの色が、2日目のアナスタシアからは「私を愛さないはずがない」という自信が聴こえてくる。表面の優美さを表すこのモチーフと内心の不安を表現するアレグロ・アジタートが交代しつつ高揚してゆく。バッティストーニの切り替えがさすがに巧みだ。急に空気が柔らぐクラリネットによるアイーダのモチーフ(譜例3)。

譜例3:アイーダのモチーフ
優しく優美な音楽が会場を包むと、弦のトレモロがラダメスの胸の高鳴りのように聴こえる。札響の弦はピットが深いため全体的にやや遠く聴こえてしまったが、ここは素晴らしかった。

撮影:武田博治
三重唱は、初日の清水の声質がソプラノに近い(清水はソプラノも歌う)ため、アイーダとアムネリスの声質が重なってしまい、似た声質で音域の低いアムネリスが埋もれてしまった。2日目はアナスタシアの声質がいかにもというメゾの深い声だったため三人の声が重なり合う色あいの面白さが十分に出ていた。
輝かしいファンファーレとともに第4曲へ。国王が登場する。国王の歌詞にはCb.のスタッカートによる対位的な進行が伴う。威厳を表現しているのだ。だが、威厳は必要なのだが国王のそれはランフィスよりは低くなければならない。ここは初日のハオがピンポイントで国王の性格を表現した。続く伝令の報告でのトレモロの緊迫感、木管の鋭さ、それに乗って行進曲がはじまるとバッティストーニの真骨頂。ここから2群の合唱と6人のソリストのアンサンブルに入る。エジプト勢に一人混ざるアイーダだけが別の装飾句を歌うのでアイーダが明瞭に聞こえなくてはならない。初日のザネッティンは埋もれがちで聴こえる箇所も音程に難がある。2日目の木下は的確に装飾をコントロールし複雑な心境が表出された。
アイーダの「勝ちて帰れ」に入る前にエジプト勢が一斉に舞台を去る。ここで、初日の清水が、アイーダの横を通るときに勝ち誇ったような笑みを浮かべアイーダを見降ろして見せた。これにはゾクっとした。2日目は何もせず素通りだった。全体的に初日のほうが演技が細かかった。おそらく初日のメンバーに演出上の細かい指示の時間がより多く割かれたのだろう。「勝ちて帰れ」は合唱より半音下がり、急に鋭く暗くなる。アイーダの不安を表す陰影は初日のザネッティンに色濃く聴かれた。木下は明るい。コーダは重要だ。どちらが勝利しようともアイーダにとっては不幸が待っている。アイーダは実ははじめから死を覚悟している。コーダでは「いっそ死んでしまいたい」、「死なせてほしい」という歌詞が続く。ここで苦悩と一緒に「諦め」の色が聴きとれなくてはならないのだ(アイーダは終曲で息絶える場面でも「見えますか?死の天使が」と歌っている)。ザネッティンに比べ木下は静かな祈りの感情を表出したが、両者ともにこの決定的に重要な「諦め」を表現できなかった。アイーダという人物のこの理解が第2幕でも食い足りなさに現われる。
第一幕第二場ではバッティストーニの指揮に注目した。オペラというものは、どんな名作であってもやや冗長な部分を含むものだ。楽譜に忠実に演奏すると、そういった箇所では会場の空気が弛み観客も疲れてくるものだ。この第二場はアイーダではそれに当たる。しかし、バッティストーニは、巫女の祈りの歌を快速で飛ばし、交代する男声四部で思い切って遅くするという処理をみせ飽きさせなかった。しかも、急激に静かになる男声四部の静謐さは特筆すべきものだった。ランフィスはバスだが、男声四部の第2テナーとユニゾンなのだ。地中へ引きずり込まれそうな重みと宙に浮遊するような軽さが同時に聴こえてくる。これほど丁寧なこの男声四部の演奏を初めて聴いた。巫女を歌った針生には宗教的な透明感が感じられる。存在感があり、出番の少ない巫女ではもったいなく感じた。

撮影:武田博治
第 二 幕
第二幕の導入は、緊張とそのわずかな緩和が連続する全曲中で唯一、気が休まる曲。ハープのアルペッジョに乗って侍女たちの女声二重唱がはじまる。2つの声部はここでも対位的であるのが面白い。演奏は両日とも、伸びやかなカンタービレで優美に歌われながらも、2つの声部が明確に分離して聴こえた。こうなると、この後に登場する2人の女性のすれ違いを示すように感じられるのが面白い。
続いて第八曲、冒頭にアムネリスが歌う「武運つたなく」に使われている「勝ちて帰れ」の音形が両日とも崩れてしまっていた。ここは惜しかった。続いてアイーダのモチーフがアレグロ・アニマートになる。このモチーフは常に優しい空気とともに奏されるがここは複雑だ。バッティストーニがオーケストラからアイーダの乱れた感情を巧みに引き出す。しかし、各声部が緻密に整理されており歌を邪魔することがない。鳴り切っておりかつ邪魔しない。これは両日そうだった。
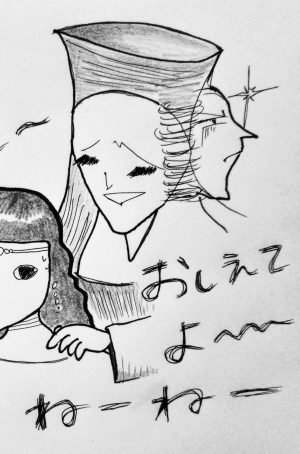 この後は初日にアムネリスを歌った清水の独壇場だった。「私はおまえの友」、「何があったの?友情を信じて話して」と偽りの優しさを見せる箇所のいかにも意地悪そうな表情。アイーダがシラを切るたびに少しずつイライラが募る感情の動き。続いてアムネリスが「ラダメスは死んだ」と嘘をつきアイーダを試す。そして、アムネリスがアイーダの動揺を見て「お前はあの人を愛しているね」と問いかけるとアイーダは否定する。それを見たアムネリスが「嘘をおっしゃい」という。ここで清水はイラ立ちが頂点に達しヒステリーを爆発させるようにアイーダに詰め寄った。もの凄い気迫だった。しかも、どこか自信がなく常にイライラしている心が見えるようなのだ。清水の声質がアムネリスにしては軽めで清潔感があることもあり、新鮮でかつ真実味のあるアムネリス像を打ち立てた。対するアナスタシアは、私を愛さないはずがないとばかりに悠然としているオーソドックスなアムネリスだ。ここはアイーダの心の動揺はオーケストラが見事に表現した。アイーダを歌った両日の歌手二人より鮮明だった。
この後は初日にアムネリスを歌った清水の独壇場だった。「私はおまえの友」、「何があったの?友情を信じて話して」と偽りの優しさを見せる箇所のいかにも意地悪そうな表情。アイーダがシラを切るたびに少しずつイライラが募る感情の動き。続いてアムネリスが「ラダメスは死んだ」と嘘をつきアイーダを試す。そして、アムネリスがアイーダの動揺を見て「お前はあの人を愛しているね」と問いかけるとアイーダは否定する。それを見たアムネリスが「嘘をおっしゃい」という。ここで清水はイラ立ちが頂点に達しヒステリーを爆発させるようにアイーダに詰め寄った。もの凄い気迫だった。しかも、どこか自信がなく常にイライラしている心が見えるようなのだ。清水の声質がアムネリスにしては軽めで清潔感があることもあり、新鮮でかつ真実味のあるアムネリス像を打ち立てた。対するアナスタシアは、私を愛さないはずがないとばかりに悠然としているオーソドックスなアムネリスだ。ここはアイーダの心の動揺はオーケストラが見事に表現した。アイーダを歌った両日の歌手二人より鮮明だった。
続いてアムネリスが、「次の一言で明白になる」と凄むときの一瞬の静けさにも緊張感がある。この幕の最大の聴きどころ、アムネリスが「嘘をついたの。ラダメスは生きている!」は、初日の清水が疑心暗鬼に怯えるように、2日目のアナスタシアは高いところからアイーダを見下ろすように歌った。「お前の恋敵はファラオの娘!」の”faraoni”でも清水はどこか複雑でクリアカットできない感情を滲ませる。対するアナスタシアは全エジプトの尊厳を背負っているとばかりの威勢を見せた。それに対しアイーダが「王女、それなら私だって」と言いかけ口をつぐむ。この箇所は、両日ともやや淡白だった。「勝ちて帰れ」のところで書いたが、アイーダは最初からどこか人生を諦めている。それでも、ラダメスに対する気持ちだけは負けない。これはアイーダが本質的に持っている強さだ。この忘れかけていた「強さ」が唯一ここで沸き上がってくるのだ。表面に見えている柔和なアイーダ像を突き破るような表現を期待したかった。かつベルカントの滑らかな発声でそれを表現してほしかった。アイーダに関しては続く「私の苦しみを憐れんでください」でも悲痛さが感じられない。2日目の木下は声楽的な完成度は高かったがやはり楽天的に聴こえた。ラダメス、アムネリス、アモナズロが両日で各役の性格描写の可能性を卓抜に示したのに比してアイーダは両日ともにやや平凡だった。
第二幕第二場の大フィナーレ。凱旋行進曲は、軍隊の大行進を使わずに品の良いバレエによって描かれた。優しい女性とバーバリスティックな男性のダンサー群が交代する。衣装も気品のある色あいが細やかでバレエの振り付けも威圧的ではなく優しい。国家の威信を誇示するというようではない。歓呼の大合唱の爆発も、その後の女声二部の旋律と男声四部のフガートもまったく暴力的ではなくとても丁寧だった。バッティストーニの合唱の扱いは年々丁寧になっているように感じられる。

撮影:武田博治
式典の場ではアモナズロが登場する。晴れやかな雰囲気が減7の和音で一気に緊迫を強めるとアモナズロが「この女の父だ」と、その声をはじめて聴かせる。初日にアモナズロを歌った今井が見事だった。一言で全観客を威圧し、しかも一国の頂点に君臨する国王の威厳を存分に轟かせた。この一言で第三幕への期待に胸が高鳴った。2日目の上江も表現力は豊かだったが、やや虚勢を張っているように聴こえてしまい惜しかった。アンサンブル・フィナーレではバッティストーニが快速で飛ばす。神官たちのユニゾンとアイーダとラダメスのユニゾンが力強く拮抗する。ユニゾンから溢れてくる若々しい情熱がヴェルディならではだ。
第 三 幕

撮影:武田博治
第三幕は冒頭の前奏からすこぶる丁寧だった。8つのパートに分割された弦がデリケートな音の色合いを弱音のまま響かせる。深いピットから聴こえてくるのが余計に神秘的に感じられる。続いてアイーダが歌う「おお、澄みきった空よ」は、「勝ちて帰れ」よりもはるかに味わいが深く難しい。恋心に望郷の念が混ざる複雑な表現が要求される上に、ソプラノの声の変わり目を往き来するのだ。初日のザネッティンはまさにこの声の変わり目に苦しんだ。高音3点Cもフラッとしてしまい気の毒だった。2日目の木下は声のコントロールは安定していたがこのナンバーが持つ微妙な陰影を表現するには至らなかった。むしろオブリガードのオーボエが儚さを感じさせた。
 続くアイーダとアモナズロの二重唱は初日が圧倒的に素晴らしかった。アモナズロがアイーダにラダメスを利用するようけしかける際に、最後に「分かるな?」という。今井は小声なのだが背筋が凍るような威圧感を実感させた。アイーダの顔を除きこむ表情にも寒気がした。アイーダが拒絶した後のアモナズロの怒りの爆発はオーケストラが落雷のようだ。ここを聴いていてピットを通常より深くした理由に気づいた。オーケストラが鳴り切る必要があるのだが、それでも声を邪魔しないように工夫していたのだ。ヴェルディはオーケストラがいかに雄弁になろうとも、それが声を上回ることを絶対に許さなかった。そこには「声の芸術」たるイタリアオペラの威信がかかっていた。バッティストーニが創り出した音響からはその意図がはっきりと感じられた。ピットが深いのがずっと気になっていたのだが、第三幕に至ってその理由がよく分かった。ヴェルディの伝道者たる指揮者のアイデアなのだろう。
続くアイーダとアモナズロの二重唱は初日が圧倒的に素晴らしかった。アモナズロがアイーダにラダメスを利用するようけしかける際に、最後に「分かるな?」という。今井は小声なのだが背筋が凍るような威圧感を実感させた。アイーダの顔を除きこむ表情にも寒気がした。アイーダが拒絶した後のアモナズロの怒りの爆発はオーケストラが落雷のようだ。ここを聴いていてピットを通常より深くした理由に気づいた。オーケストラが鳴り切る必要があるのだが、それでも声を邪魔しないように工夫していたのだ。ヴェルディはオーケストラがいかに雄弁になろうとも、それが声を上回ることを絶対に許さなかった。そこには「声の芸術」たるイタリアオペラの威信がかかっていた。バッティストーニが創り出した音響からはその意図がはっきりと感じられた。ピットが深いのがずっと気になっていたのだが、第三幕に至ってその理由がよく分かった。ヴェルディの伝道者たる指揮者のアイデアなのだろう。
今井は演技も卓越していた。アイーダとラダメスの二重唱が終わる頃に二人の背後にそっと忍び寄る。言葉を発していないのだが、アイーダに「何をしている。早く道を聞き出せ」と催促しているのがはっきり分かる。2日目の上江は同じタイミングで舞台に登場したが何をしに登場したのか分からなかった。2日目は初日と比較するとやはり棒立ちが目立ってしまった。
ラダメスがアイーダに逃げ道を話したとたんアモナズロが登場する。初日にラダメスを歌った福井は、微塵も動揺を感じさせない。「嘘だ!これは夢だ!」というときも常に英雄的なのだ。そのベルカントの声楽的な完成度は見事であったが、その分、一本調子に聴こえてしまった。ここは2日目の城が優れた性格描写を聴かせた。いま、自分がしてしまったことに気づいたショックで失神しそうな表現を聴かせた。演技面で単調になってしまった2日目の出演者のなかで城は気を吐いた。幕の最後の「神官殿、この身をお任せします」でも福井は微動だにしない。対する城は動揺から我を取り戻し、覚悟を決めたように歌う。まったく違うラダメス像だった。福井のラダメスは大きな歓声を浴びた。だが、ラダメスとは一貫して英雄的に歌われてよいのだろうか。アイーダに唆されて他国での生活に希望を見出したり、やはり弱いところがある。アーノンクールは、ラダメスは強い女性二人に挟まれた「軟弱な」英雄でなければならないと述べている。その意味では城が描いたラダメスにより共感できた。
第 四 幕
第四幕は一場も二場も出演者全員が打って出た名場面となった。まず第13曲シェーナと二重唱でのラダメスとアムネリスの応酬。初日は清水が「お願い、私を愛するなら助けてあげられる」と必死に訴える。福井のラダメスがもうすべてを受け入れているというような毅然とした態度で突き返す。繰り返されるうちにアレグロ・アジタートのハ短調に入ると清水の狼狽がヒートアップする。清水が全身で訴える。まるで何かに憑かれたかのようなのだ。観客の全員が舞台に釘付けになった。
続いて裁判の場。神官のモチーフ(譜例4)が重苦しく繰り返される。清水のアムネリスはそのなかでほとんど音程の幅のない独白を呻くように歌う。ここはアナスタシアからも苦悩が伝わってきた。

譜例4:神官のモチーフ
神官のモチーフが荒々しく強奏されると裁判がはじまる。非情な金管とランフィスの詰問が続く。ここのランフィスは金管と同じように感情を排し誇張することなく冷徹に歌わなくてはならない。しかし、3回目に「祖国を裏切った」と言い渡すときに両日ともラダメスを罵倒するような感情を露わにした。もっと冷たく非情に徹するべきではないのかと感じた。金管は詰問を反復するたびに半音ずつ上昇し緊張の度合いを上げてゆく様子を見事に表現した。ここには凱旋行進曲の響きがたしかに重ね合わされていた。それによって、あの華々しい凱旋の明るさが無慈悲な国家権力の暗さと表裏一体であることをまざまざと実感させた。
この裁判の場は、見えない舞台裏で裁判が行われている。アムネリスは最も大切な人の危機にもかかわらず関与することができないのだ。清水は右往左往しつつ、どうすることもできないという圧倒的な無力感を見事に表現した。心を鷲づかみにされた。内臓が抉られるような思いがした。裁判が終わり神官たちが表に出てくる際の金管の低音が阿鼻叫喚の響きで襲ってくる。ここはいつも大人しい札響がどれだけできるか心配だったのだが、杞憂だった。言うことなしだった。
判決を下した神官にアムネリスが食ってかかる箇所は、両日ともに白眉だった。アムネリスはここで、「お前達が殺そうとしているのは私がかつて愛した人だ」と言う。「かつて」と言っているのだ。テクスト上ではこの時点でアムネリスはラダメスから愛されることをもう諦めている。ここの解釈は両日で異なった。初日の清水は「私が(今も)愛している人を殺さないで」と我を忘れてすがりつく。もう王女の権威も外聞もかなぐり捨てているが、神官たちに無碍にあしらわれる。そして幕の最後の歌詞、おそらく全幕中、もっとも重要な歌詞「お前たちの上に呪いを!天の復讐が落ちることになろう!」を清水は、泣き崩れる最後の捨て台詞のように言い放った。地位も権力も何もかも捨てても手に入れたいラダメスへの想いを最後まで訴え続けた。涙が止まらなかった観客も多かったことだろう。これに対してアナスタシアは、テクストのアムネリス像に近かった。神官たちと対峙した時点でもうラダメスから愛されることは諦めている。その上で、ラダメスは正しい、正しい人を罰すべきではないという強烈な義憤を爆発させたのだ。裁判の場に入り、一度失った王女の威厳を最後にもう一度取り戻して見せた。第4幕第一場に関しては清水もアナスタシアも最高に美しかった。こうなるとどちらが正解ということはない。バッティストーニと札響も尊厳を奪い去る非人間的な神官たちの恐怖感を素晴らしく表出した。バンダの金管も陸上自衛隊北部方面音楽隊ということだったが、研ぎ澄まされた怜悧な音楽を実現した。会場にいた全員にとって忘れることができない名場面となったことだろう。
最終場は通常は二重舞台を使う。地下の石室に閉じ込められたラダメスを一階に配置し、その上の二階を地上に見立てるのだ。しかし、チャバッティの舞台はラダメスとアイーダが閉じ込められた石室と、地上で祈るアムネリスを同一平面に置いた。その上で巫女たちが喪服で葬送する。

撮影:武田博治
この配置はコンヴィチュニー演出でも見たがやはり想像をかき立てる。アイーダとラダメスは死によって救済される。優しい甘美な音楽がそれを表している。しかしアムネリスはこの後も生き続ける。非情な国家権力によって「何か」を奪われたという点ではこの3人は同じなのだ。甘美な二重唱は一見すると「救い」であるがそれと同時に凄惨な「死」でもあることをチャバッティの舞台は訴える。チャバッティは一面的に死を美化しない。しかも一階に並ぶ彼らは私たちの隣人なのだ。
アイーダとラダメスは徐々に酸素が薄くなり意識が遠のく。呼吸が徐々に弱くなるようにバッティストーニが巧みに音楽をコントロールする。最後に息を吸ったところでハッと音楽は止まる。それをアムネリスの祈りが引き継ぐ。アムネリスは生き続けるのだ。初日の福井は最後まで堂々と、城は意識が遠のくように、それを受ける初日の清水は涙で声がかすれるように、アナスタシアはただ静かに祈るように、そして神を讃える音楽がいかにも空虚に一度鳴り幕は下りた。前奏曲で呼び出された魂が冷たい墓へ還ってゆくようだった。

1日目カーテンコール(撮影:武田博治)

