【STJ第5号掲載】札幌交響楽団 東京公演2020(執筆:平岡拓也)
さっぽろ劇場ジャーナル第5号の完成記念に、第5号の「札響PickUp!」欄に掲載している2020年2月の定期演奏会と東京公演のレビューを2本立てでWebに公開します。札幌での演奏会は本紙編集長、東京公演は若手音楽評論家の平岡拓也さんが執筆しています。
※編集長の第626回定期演奏会のレビューはこちらからどうぞ。
紙のジャーナルでは4~5面にわたって「多田 vs 平岡のレビュー対決」になっているので、ぜひ紙もご覧ください。(事務局)
2020年2月7日(金) サントリーホール (大ホール)

札幌交響楽団提供
毎年この時期に催される札幌交響楽団(以下、札響)の東京公演を聴いた。あくまで在京リスナーである筆者の感触であるが、定期的に来京してくれる東京以外の楽団というのは意外にも決して多くなく、その意味で札響は貴重だ(他だと大フィルくらいだろうか)。ある楽団を一定周期で聴くことにより、その楽団の癖や音色の独自性、強みを発揮するレパートリーなどを朧げながらも聴衆は把握することができる。そしてその聴取の蓄積に基づき、一部の聴き手は「ああこの曲ならきっといい演奏になりそうだから現地に飛んでみようか」等の想像を膨らませ、より濃い鑑賞体験へと誘われるのである。オーケストラにとっても、本拠地のホールとは異なる音響・聴衆の下での演奏は間違いなく糧となる体験だ。つまりは、演奏者・聴衆にとってwin-winのイヴェントが演奏旅行だと言える。
 さて、それでは今回の東京公演について見ていきたい。昨年に引き続き首席指揮者(2018〜)のマティアス・バーメルトが指揮。演目は中プロを除いて1/31・2/1に行われた第626回定期と共通で、中プロのモーツァルト第39番はディートリヒ・ヘンシェルを独唱に迎えたマーラー『亡き子をしのぶ歌』に変更された。このようにほぼ定期そのままのパッケージを提げて来演してくれるのも、現地での活動を垣間見ることができて嬉しい。
さて、それでは今回の東京公演について見ていきたい。昨年に引き続き首席指揮者(2018〜)のマティアス・バーメルトが指揮。演目は中プロを除いて1/31・2/1に行われた第626回定期と共通で、中プロのモーツァルト第39番はディートリヒ・ヘンシェルを独唱に迎えたマーラー『亡き子をしのぶ歌』に変更された。このようにほぼ定期そのままのパッケージを提げて来演してくれるのも、現地での活動を垣間見ることができて嬉しい。
冒頭のシューベルト『6つのドイツ舞曲』。ヴェーベルンの編曲は、最小限の木管と弦5部という編成であり、言わば「素材の味」での正対を演奏者に要求する。素朴な舞曲集でありつつ、第一声からオーケストラの特徴を丸裸にするのだ。演奏会の1曲目として充分適切でありながら、幾分緊張感を伴ったチョイスともいえるだろう―このあたり、知匠バーメルトの意図も滲む。札響は冒頭アウフタクトからぎこちなさの無いフレージングで、旋律線が伸びやかに着地する。それでいながらマーラー並みに細かく記譜されたfpやsf、アクセントを的確に弾き分けているのが見事だ。弦5部の分離・木管の発音ともに明瞭で、先述の「素材の味」も過不足無く味わえた。好調の滑り出しだ。
中プロ、東京のみでの披露となるマーラー『亡き子をしのぶ歌』。バリトンのディートリヒ・ヘンシェルはオペラ、宗教曲、歌曲と幅広く手掛ける実力者であるが、何度かの実演を聴く限りここ数年歌のコントロールが下降線を辿っているようだ。今宵も随所で衰えが目立ち、演奏の平板さを招いた。まずは全曲におけるダイナミックレンジの狭さが顕著で、第1曲最終節の„Heil sei dem Freudenlicht der Welt!“はp、第2曲冒頭„Nun seh ich wohl, warum so dunkle Flammen“はppで管弦楽の中に滑り入るべき箇所であるが、ほとんどmp程度の音量で処理されていた。また高音域をストレスなく鳴らしに行くことが難しく、過剰なヴィブラートを用いた嘆き節で補おうとするあまりアクセントが無い箇所もaccentuareされてしまう。結果として楽曲内での表情の移ろいが淡彩になるのだ。同じ上のFでも、第2曲の„Daß sich der Strahl bereits zur Heimkehr schicke“頂点schickeと第4曲の„Der Tag ist schön auf jenen Höhn! “頂点jenenでは当然ながら全く異なる意味合いを帯びてくるのだが―。細かな指摘を並べてしまったので、ヘンシェルの歌唱の美点にも触れておきたい。一単語が数小節にまたがるような長いスラーを一息で繋ぎつつ、細かな音型も的確に歌っていた点は流石に熟練の技を感じさせた。
この曲でもオーケストラはバーメルトの冷静な棒に導かれ、スコアの忠実な音化に徹した。過度な没入のない音楽作りが却って曲の秘めたる美を炙り出した感すらある。例えば第2曲後半、D-durに転じた第41小節。ハープの躍動に糾われつつ躊躇い気味なため息音型(2度下降)が一瞬顔を出すが、この場面の耽美は既に『大地の歌』終曲の„Die liebe Erde …“を先取りしているではないか。こうした発見が突然やってくるから、よく知ったつもりの楽曲でも実演に接する喜びがある。木管のソロが全曲に散りばめられ、時折応唱も求められるが、札響はいずれも好演。特にホルンの谷瞳は類稀なる美感とニュアンスを醸して絶品だった。後半はassi.に入ってしまったのが残念。
後半のベートーヴェン『交響曲第7番』。屈指の人気曲につき演奏機会も多く、斬新なフレージングやパウゼで衆目を集める演奏も時折聴かれる。ここまでお読みいただければ大方想像に難くないだろうが、バーメルトはそういった特異性には目を向けない。愚直なまでに総譜の指示を実行、且つ弦5部の分離を徹底した。結果浮かび上がったのは音像の細部まで明晰を極めた演奏である。仮に、この曲をリズム面で統一するダクティル(長短短)だけを概括しても相当の数に分類できよう。
バーメルトの執拗なリハーサルは全曲至る局面で窺い知れる。キリがないので両端楽章だけに絞るが、まず第1楽章第256-7、260-1小節の弦5部リレー、第309-18小節のpp(ここを徹底することで第319小節以降のcresc.が活きる)の強調。第4楽章はまず、冒頭動機の叩き付けに続き疾走を始める第1主題の扱い。ffの冒頭動機に続きこの主題も元気一杯のffで突き進む演奏が多いが、バーメルトは幾分音量を意図的に抑え、第26小節から再び楽章頭の音量に戻した。これは?と思いスコアを見ると、成程第5小節からの主題には特に強弱の指示はない。つまり強弱は演奏者次第となるが、バーメルトは「ffではなく中庸」と解釈し意図的に抑えたのだろう。スコアを遵守しつつの踏み込みと言える。そして終盤、第336小節のff(周りがsfなので相対的にかなり鳴らす必要がある)の強奏、第400小節からの長大な低弦オスティナート、第408小節以降の第1・第2ヴァイオリンが掛け合いながらの昂揚もやはりそれぞれ抜かりない。
決して熱に任せて邁進する演奏ではないにも拘らず、音楽から自ずと立ち昇る熱量は圧巻であった。音楽の構造自体が聴き手の眼前に悠然と屹立した、とでも言おうか。その弾き分けと音像の精緻さに、思わずジョージ・セル/クリーヴランド管の同曲演奏をも想起してしまったほどである。偶然か否か、セルとクリーヴランド管の両方とキャリア初期のバーメルトは関係しているのだが―彼の理想の響かせ方として、かの名コンビの音像があるのやもしれぬ。
尾高忠明、ラドミル・エリシュカら熟達の名匠との演奏を聴いてきた札響を、初めて現シェフ・バーメルトの指揮で聴いた一夜であったが―その緻密な共同作業は正直なところ、筆者の予想を遥かに超えていた。幾分無骨な指揮から生み出される音楽の精緻さ・筋の通った説得力に感服し、またそれに見事応じる札響(しかも特有の爽やかな音色の魅力は保持しつつ、だ)にも拍手を贈った。バーメルトの聡明さが作品に光を当てるという意味で、来年1月のブルックナー『第8番』はまたもや目から鱗の鑑賞体験が待つ予感がする。今後も本コンビに注視したい。
著者紹介
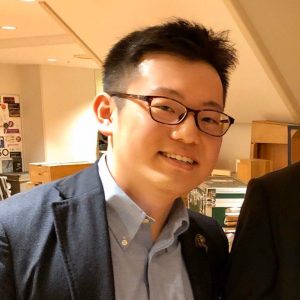 平岡 拓也(Takuya Hiraoka)
平岡 拓也(Takuya Hiraoka)
1996 年生まれ。幼少よりクラシック音楽に親しみ、全寮制中高一貫校を経て慶應義塾大学文学部卒業。在学中はドイツ語圏の文学や音楽について学ぶ。大学在学中にはフェスタサマーミューザKAWASAKIの関連企画「ほぼ日刊サマーミューザ」(2015 年)、「サマーミューザ・ナビ」(2016 年)でコーナーを担当。現在までにオペラ・エクスプレス、Mercure des Arts、さっぽろ劇場ジャーナルといったウェブメディア、在京楽団のプログラム等にコンサート評やコラムを寄稿している。

