<STJ新春エッセイ> いきなり!クラシック – 2022年、コミュニケーションの臨界点から -(執筆:多田圭介)

1)紅白をみた!
大晦日に(一瞬だけ)テレビを付けました。紅白歌合戦が懐メロ大会になっていました。紅白がこうなってどのくらいたつのでしょうか。テレビの視聴者のメジャーな層がほぼ高齢者になってしまったので費用対効果を考慮するとこれが最適解であるのはよく分かるところ。いつの時代でも高齢者が青春時代のノスタルジーに浸るのは当たり前のことだからです。だけどそれを差し引いてもなおこの「紅白の懐メロ大会化」という現象は20年代の文化的想像力のある臨界点を象徴しているように思えました。 2000年以降、この20年というのは、「普遍的な感動や質の高いものはまだある」と言い続けてきた側が負け続けた20年でした。この20年の文化現象は世界的に文脈主義で動いてきました。「美しいモノがある」ではなく自分とアーティストの「美しい関係性がある」という思想です。だから「推しごと」ができればそれでいい。この発想は、「結局のところ文化の感動というものは個人的な体験にしか還元され得ない」という立場を行き着くところまで進めました。自分が投票することで順位が変わるAKBと、目の前の懐メロが二度と戻らない自分の過去であることを確認するたびに何度でも泣けてしまう今の紅白の仕組みは間違いなく地続きです。情報環境に後押しされた文脈主義を誰も倒せなかったのがこの20年。個人の体験に還元され得ないような「この素晴らしい虚構にひれ伏せ!」と言える人は今なかなかいない。
2000年以降、この20年というのは、「普遍的な感動や質の高いものはまだある」と言い続けてきた側が負け続けた20年でした。この20年の文化現象は世界的に文脈主義で動いてきました。「美しいモノがある」ではなく自分とアーティストの「美しい関係性がある」という思想です。だから「推しごと」ができればそれでいい。この発想は、「結局のところ文化の感動というものは個人的な体験にしか還元され得ない」という立場を行き着くところまで進めました。自分が投票することで順位が変わるAKBと、目の前の懐メロが二度と戻らない自分の過去であることを確認するたびに何度でも泣けてしまう今の紅白の仕組みは間違いなく地続きです。情報環境に後押しされた文脈主義を誰も倒せなかったのがこの20年。個人の体験に還元され得ないような「この素晴らしい虚構にひれ伏せ!」と言える人は今なかなかいない。
2)タカラヅカ、インターステラー、コミュニケーション消費の現在
『「タカラヅカ」の経営戦略』という新書をご存じでしょうか。2015年にとても話題なった本です。著者は元宝塚支配人の森下信雄さん。「経営戦略」というタイトルに相応しく、内容はほぼファンコミュニティ運営の推奨です。つまり文脈主義の徹底によって生き残るべしというわけです。この本には、効率よく人の心を動かすものは、”コンテンツ”そのもの(=「美しいモノ」)ではなく、ファンと出演者の”コミュニケーション”(=「美しい関係性」)だという思想があります。同書から、感動という現象は徹頭徹尾「個人の体験に根差す」という思想を読み取る人もいるでしょう。しかも、短期的な流行り廃りのレベルではなく、もっと長いスパンでそう考えられています。もし後世に日本文化論みたいな教科書が書かれるとしたらそういう観点から言及されうるような射程を持っている本です。ゼロ年代以降、日本の文化現象はこの文脈主義をひた走ってきました。プロ野球は地域に根ざした活動に舵を切った球団が経営の面でも成績の面でも勝ち続けた(日ハム、ソフトバンク)。大抵の人は、自分を隔絶した完成された美よりも、”おらが町の〇〇”という自分との関係性をより好むわけです。悲しいかなそれは真実。

この新書のそれはあくまでも「経営戦略」としてみればまっとうな発想です。ただそれを「文化論」として見た場合、文化の自己否定的な側面が見えてきます(※もちろん、同書はタイトルも「経営戦略」と銘打っているわけですからこれをもって同書の価値を否定することには、言うまでもなくなりません。むしろ、議論を徹底して経営戦略に絞り、そこから「だからタカラヅカのコンテンツは素晴らしい」と飛躍させなかったことは誠実だと言えます)。というのは、すべてを個人の体験に還元するということは、小林秀雄風に言えばすべての文化は「様々なる意匠」、すなわちすべては流行だということになります。すべてが流行だということは、全体は部分に帰属させられるということ。ということは全ての世界観は個人に帰属させられ、何が宣言されようともそれは流行宣言を超えることはないということ。そうするとすべての文化現象は「自己のホメオスタシス(自分の快適さの維持)」と自意識のチューニングに必然的に結び付けられてしまうことになります。この20年、普遍的な感動はまだあるはずだと言い続けた人が負け続けたということはそういうことです。
それでは、100%、150%作家がコントロールできるからこそ描けるものとは一体何なのか。それをこの20年貪欲に追及した作家もいることはいる。例えば映画監督のクリストファー・ノーランがそう。ノーランは人間に新しい感覚を付け加えるものは普遍的な感動でありうるという思想を持っています。フロンティアなきところに美も崇高もないというわけです。ただ、彼の反動的な作家主義回帰は(特に近年は)、虚構だからこそ追求できる他者性や想像力をむしろ喪失する方向を向いてしまっている。
 2014年の映画「インターステラー」は(前提として意欲作だし傑作ではある)「どんどん外宇宙へ行ってフロンティアを探してこなければいけない、それが子供たちの未来をつくるんだ」というメッセージを強烈に打ち出しています。しかし、そこで描かれるフロンティアのビジョンがどうしようもなく貧しい。ごくありふれた家族愛を確認して終わってしまっている。たんなる個人の体験を超えた普遍的な感動はあるはずだという信念によって、「冬は寒いから厚着をしたほうがいい」程度の常識を全力で主張してしまっている。新しい世界とも他者とも出会っていない。事はそれほどに難しい(ちなみに、「機動戦士ガンダム」は、人間が外宇宙に出てもせいぜい木星に資源を取りに行く程度のことしかできないというフロンティアの喪失と絶望を、宇宙開発がまだ人類の希望だった1979年の段階で描いている。富野由悠季の知的洞察力と予見性は破格である)。
2014年の映画「インターステラー」は(前提として意欲作だし傑作ではある)「どんどん外宇宙へ行ってフロンティアを探してこなければいけない、それが子供たちの未来をつくるんだ」というメッセージを強烈に打ち出しています。しかし、そこで描かれるフロンティアのビジョンがどうしようもなく貧しい。ごくありふれた家族愛を確認して終わってしまっている。たんなる個人の体験を超えた普遍的な感動はあるはずだという信念によって、「冬は寒いから厚着をしたほうがいい」程度の常識を全力で主張してしまっている。新しい世界とも他者とも出会っていない。事はそれほどに難しい(ちなみに、「機動戦士ガンダム」は、人間が外宇宙に出てもせいぜい木星に資源を取りに行く程度のことしかできないというフロンティアの喪失と絶望を、宇宙開発がまだ人類の希望だった1979年の段階で描いている。富野由悠季の知的洞察力と予見性は破格である)。

いや、コミュニケーション主義(文脈主義)の突破は難しいけれどその危機感の理解は決して難しくはない。紅白が懐メロ大会になっていることの危機感なら誰でも理解できる。その危機感の正体は、実は言葉や理念の危機感からきている。僕らは、言葉や物語、理想こそがローカルな共同体を超えて遠くまで届くと思っていたけれど、実際は物語や理想の正確なニュアンスはごく小さなコミュニティのなかで文脈を共有できる人にしか伝わっていないのではないか。紅白の懐メロ大会化によって揺さぶられる危機感の正体はこの危機感である。コミュニケーションの目的化という事態は実はこういう射程のなかで議論されるべきなんです。
3)「老いた少女」化する理性
コミュニケーションの目的化は文化現象から他者性を喪失させる。それはつまり「訳の分かるもの」、「コントロール可能なもの」に対して大量のリビドーが放出されるということ。これは類比的にみると、例えば母親が子どもに対して訳の分かる存在であることを要求することに似ています。母親自身の生き方を承認する役割を子どもに求める本末転倒とです。本来は、親が子どもを承認するのではなくて、親が子どもに承認してもらうはずですよね。ちょっと前、フランソワーズ・サガンが亡くなったときに関川夏央が「彼女は『老いた少女』のように死んだ」と書いていました。上記の本末転倒を巧妙に表現しています。夏川さんのこの言葉はすごい表現力だと思います。

コミュニケーションの目的化は人を「老いた少女」にしてしまう。AKBメンバーの刺傷事件なんてありましたね。これもおそらくはコミュニケーションの目的化が招いた他者性の喪失=老いた少女化が関係しているはずです。この2年、こんなこともありました。コロナ初期の2020年の4月、札幌のプロフェッショナルの演奏団体に対して、SNS上で演奏会の中止デモが起きました。その演奏会は実際に中止に追い込まれました。コロナの騒動が2月に始まったばかりで、まだその全貌が分からない状況。この状況で「人の命」という最強の盾を隠れ蓑にすればどんな暴力でも正義の名のもとに正当化される。老いた少女たちの普段抑制している暴力性が爆発した好例だったと思います。起こるべくして起こった事件だと思います。もう一つ、コミュニケーションの目的化=老いた少女化は情報環境によって後押しされています。これについて気づかされることもありました。

この演奏会潰しを、自分の名前と顔を晒して主催者に意見できたひとはどのくらいいたでしょうか。20世紀に現代思想や生物学の分野で、「人間の暴力性、攻撃性を制御しているのは、果たして理性と身体のどちらなのか」ということが盛んに議論されました。普通に考えると、動物的な身体の攻撃性を理性が抑制していると考えがちです。だけど、逆なのではないかと。生物学者のコンラート・ローレンツの説にあるように、オオカミは一方が「負けました」と喉を晒すともう一方はもう噛めない。噛もうとしても身体がストップをかけるのだそうです。ローレンツは人間の場合も最終的に攻撃性を抑制するのは身体なんじゃないかと言っています。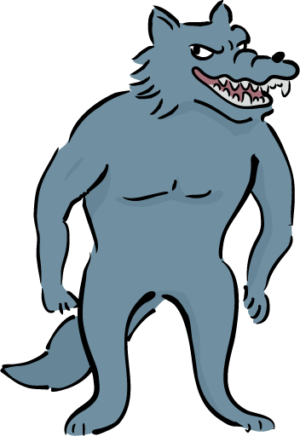 一昨年の演奏会中止デモも、身体と顔を晒さない理性というものがどれほど攻撃的なのかということを証明したように思えます。もし演奏会の中止要求が「暴力性によって」ではなく「正しさ」のために行われていたという人がいたらどうでしょうか。もしそうなら、自分の顔と名前を晒して、先が見えない状況で錯綜する状況を勘案して次善の選択として開催に漕ぎ着けた主催者の顔を見て、その要求ができたはずです。しかしそうではなかった。それが証明しています。SNSでは直接顔を合わせているときに身体が担保している抑制が効かなくなるからです。
一昨年の演奏会中止デモも、身体と顔を晒さない理性というものがどれほど攻撃的なのかということを証明したように思えます。もし演奏会の中止要求が「暴力性によって」ではなく「正しさ」のために行われていたという人がいたらどうでしょうか。もしそうなら、自分の顔と名前を晒して、先が見えない状況で錯綜する状況を勘案して次善の選択として開催に漕ぎ着けた主催者の顔を見て、その要求ができたはずです。しかしそうではなかった。それが証明しています。SNSでは直接顔を合わせているときに身体が担保している抑制が効かなくなるからです。

これは米軍の空爆と同じ。傷つく相手が見えない状況でボタンを押すだけだから、いくらミサイルを撃ち込んでも殺傷のリアリティがない。事務仕事みたいにこなすことができてしまう。この問題も宝塚の経営と同様にけっこう射程が長いんです。M.マクルーハンが『グーテンベルクの銀河系』という本で、大量殺戮が起こるようになった時代と世界地図が作られた時代が重なると述べています。ウェストファリャ・システムです。世界像がバーチャルになるときに攻撃性が抑制できなくなるというのは、けっこう昔から言われていることなんです。理性による抽象化っていうのは教養の基本中の基本ですが、それが同時に暴力性を喚起するということです。抽象化によって身体が抑制していた暴力性が発動される。理性の二重性ですね。吉本隆明が『自立の思想的拠点』で、”自分の拳で表現できない思想を語るな”と言っています。この言葉は今のSNS時代にとてもインパクトがあります。翻訳するなら「自分が今しようとしていることが、相手の顔を見て、自分の顔を晒した状況でも、それでもすべきと思えるか、常に自分に問いかけながら行為せよ」となるでしょう。結局のところ、人は言葉ではなく身体で動いているのかもしれない。いや、それでは理性はただ邪魔者になってしまうではないですか。それではショボすぎる。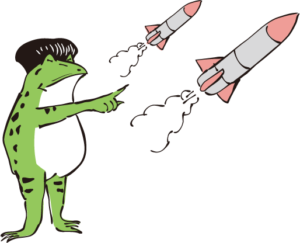
4)2022年、コミュニケーションの臨界点から
私たちは理性、言葉や想像力こそが、ローカルな共同性を超えて遠くまで届くと信じていたけれど、情報環境によって露呈した現実は逆のほうを向いてしまっています。2022年、コミュニケーション消費の臨界点でこの現実を見せつけられていのが今です。もう一度、言葉に、理性に、次のページをめくりたいと思わせるような物語を語る機能を取り戻せないか。それは、やはりコミュニケーション消費のなかにではなく、作家が100%コントロールできるコンテンツ消費のなかにしかないのではないか。もちろん、どんなコンテンツであってもそれが「自己(作家の)」に帰属してしまうことから逃れることはできない。永久に逃れられない。でもそれでも構わないんだと考えて前に進まないと物語は語れない。それで構わないという態度が、「脱自己化」と「自己への再参入」の二重性としてのコンテンツ創造ということなります。親鸞風に言い換えれば、往相(脱社会)と還相(社会再参入)の二種回向ということになります。その自己からの脱出方法が安直だとインターステラーのようにありふれた家族愛になったり、宮崎駿のようにお母さんっぽいヒロインが主人公の少年に完璧な承認を与えて全能感をゲットして万事解決となってしまう。超越は断念されざるを得ない。
 けれど、断念しつつ、同時に諦めずにそれに触れそうな言葉を次々と繋いでゆくことしか人間にはできない。矛盾しているけれど、自己を超えた言葉を正しく諦めた人間だけが、逆説的に、自己を超えた言葉に開かれる(かもしれない)。文化現象からこういった思考の運動性を宿したコンテンツの機能、すなわち物語を語る機能を取り戻すこと、コミュニケーションのダシとしてではなく、いきなり!コンテンツに飛び込むこと、2021年の暮れに紅白を(一瞬だけ)見てそんなことを考えましたということでした。クラシック音楽や舞台芸術の世界でもこうした流れをカウンターとしてではなく本流として取り戻すことはできないものかと。2022年、コミュニケーションの臨界点からご挨拶に代えて。今年も本紙のお引き立てをお願いいつつ(何様)。
けれど、断念しつつ、同時に諦めずにそれに触れそうな言葉を次々と繋いでゆくことしか人間にはできない。矛盾しているけれど、自己を超えた言葉を正しく諦めた人間だけが、逆説的に、自己を超えた言葉に開かれる(かもしれない)。文化現象からこういった思考の運動性を宿したコンテンツの機能、すなわち物語を語る機能を取り戻すこと、コミュニケーションのダシとしてではなく、いきなり!コンテンツに飛び込むこと、2021年の暮れに紅白を(一瞬だけ)見てそんなことを考えましたということでした。クラシック音楽や舞台芸術の世界でもこうした流れをカウンターとしてではなく本流として取り戻すことはできないものかと。2022年、コミュニケーションの臨界点からご挨拶に代えて。今年も本紙のお引き立てをお願いいつつ(何様)。
さっぽろ劇場ジャーナル 多田圭介
※「投げ銭」するための詳しい手順はこちらからご確認いただけます
この記事はこちらの企業のサポートによってお届けしています


