ローカルな“ヴォルフガング”が、グローバルな“アマデウス”になるまで ~「強い国アメリカ」から読み解くモーツァルト像~(執筆:越水玲衣)

|
INDEX |
小6の秋、偶然テレビの日曜洋画劇場で「アマデウス」を観て、一夜にしてモーツァルトに魅了された。それ以来、まるでサリエリのようにモーツァルトを追いかける人生が始まった。しつこく映画を視聴した回数は延べ300回あまり。しかしこういう「どハマリ人生」を生きていると、考え方や好きな曲の傾向、周辺情報など、年月を経るごとに興味があちこちに飛ぶのが面白い。最初の興味は純粋に生涯と音楽について。中高生の頃は、とにかくたくさんの曲を知ること、聴くことが楽しかった。大学に通っていた頃はピアノ協奏曲第20番にハマった。そして音楽に潜む魔性と宗教性が気になってどうしようもなくなり、それが最終的に卒論のテーマになった。数年前は彼の(書簡に残っている)言葉について。ブログ運用を通して、現代に通用する名(迷)言を掘り起こすことに熱中してきた。
ここ 1~2年の興味はもっぱらこれだ。
「モーツァルトとアメリカって何か似てない?」
「アマデウス」からモーツァルトとアメリカに迫る
こんな漠然とした直観(霊感?)が時々脳裏をかすめる。モーツァルトとアメリカの類似性?親和性?もちろん彼の人生に、アメリカなど「ひとかすり」もしていない。強いていえば1776年、モーツァルトが20歳の年にアメリカが独立宣言をしたくらいだ。しかし遠い新大陸の独立を、彼が新聞でも噂話にでも聞いて、それに興味を示したかといえば何の記録もない。この時点ですでに関係なさそうだ。しかもこれを知ったところで何になるのか?その程度のお題かもしれない。それでも自分には、そこに見えない重要な意味、何かの赤い糸を感じる。そう、問いはいつだって白昼夢のように、突飛な夢想から始まる。
とはいえ、まず両者を結び付けたくなる絶対的な理由がある。なんといっても映画「アマデウス」だ。これがヨーロッパ映画ではなく、バリバリのアメリカ映画だということ。そしてクラシック音楽や時代物を扱っているにも関わらず、マニアックな人気にとどまらず大ヒットしたことだ。公開後のアメリカでは、一時的にモーツァルトへの人気が爆上がりし、ヒットチャートにモーツァルトの音楽が躍り出たと何かで読んだ。ピーター・シェーファーの原作の面白さ、衣装の生地へのこだわりや、ロウソクのみでの夜間照明など、18世紀ウィーンをほぼ完璧に再現しようとした映画的クオリティの高さから、この映画がアカデミー賞8部門を独占受賞したことは充分に理解できる。しかしヨーロッパの一作曲家の映画が、なぜこれほどアメリカで受け入れられたのだろうか?(そして私はなぜ、こんなにハマったのか?)
映画「アマデウス」は、アメリカ映画史の中でどんな位置づけで存在し、アメリカの人々にとっては何が魅力だったのだろうか。正直なところ、自分は特に「アメリカ」大好き人間ではない。居住も留学も考えたことはないし、銃社会が怖い。アメカジも着ないし、観光で訪れたいのはハワイのみ。それでも子供時代から今にいたるまで、とにかく「アメリカ映画」にはどっぷり浸かって生きてきた。アメリカ映画なしに、私の精神は形成されなかった。Z世代にとってのアメリカとは「GAFA」や各種動画配信サービスかもしれないが、それより上世代の日本人であれば、まずは映画に影響を受けて育ってきたのではないか。自分もその一人だ。

舞台と映画、2つの「アマデウス」
まずは基本情報をザックリおさらいしよう。映画「アマデウス」は1984年に公開された(日本公開は1985年2月2日:松竹富士)アメリカ映画である。制作はソウル・ゼインツ。監督は、当時社会主義国だったチェコ(旧・チェコスロバキア)から、プラハの春がきっかけでアメリカに移住してきたミロス・フォアマンだ。原作はイギリスの劇作家ピーター・シェーファーの戯曲「アマデウス」。その舞台版「アマデウス」は、1979年ロンドンのロイヤル・ナショナル・シアターで初演された。舞台はすぐに話題になり、翌年1980年にはニューヨークでも上演されている。
あらすじはこうだ。神童モーツァルトと、彼を毒殺したと長年噂されてきた宮廷作曲家アントニオ・サリエリ。モーツァルトの死後32年たった1823年のある日、老いたサリエリは突然錯乱し、こう叫んだ。「わたしがモーツァルトを殺した!」。
舞台はサリエリのモノローグと回想シーンで進んでいく。18世紀後半、早い頃からウィーンの宮廷音楽家として成功していたサリエリ。社会的にも成功し、自分の音楽にも満足していた。しかしある日、フリーランスの若き音楽家ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトと出会ったことで、運命が狂い始める。モーツァルトの音楽に、苦痛を感じるほどの美しさを見たのだ。それに比べて自分の音楽はどうだ?彼はモーツァルトの才能に激しく嫉妬した。同時に、幼稚で自己中心的なモーツァルトの人格にも激しい嫌悪感を抱いた。「どうして神は、あれだけ祈り、全てを音楽に捧げた私にではなく、アイツを選んだのか」と、理解に苦しんだ。苦悩の果てに、ついにサリエリはモーツァルトを死に追いやろうと密かに計画をたてる。それはつまり「真の才能」を自分に与えてくれなかった「神」への挑戦でもあった――
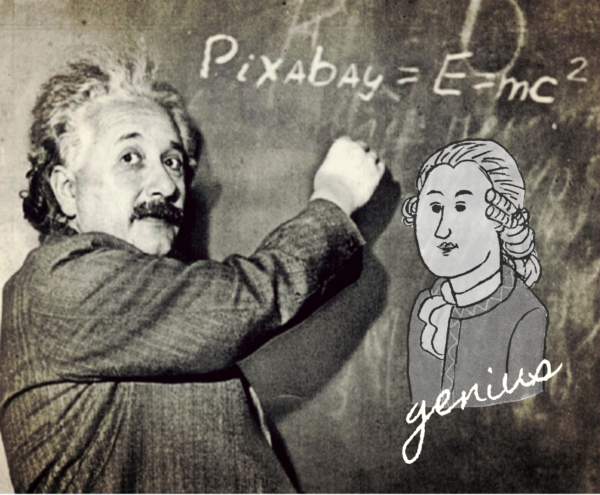
「面白い作曲家映画」というミッションインポッシブル
歴史的エピソードをもとに書かれた作品ながら(実際はサリエリがモーツァルトを殺した事実はない)2人の確執をあえて醜悪すぎるほどにデフォルメし、ショッキングなインパクトを与える作品である。内面の闇を深くえぐるストーリーは、神や悪といった哲学的な問いについても、深く考えさせてくれるはずだ。
この舞台の映画化の話だが、1970年代の終わりにはすでにフォアマンのところにやってきたという。しかし彼は浮かぬ顔をした。その理由が振るっている。
「作曲家の出る映画で面白かったことなんてあるか?」
思わず笑ってしまった。掛け値なしで、率直すぎる発言だ。芸術作品と市場のニーズ、両者のバランスを読む感覚がフォアマンにはあったのだ。劇場には物語を深く読み取れるコアな客層がいる。しかし映画館はそうではないのだ。モーツァルトやサリエリを何も知らずにやって来て、2時間40分(それでも長い)で面白いと思ってもらえなければ意味がない。つまり採算が取れないということを「アメリカ人になった」フォアマンは理解していたのだ。だからこそ徹底的に面白い「作曲家映画」にしてやろうと目論んだ。

そこで彼は、原作者のピーター・シェーファーと大胆な脚本改変を試みる。2人は週末ごとに集まり、映画版の脚本作りにいそしんだ。できあがった脚本は、舞台とは全くの別物である。ショー化されたオペラシーンがふんだんに盛り込まれ、音楽が占める割合が激増した。あの印象的なモーツァルトの高笑い。美しい夫婦愛。舞台では徹底的にモーツァルトを追い詰めるサリエリが、映画では何とモーツァルトの作曲を手伝う――
ここでよくある問いをたてる。フォアマンは「敷居を下げた」のか?いや、そうではないと思う。彼は別の敷居、別の入り口を用意したのだ。「80年代のアメリカ社会の価値観」に合わせて作り変えたのだ。当時のアメリカ人が、共感しながら自然に世界観に入り込めるような切り口を作ったということである。リアルタイムのアメリカ社会を、18世紀のウィーンで表現する。おそらく「ヨーロッパ人」のシェーファーにとって、それはまるで理解に苦しむ改変だったと思われる。毎週末ごとに激しく口論し、互いをディスり合いながら作業を進めたというから、かなり抵抗を示しただろうことは想像に難くない。
「アマデウス」が作られた80年代アメリカ
では、映画「アマデウス」がどんなふうにアメリカで受け入れられたのかを探っていこう。まずは公開当時80年代のアメリカ社会が、どんな空気感に包まれ、その中で人々はどのように生きていたか、ということから。それを見極めるには、NHK Eテレで放送された番組「世界サブカルチャー史 欲望の系譜 アメリカ葛藤の80’s」がかなり使える。
1980年代のアメリカ。それはベトナム戦争の敗北と大不況という、国家的なトラウマから再び元気を取り戻しつつある時代だった。もともと熱狂好きだった人々の生活に、エンタメ的な要素がさらに入りこんでくるようになる。映画産業は飛躍的に大きくなり、ハリウッド大作やシリーズが次々に生まれた。子供そっちのけで、コンピューターゲームに熱中する大人たち。24時間配信の音楽番組「MTV」が開始され、音楽を家で「シャワーを浴びるように」聴くことができる生活に。マイケル・ジャクソンやマドンナ、シンディー・ローパーの歌が流行。そして1984年のロサンゼルス・オリンピック開会式では、世界中に「エンターテイメント大国」をアピールした。そんな1980年代を象徴する人物がいる。合衆国第40代大統領(元俳優の)ロナルド・レーガンだ。在位は1981年1月~1989年1月。ドンピシャすぎる。しかしレーガンの政策は自由主義アメリカの自己責任論をさらに推し進めた。強い光には強い影ができるものだ。「世界がうらやむ」アメリカも、個人レベルでは深刻な問題を抱えていたのだ。
もっと成長を、もっと出世を、もっと快楽を。資本主義経済は、人々の欲を取り込んで、どこまでも成長を求め続ける。セレブたちは金儲けとパーティー三昧の日々。かたや一般庶民は食の快楽を求め、ファストフードを頬張る日々(そして肥満になる)。

一見、華やかで浮足立ったように見える80年代アメリカ。しかしその舞台裏を覗いてみれば、いたるところに「ひずみ」が見え始めていた。例えば家庭だ。外から見れば何の問題もなさそうな理想の家庭など、もはや虚像に過ぎなくなっていた。実際は夫婦はすれ違い、子供は自分の殻に閉じこもる。『大草原の小さな家』のような古き良きアメリカの家族(日本なら、さしずめ『サザエさん』)は、もはや形式的な「家族ごっこ」になり始めていたのだ。若者のアイデンティティも、上昇志向の影では強い劣等感や苦悩を生んでいた。若者は田舎を飛び出して「成功したい。何者かになりたい」と都会に出るか『愛と青春の旅立ち」のように軍に入り、アイデンティティを求めて彷徨う。なによりも、国際的な「アメリカ」という国の立ち位置だ。「世界の警察」として、政治的にも経済的にも「世界のヒーロー」的な存在ではあるが、そこに住む人々の内面には、どこか空虚なすきま風が吹き始めていたのだ。
番組では、80年代の光と闇を読み解くキーワードとして(7つの大罪にあやかって?)7つの要素をあげ、当時の「映画」を参照しながら時代の中核に迫っている。その7つとは、①虚飾(家庭崩壊を隠蔽するための見栄)、②焦燥(若者の強い上昇志向)、③愛国(強いアメリカを取り戻す)、④郷愁(ここではない世界・ユートピアへの憧れ→テーマパークの乱立)、⑤自虐(自堕落さに溺れる→ドラッグ)、⑥欺瞞(成功に隠れた心の闇)、⑦強欲(儲けを優先して何が悪い?)
以下、番組に登場した作品をリストアップしてみた。加えて私自身の独断で、ここで重要と思われる数作品をつけ足している。(もちろん「アマデウス」もだ)こうして見ると、80年代は本当に傑作揃いだ。いまだに何度も観られたり、シリーズ化されたり、当時生まれていなかった世代までもが知っている作品ばかりである。
| 1977年 | 「スター・ウォーズ エピソード4/新たなる希望」 |
| 1980年 | 「ブルース・ブラザース」 「スター・ウォーズ エピソード5/帝国の逆襲」 「普通の人々」 |
| 1981年 | 「レイダース/失われたアーク《聖櫃》」 ※MTV開始(24時間配信の音楽チャンネル) |
| 1982年 | 「E.T.」 「愛と青春の旅立ち」 「ランボー」 |
| 1983年 | 「フラッシュダンス」 「スター・ウォーズ エピソード6/ジェダイの帰還」 |
| 1984年 | 「インディー・ジョーンズ/魔宮の伝説」 「ビバリーヒルズ・コップ」 「ベスト・キッド」 「アマデウス」 「ゴーストバスターズ」 ※ロサンゼルス・オリンピック開催 |
| 1985年 | 「ランボー/怒りの脱出」 「バック・トゥ・ザ・フューチャー」 「グーニーズ」 |
| 1986年 | 「トップガン」 「プラトーン」 「スタンド・バイ・ミー」 |
| 1987年 | 「摩天楼はバラ色に」 「ウォール街」 |
| 1988年 | 「バットマン」 「インディー・ジョーンズ/最後の聖戦」 |
では、これらの映画に「7つのキーワード」を当てはめてみよう。「愛と青春の旅立ち」「トップガン」「摩天楼はバラ色に」(3作とも②と③の複合)、「フラッシュダンス」(②)「普通の人々」(①)、スター・ウォーズシリーズ、インディー・ジョーンズシリーズ、「バック・トゥ・ザ・フューチャー」「スタンド・バイ・ミー」(未来であれ過去であれ異世界であれ、どれも④の変形態)、「ランボ―」(③と⑤と⑥の複合)、「ウォール街」(⑦)など、当時の空気を絶妙に反映している。(みなさんも思い思いの映画に当てはめてみると楽しいですよ)
そして「アマデウス」には、これらの要素は含まれているか?もちろん。ほぼ網羅しているといっても過言ではない。
「アマデウス」キーワードとの合致点を探る
①虚飾Vanity
舞台版では、サリエリが辟易するほどの「変人同士」だったモーツァルト夫婦。それが映画版ではモーツァルトの生々しい女性関係はカットされている。そして「恋愛結婚で結ばれたアメリカの中流家庭」的な夫婦像に変えられた。コンスタンツェのキャラクターも、より一般受けする女性になった。フリーランスで独立した夫を、精神的にも金銭的にも支えようと奮闘する若き妻になった。傍から見ればうまくいっているようでも、内部では崩壊寸前の家族の絆。当時のアメリカの平均家庭の抱える問題点は、映画の中のモーツァルト家も同じである。
②焦燥Impatience
モーツァルトの、自分の才能への確固たる自信。映画版ではより魅力的に描かれ喝采を誘う。例えばモーツァルトがサリエリの作曲したマーチを即興で編曲してしまう「大人をギャフンといわせる」シーンだ(実は、小6の初期反抗期を迎えていた自分が一番刺さった場面はここ)。なぜなら80年代アメリカでは「強い向上心」は美徳だからだ。誰もが人より成功したい。そしてそれを露骨にアピールすることも場合によっては「保守的な大人たち」への反抗として迎え入れられる。マーチのシーンはその象徴だ。
③愛国Patriotism
映画「アマデウス」では、自国語(ドイツ語)オペラの上演を実現させるシーンにかなりの時間を割いている。イタリア人に牛耳られた宮廷に「ドイツ」を取り戻そうと奮闘するモーツァルト。これはそのままレーガンの謳った「強いアメリカ」にすり替えることができる。映画では、ドイツ語オペラのシーンはアメリカでの母国語である英語で歌われている。映画の中で、モーツァルトは「ドイツ的美徳とは」と聞かれて「愛です」と答えるが「愛」を美徳と考えているのはドイツではない。それは他でもないアメリカである。
この愛国意識だが、映画の中だけの話ではない。当時、撮影のためプラハ入りした出演者や撮影クルーにも、やはり「世界一の先進国アメリカから我々はやってきた」という優越意識があったようだ。そのことが暗に窺える資料がある。2020年に公開された「アマデウス ディレクターズカット」の特典インタビューだ。そこで当時のキャストたちは、口を揃えて「社会主義国の文明の遅れ」を驚きをもって伝えている。一方で、撮影を許可したチェコスロバキア側もピリピリしていた。「モーツァルトの映画を撮りたい」とやって来たアメリカ人たちに常に目を光らせていた。盗聴、観客役のエキストラに紛れていた秘密警察・・・「アマデウス」は、スクリーンの中だけではなく、現実でも「強い国アメリカ vs 社会主義国」という冷戦構造の板挟みになりながら作られたのだ。
④郷愁Nostalgia
アメリカ人は「未知のもの」「古き良き時代への憧憬」「ごっこ遊び」に寛容だ。というか大人も子供も大好きだ。ディズニーやラスベガスなどを始め、テーマパーク的世界を常日頃求めているといっていい。元来ミーハー気質なのかもしれないが「つらい現在から逃げる」手段でもある。「アマデウス」もひとつのテーマパークだ。フォアマンが撮影場所をチェコのプラハに選んだのは、自分の故郷に帰りたかったからではない。当時社会主義国だったチェコは近代化が遅れており、街でカメラを360度まわしても、近代的な建物がいっさい映り込まなかったからである。その中で行われるオールロケ。当時の衣装の再現、床の軋みの音。昼間は自然光で夜はロウソクのみの照明。エキストラの人選(現地調達)まで。細部にこだわった再現性は、本当に18世紀のウィーンにいるような錯覚をおこさせてくれる。
⑤自虐Self-deprecation
ディレクターズ・カット版を観て改めてわかったことだが、モーツァルトの女性問題と金銭問題はほぼカットされているが、酒と薬(ドラッグ)に溺れる姿は残された。80年代アメリカは、豊かさに溺れ自堕落な生活に陥る者が増加していたのだ。というかアメリカはもともとドラックとはかなり親和性が高い。入植後の布教活動やカルト集団、ヒッピーやアーティストなど、ドラッグを肯定的に受け止めて「高みに至る手段」としてきた歴史は長い。
⑥欺瞞Deception
都会の仕事人間は闇(病み)が深い。そこで彼らはカウンセラーやセラピストに通う。舞台版でサリエリは観客に向かって自分のしてきたことを告白するが、映画版では観客の役目は救護院(精神病院)に一時収容されたサリエリに面会に来る神父に引き継がれている。神父は「カウンセラー」「セラピスト」として、サリエリの話に最後まで傾聴するのだ。するとサリエリに思わぬ気づきが訪れ、ラストでは安堵の表情に変わる。ラストシーンからクレジットに続く音楽が、舞台版で使われていた「フリーメーソンのための葬送音楽K.477」から「ピアノ協奏曲第20番K.466」の第2楽章(中盤のドラマチックな部分はカット)に最終的に変更されたのも、サリエリがすでに「癒された後」だからだ。この映画は「ひとりの男が他人に自分の闇を話すことで癒しが起こる物語」でもあるのだ。
⑦強欲Greed
有り余る上昇志向は、時として「ルール違反」も是とするほどに膨れ上がる。「摩天楼はバラ色に」でマイケル・J・フォックスがコミカルにやってみせた、あり得ない「社内ダブルワーク」は、出世のための手段を択ばないやり方だ。「アマデウス」でも、大司教に「そんなに僕が嫌ならいっそ解雇してください」と願い出たモーツァルト。実際のモーツァルトもこの頃は「ダブルワーク」で独立を目論んでいた。より自分を「高く買ってくれる」場所へ。合理的なビジネス精神、もらえるはずの報酬を堂々と要求すること、それのどこ悪いのか。モーツァルトは欲望に忠実な若者のアイコンだ。
まだまだ見つかる「アマデウス」のアメリカ
このように当てはめてみると、「アマデウス」がこの上なく「アメリカ映画」だということが理解できるのではないだろうか。映画のヒットは、チェコ人だったフォアマンのアメリカの空気を読むドライさにあった。ではここで、ストーリーとして、また映画の手法として、アメリカ的だと思われる部分をもう少し挙げてみよう。
①魅力的なキャラクターづくり
80年代アメリカ映画では、キャラクターが魅力的なこと(殊に主人公)は最重要事項だ。舞台版でのモーツァルトとサリエリは両者ともに、あまりにもイヤな奴だった。アメリカ映画では(ソ連が相手でなければ)悪役だって、それなりの魅力が必要なのだ。
サリエリの意地悪は軟化され、菓子のつまみ喰いがやめられない病的な部分は削除。大人の色気を感じさせ、成功した人間としての品格を湛えながらも嫉妬心に苦しむ葛藤を抱えたキャラクターに変わった。不健全なナルシズムで悪口をまき散らすモーツァルトは、社会人になりたてのアメリカ青年のようになった。不器用でKY、独特の間の悪さがユーモアを誘う。外見はよりアイドル的になった。そして演奏している時と指揮をしている時は、ロックスター並みに輝いて「魅せる」。これぞギャップ萌えだ(私はまんまと引っかかった)。

②3時間弱で「にわかファン」に
「エンタメ性」は、アメリカ人が建国以来持ち続けてきた気質・メンタリティの中心である。過去15世紀から始まるアメリカでの宗教の布教活動には、エンタメ的・ショー的な要素が欠かせなかった。理想社会を求め、カリスマ的な布教者(もしくは「教祖」)が聴衆を熱狂させ、集団でトランス状態になり、異言を話す。そうして数多の「新宗教」が乱立した歴史がある。今でもアメリカでは、見えない力・疑似科学・超常体験が妙に好きだ。映画であれば、その代表的なものは「フォース」だろう。ジェダイの騎士の哲学は「ジェダイ教」としてすでにフィクションの枠を超え、一部の人々によって信仰されている。アメリカの作家カート・アンダーセンは、著書『ファンタジーランド 狂気と幻想のアメリカ500年史(上・下)』で、アメリカ人の熱狂しやすい国民性を、内なる子供(インナー・チャイルド)になぞらえて説明している。著書によれば、アメリカの精神とは「終わらない子供時代」「いつまでも続く熱狂」である。

そこでフォアマンは「アマデウス」映画化にあたり、アメリカ国民の「熱狂しやすさ」を、オペラシーンを大幅に増やしライブ感を出すことで応えた。そしてオペラを観ている客席の興奮を臨場感たっぷりに伝える。実は「アマデウス」には、オリジナルの楽曲(“〇〇のテーマ”など)や効果音がない。ミュージカル映画とも違う。全編が演奏された音楽(もしくは登場人物の脳内で鳴っている音楽)だけで構成されているのだ。つまり登場人物には聞こえていなくて、スクリーンを見ている観客だけが聞こえている音楽「BGM」がない。観客は登場人物と完全に音を共有しているのだ。これはよくよく考えると、かなり変わった映画音楽の使い方である。そして映画自体がいわば「モーツァルトの音楽のカタログ」になっているのだ。しかもクラシックに疎い客層に向け、老いたサリエリ自身がモーツァルトの聴きどころを(神父に説明するというかたちで)わざわざ解説してくれる。こんなご丁寧なことはない。
こうした音楽の使い方が、さらに「18世紀ウィーンへの没入感」を高めてくれる仕掛けになっているのだ。まずはにわかファンでいい。熱狂させ、一瞬で心を掴む。フォアマンは後に、ディレクターズ・カット版のインタビューで、こう語っている。「歴史が200年かかってやってきたことを、我々は2時間40分でやってのけたわけさ」
③バッドエンドよりハッピーエンド
舞台版では、モーツァルトとサリエリは完全に憎みあう。しかしアメリカ映画では、往々にしてこんなシーンはないだろうか。弱虫だった主人公が一念発起して勇気を出し、悪いヤツを倒す。すると突然「お前もなかなかやるじゃないか」と一目置いてくれるという。「バック・トゥ・ザ・フューチャー」でビフを殴ったマイキーの父親は、こうして立場が逆転した。「ベスト・キッド」もそうだ。
アメリカでは、どんな人間でも一発逆転、能力次第でまわりの評価が180度変わる。だからバッドエンドよりハッピーエンドがウケる。清涼飲料水のような、さわやかな後味のラストでなければいけないのだ。人間関係も同じことだ。さまざまな解釈を必要とする複雑な人間関係よりもわかりやすい勧善懲悪を、修復不可能な憎悪よりも友情に変わる可能性を感じさせる関係が好まれるのだ。

「アマデウス」でも、ちゃらんぽらんなモーツァルトを見るに見かねたサリエリは、妨害しつつも事あるごとに助けてしまう。一方のモーツァルトも、自分が嫌われていることを自覚しながらも結局サリエリをどことなく頼っている。そこに「奇妙な友情」が芽生えてしまっているのだ(あくまで潜在的なレベルだが)。
ラスト20分、彼らは「レクイエム完成」というひとつの目標に向かって力をあわせる。サリエリとしては、一刻も早くモーツァルトにレクイエムを完成させたのちに殺したい一心で手伝い始めるわけだが、同時に、モーツァルトのいわば「聖域」に踏み込めることに興味をそそられている。「ついに、神の源泉に触れる瞬間に立ち会える」禁断の悦びに打ち震えるサリエリ。しかし衰弱しきった中で、必死にレクイエムのオーケストレーションを指示するモーツァルトを前に「コイツ、やっぱ凄いわ・・・」と圧倒され、殺そうとしていたことも忘れて記譜に夢中になってしまう。もはやサリエリは、ただ「音楽」というものが持つ強烈な魅力に突き動かされてしまっていた。
一方、衰弱しきったモーツァルトも、もはや自分だけでは音を「出力」できないでいた。ここはサリエリの手に託すしかない。モーツァルトは素直に「自分はあんたに嫌われていると思っていた」と打ち明け、それを詫びた。そして曲が出来上がるまで「ここにいてくれる?」と懇願するのだ。この憎しみとリスペクトのギリギリの線をいく、緊迫しつつも熱い感情。まるで同じチームながらもライバル同士だった2人が、大事な試合で一転協力し合うような面白さがある(「トップガン」のマーヴェリックとアイスマンの関係にも似ている)。そして32年後、サリエリは若き神父にモーツァルトとの思い出を話すのだ。かつての戦友を懐かしむように。
僕はモーツァルトのようになりたい
こうしてWolfgang Amadeus Mozartは、ローカルな「ヴォルフガング」から、グローバルな「アマデウス」になった。「Amadeus」とは「神に愛されし者」という意味がある。アマデウス――「狼の道」を意味する「Wolfgang」よりも、格段に普遍性を感じさせるネーミングではないか。そしてこの言葉は、単なる人物名称を超えて「天才性を端的に表現する記号」として機能し始め、これ以降「アマデウス」という言葉を使った作品が生まれることになる。
ここで最初の問いに戻ろう。80年代のアメリカ社会では、誰もがアマデウス「神に愛されし者」になりたいと思っていた。そして無邪気にも「なれるはずだ」と沸いていた時代だった。だから映画「アマデウス」は熱狂的に迎え入れられたのだ。神に愛されるとはどういうことか?それは「自分の才能によって、人生の成功や幸福をつかめる者」ということだ。公開当時、モーツァルトにまるでロックスターのように憧れた若者は多かった。ブロードウェイでもハリウッドでもいい。いやシリコンバレーのイノベーターとして才能を発揮するのでもいい。とにかく自分らしく成功したい。
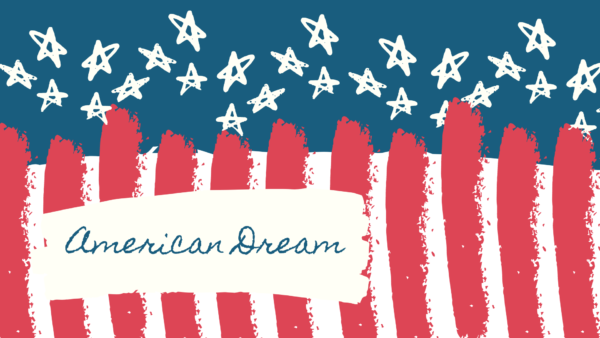
映画の中で少年時代のサリエリは、父に「僕はモーツァルトのようになりたい」と訴えるが、ラストシーンでは神父に対し「私はその(モーツァルトになりたい者の)代表者だ( I am a champion.)」と、どこか悟ったように言って去る。大切なのはここだ。サリエリは80年代のアメリカ社会が抱える欲求を代弁者として代表している。「そういう欲求を満たそうとする戦いは、どことなく虚しい」ということを示唆しているのだ。
前述したが、この時のエンドロールの音楽を「フリーメーソンのための葬送音楽K.477」から、最終的に「ピアノ協奏曲第20番K.466」の第2楽章(中盤のドラマチックな部分はカット)に変更したことは、本当に秀逸な選曲だと思う。第2楽章のメロディには無為な戦いを終えた後の疲労感、そして「もう誰かや何かと戦わなくてもいいんだ」という静かな安堵と平安が感じられるのだ。この、ミロス・フォアマンの「時代の功罪」を見通す先見の明。この選曲に「アマデウス」の全てが詰まっている。そう言っても過言ではない。
余談だが、1984年という同時期に旧・西ドイツでもモーツァルト映画が公開されている。「くたばれアマデウス」(原題:Vergesst Mozart /英題:Forget Mozart)だ。時期的に舞台版「アマデウス」の影響なのか、プラハで撮影されていた映画「アマデウス」の関係筋で「我が国でも」となったのか。あるいは全くの偶然か。映画のファーストシーンからすでに似通っているから驚きだ。血みどろの蝋人形たちが転がる部屋。そこで何らかの惨劇があったことがほのめかされる。「モーツァルトを殺したのは誰なのか?」真犯人は意外な場所の、意外な人物だった――というミステリー仕立ての物語だ。
「くたばれ~」は「アマデウス」の親しみやすさとは反対で、彼のデーモニッシュな面をクローズアップしている。モーツァルトが「魔術的な魅力で動物までをも操る、神出鬼没の謎めいた男」として描かれているのだ。フリーメーソンの参入儀礼なども描かれていて、啓蒙時代を生きたモーツァルトの知られざる一面にスポットを当てている。しかも「アマデー」と呼ばれている!(史実ではこちらの呼び方が正解らしい)さすが本場だ。だが史料としてはいいが、ヒットするか、多くの人に受容されるかといえば、答えは「ノー」だ。ともあれ「アマデウス」を補完する映画としては良い作品なので、DVD化されていないのが惜しい。
実際のモーツァルトとアメリカ
映画によってモーツァルトは、あるひとつの現代的な「アイコン」として定着した。では、実際のモーツァルトはどうだったのだろうか?確かに彼は(自身の死で叶わなかったが)いつかはヨーロッパの近代大国イギリス(ロンドン)の音楽市場に進出することを目論み、前もって英語を習得していたくらいだ。そのイギリスをすっとばしてのアメリカ。どうだろう?少し考えてみよう。実際のモーツァルトとアメリカの「マッチング度」を。
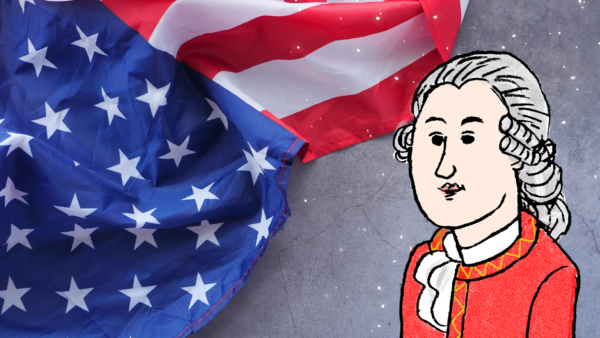
歴史的なエピソードとしての接点は限りなくゼロに等しい。敢えて挙げれば、3大オペラ(「フィガロの結婚」「ドン・ジョヴァンニ」「コジ・ファン・トゥッテ」)の台本作家ロレンツォ・ダ・ポンテが、モーツァルトの死後アメリカに渡り、ニューヨーカーとして没したことくらいか。そのこと自体は、直接モーツァルトとは何の関係もない。しかしモーツァルトとアメリカには、かなり地続きの部分があると思っている。なぜなら、実際のモーツァルトと「アマデウス」のキャラクターにまるで接点がないならば、そもそも「アマデウス」という作品すら生まれなかったと思うからだ。
そこで今回は3つのキーワードでまとめてみたい。「フリーメーソンの精神(理想の社会)」「自由なビジネス観(経済)」「スピリチュアルな感性(宗教)」だ。この3つは密接に絡み合い、モーツァルトの人間(とアメリカとの共通点)を形成している。
- フリーメーソンの精神(理想の社会)
モーツァルトは幼い頃から、各地の演奏旅行先で出会う聖職者があまりにも世俗的なことに幻滅していた。そもそも故郷のザルツブルクという都市自体が、聖職者と君主がイコールで結ばれた「世俗的宗教都市」という、何とも矛盾するような場所で育った。そんなモーツァルトが心の拠り所としたのはなにか。まずは「自分の才能」だろう。そしてその才能を活かすには「身分によらず対等でいられる場」が必要だと考えた。身分制度の強い社会では、通るものも通らなくなる苛立ちを、彼は常に抱えていた。そこで彼が惹かれたものは、フリーメーソンの集会所(ロッジ)である。
モーツァルトは啓蒙主義時代に生きた人物だ。モーツァルトはカトリック信者だったが、フリーメーソンに入会し、熱心に活動していた。そのフリーメーソンが理想とする会員とは「象徴に満ちた結社の儀礼を理解できる、宗教的素養のある人物」であること。しかし各人がどの宗教を信じているかは、まったく自由だったのだ。フリーメーソンのロッジには、聖書やコーランをはじめ、あらゆる宗教の経典が優劣なく「並列」に置かれていた。フリーランスのモーツァルトにとって、身分や信条によらずその人個人として対等な付き合いができるコミュニティーは、理想の社会モデルに見えたはずだ。そこでは最先端の情報と人脈が得られる。
そしてアメリカという国も、カトリックに反旗を翻したピューリタンによって開拓され、フリーメーソンだったジョージ・ワシントンやトマス・ジェファーソンらによって建国の基礎がなされた国である。
- 自由なビジネス観(経済)
モーツァルトの書簡を何度も読むと、いかに彼が伝統やコネよりも、自分で磨いたスキルや才能で自由に稼いでやろう(稼ぐべきだ)と考えていたかがわかる。中央ヨーロッパの旧態依然とした宮廷で「田舎出身の若者が都市部に出て成功し、普通の恋愛結婚をして幸せに暮らしたい」そんなアメリカンドリームである一発逆転・一攫千金を、保守的な神聖ローマ帝国の首都ウィーンで、たったひとりで組織を捨てて、たとえ家族から「お前はバカか」と見放されようとも大真面目に信じて生きようとした、最初の音楽家なのである。
彼は同じ演奏会をやるにしても、宮廷に官吏として雇われている場合と、個人事業主としての企画でやる場合とでは、収入がケタ違いに変わるということを知っていた。音楽家は貴族か宮廷に雇われ固定給をもらって当然という時代に、レッスンや興行収入だけでやっていくことに(図らずとも)なってしまった彼が、自分の音楽に「クライアントのニーズ」や「刺さるターゲット層」など「市場原理」を意識しなかったはずがないのだ。それはまるで「アマデウス」を、舞台版のままやったのでは収入に繋がらないと踏んだミロス・フォアマン監督と同じ発想である。
ビジネスと音楽――この2つを、モーツァルトは切り離してはいなかった。それどころか、音楽は高尚だがビジネスは俗っぽい、などという考えすらもなかった(できなかった)のではないだろうか。音楽は、本来的には「演奏・上演されてこそナンボの世界」なのだから。ましてや、モーツァルトが最もやりたかったジャンルはオペラである。当時の「エンタメ」なのである。特に彼は、楽譜だけを出版して満足とは思わなかった。
ちなみにモーツァルトは21歳の年、なかなか決まらない就職活動中のマンハイムで、あるアイディアを父レオポルドに打ち明け、その現実離れした思いつきに大目玉をくらっている。それは「毎月一定の額を仲間に寄付してもらい、自分はそれで生活・活動する」というもの。つまりフォロワーを募った「オンラインサロン」的な?この発想に、モーツァルト研究家のアルフレート・アインシュタインは、父レオポルドと同じ側にまわって、著書の中でこんなコメントを浴びせている。「マンハイムでは、モーツァルトはまた別のユートピアをでっちあげた」。でっちあげ・・・ひどい言われようであるが、こういう「推し活」みたいなエグい稼ぎ方は、現代では普通に行われていることだ。
かつて「新大陸をユートピアにしよう!」そう思ってヨーロッパからアメリカに渡った人々も、きっとモーツァルトのようなメンタルを持った者だったのではないか。彼らはヨーロッパの社会では、何となく生きづらい、ちょっと浮いてしまう、そんな人たちだったのかもしれない。

- スピリチュアルな感性(宗教)
アメリカ政府は早い頃から、個人の信じるものへの寛容さを示してきた。そのため、キリスト教系新宗教や科学ベースの新宗教など、あまたの新宗教が乱立してきた歴史がある。60年代頃からは、特定の教団には属さないが、信仰のある生活に親和性が高い人たち、本で読んだ独自のニューエイジ思想やスピリチュアル思想(最近ではSBNR“Spiritual But Not Religious”というらしい)を個人的に信じ、生活態度に活かしたり生きる指針としている人も多い。
アルフレート・アインシュタインは、モーツァルトの信仰態度について「幼児のような敬虔さ」だと表現している。しかしそれは、自分の中に湧き出た直感を素直に受け止め、全面的に信じて生きようとする無邪気さともとれる。モーツァルトは、故郷ザルツブルクを出てウィーンに移り住むべき理由を「運命が導くのを感じる」「僕はそうしなければいけない気がする」と、何かの呼び声に応えるような言い回しで父に訴えているが、たとえそれが「ザルツブルクから出たさゆえの自己承認的な言い訳」だったとしても、この声に全力で応えようと猛烈に動き始め、結果的には(喧嘩別れという形にはなったが)ウィーン定住にこぎつけているのだ。彼は不思議な導きに従うことで、自分の運命と未来を切り開いたのだ。
アメリカのスピリチュアルやニューエイジ界隈では、この手の声や直感を「高次の存在」「ハイヤーセルフ」「サムシンググレート」「宇宙」(何なら「フォース」でもいい)などと呼ぶが、モーツァルトが従った声も含め、これらスピリチュアルな直感には共通点がある。それは決して自分にとって「怖い声」ではないということだ。むしろこうした直感こそが自分の人生を導き、真実を見せてくれて、豊かにしてくれると彼ら(モーツァルトも含めて)は信じている。アメリカほど、大いなるもの導かれながら自分の信じた道を行くのだと、高らかに称揚している国はない。たとえそれが、大人たち(例えばアインシュタインやレオポルドのような)からみれば「バカバカしいファンタジー」に思えたとしてもだ。ここは「子供」のような無垢さで「声」に応えなくてはいけない。なぜならこれこそ、自分の強みや才能を活かせる世界に連れて行ってくれる道しるべとなるからだ。
信じるほどに疑わしくなる外の世界
以上、おおまかに3つに分類して両者の類似点を挙げてみた。では最後に、これらがもたらす「負」の部分、つまり彼らの「似ているけど残念なところ」もあげておきたい。『ファンタジーランド 狂気と幻想のアメリカ500年史(上・下)』の著者カート・アンダーセンは、このように言っている。「強い信仰心は、陰謀論を生む」と。60年代のアポロ11号の月面着陸やNASAによるUFO目撃説に始まり、現在ではトランプ大領領のフェイクニュースやQアノンまで。アメリカ人が容易に飛びついてしまう「陰謀論」は、信じるという「光」から生まれた「闇」である。
モーツァルトも(父レオポルドも)音楽界の「陰謀」には敏感だった。父子は、誰かが自分を妨害していると信じていた。自分の正義が通らなかったとき、人はあらゆるところから持ってきた憶測を結びつけて「これは陰謀ではないか」「これが悪の元凶ではないか」と疑い、その疑い自体を強く信じ始める。自分の正義を信じることとそれ以外を疑うことは表裏一体でもあり、諸刃の剣なのだ。モーツァルトの「信じやすさ」。確かにそれが彼の人生を駆り立ててきた。一方で、まわりとの軋轢を生んだことは確かだ。
似ているというより「デジャヴ」
さて「モーツァルトとアメリカって、何か似てない?」という突飛な問いで始まった共通点探し。実際のモーツァルトとのマッチングの感触も、案外よいのではないかと思うが、いかがだろうか。
そもそもこの「モーツァルトとアメリカ」というテーマ。いつから考え始めたのかというと、毎日のように家で映画を観まくっていた学生時代の頃ではない。それは数年前、モーツァルトの名言を集めたブログを始めようと改めて書簡を読み込んでいた頃に感じたことだ。ここまで書き進めてきた今、この感情は「似ている」というよりもちょっとした「デジャヴ(既視感)」なんじゃないだろうかと気づいた。「モーツァルトの言ってることって、何かどこかで・・・」そう、それはかつて「映画を観てずっと慣れ親しんできたアメリカっぽさ」だったのだ。
80年代にピークに達した、アメリカの無邪気なヒーロー映画(自分にとってそれは「トップガン」ではなく「アマデウス」だったのだが)を観て育った自分。その自分の歩いてきた道を、200年以上も前のモーツァルトの書簡を読んで既視感を憶えるという不思議さ。だからこそ私は「現代に通じるモーツァルトの名(迷)言ブログ」を80記事以上も書き抜いてこれたのかもしれない。そして12歳だった当時の自分がなぜモーツァルトにあれほどハマったのか、その潜在的理由も。「アメリカはそれほど好きではないけど・・・」などと冒頭で述べたが見当違いだった。私こそ「隠れアメリカ大好き人間」だった。「モーツァルトのようになりたい人」の一人だったのだ。
それからのアメリカ
では、アメリカ映画とモーツァルト、それぞれの「これから」を考え、このエッセイを閉じることにしたい。典型的なヒーロー像が次々に生まれた80年代アメリカ映画。しかし90年代になると、ヒーローはそこまで能天気なキャラではいられなくなる。例えば「バットマン」の変遷だ。1989年、マイケル・キートンとジャック・ニコルソンの「バットマン」が公開された。この作品は「正義の味方」VS「悪者ジョーカー」という、従来の「善vs悪」という構造で描かれているものの、それにしても、あまりに強すぎる光に耐えかねたかのように、夜(闇)を感じさせるバットマンの世界観が登場した。まさに80年代の終わりを告げる「予兆」を感じさせてくれる。
2000年代に入ると、さらに複雑化したものになる。同じバットマンを主人公にもってきてはいるが、そこに葛藤やアイロニーが入り込む。ダークナイト3部作「バットマン ビギンズ」(2005)、「ダークナイト」(2008)、「ダークナイト ライジング」(2012)のバットマンのキャラクターや存在意義は、すでに別物である。ゴッサムシティにおける「バットマン」とは、社会を照らす「光」ではなく「ダークナイト(影の騎士=守護者)」である。理想社会(タテマエ)としての正義は、現実的な混沌にかき回され、壊されていく。このダークナイト3部作は、60年代から現代に至るまでのアメリカの姿を象徴しているのだ。
それからのモーツァルト
最後に、我らがモーツァルト。モーツァルトという人間は本当に不思議である。その時代ごとに見せる顔が違うのだ。時代の映し鏡のような多面性がある。古くは19世紀、モーツァルトは無垢でありながらも無知、そして貧困の象徴だった。「報われなかったかわいそうな天才モーツァルト」として、借金依頼の手紙や、妻との「貧乏乗り越えエピソード」がもてはやされた。そして20世紀後半、舞台「アマデウス」で彼の「実は自己中心的で我儘な一面」として、映画「アマデウス」で「神に愛されたが、ロックスターのように散った天才」として描かれた。天真爛漫、おちゃらけキャラ、少年のような純粋無垢さ。それから今に至るまでのモーツァルトを描いた作品のキャラクターはその派生・アレンジといえる。
しかし書簡の中には、まだまだ彼の「別の面」が隠されているように思う。神に愛されし者――そういった「天才性」だけでは片づけられない部分、意外に地道な「努力家」だったり、自分が知られていない土地に行くとソワソワする人見知りの、実は「陰キャ」だったり。知られていない顔がたくさんある。そしてそれがとても「新鮮」なのだ。自分はそんなモーツァルトの知られざる多面性を掘り起こすことで、次なるモーツァルト像を紹介していきたいと思っているところだ。
The End
参考文献・映像
世界サブカルチャー史 欲望の系譜:(7)アメリカ 葛藤の80s. NHK Eテレ, 2022年11月9日.(テレビ番組)
ピーター・シェーファー「アマデウス」(江守徹訳)、劇書房、1984年
Peter Shaffer, Amadeus: A Play by Peter Shaffer, New York City, HarperCollins Publishers, 2001
カート・アンダーセン『ファンタジーランド 狂気と幻想のアメリカ500年史(上・下)』(山田美明、山田文訳)、東洋経済新報社、2019年
J・C・ブラウァー『アメリカ建国の精神 宗教と文化風土』(野村文子訳)、玉川大学出版部、2002年
アルフレート・アインシュタイン『モーツァルト その人間と作品』(浅井真男訳)、白水社、1997年
ユルゲン・ハーバーマス/ヨーゼフ・ラッツィンガー『ポスト世俗化時代の哲学と宗教』( フロリアン・シュラー編 三島憲一訳)岩波書店、2007年
湯浅慎一『フリーメーソンリー その思想・人物・歴史』中公新書、1990年
<著者紹介>
越水 玲衣(Rei Koshimizu)
 音楽コラムニスト・エッセイスト
音楽コラムニスト・エッセイスト
16歳で県の高校生小説賞、集英社『ロードショー』
※「投げ銭」するための詳しい手順はこちらからご確認いただけます
この記事はこちらの企業のサポートによってお届けしています


