ゴジラvs札響~伊福部昭の世界~
 2019年の10連休となったゴールデンウィークの最終日、5月6日に札幌文化芸術劇場hitaruで”ゴジラvs札響~伊福部昭の世界~”が開催された。2016年にシン・ゴジラがリバイバル大ヒットを飛ばし、その余勢を刈って人気シリーズとなったこのイベントは、1954年に上映された初代ゴジラの映画本編をスクリーンに映しつつ、伊福部が魂を込めて作曲した音楽をオーケストラが演奏するという画期的なライブ・シネマである。指揮は伊福部の東京音大教員時代の弟子の和田薫。また、前半のトークショーと本編の「栄光丸船員の休息」のハーモニカとギター演奏には、いわゆるミレニアム・ゴジラ(1999年シリーズ第23作「ゴジラ2000ミレニアム」から2004年第28作「ゴジラFinal Wars」までの6作)のうち3作に出演した佐野史郎が参加した。
2019年の10連休となったゴールデンウィークの最終日、5月6日に札幌文化芸術劇場hitaruで”ゴジラvs札響~伊福部昭の世界~”が開催された。2016年にシン・ゴジラがリバイバル大ヒットを飛ばし、その余勢を刈って人気シリーズとなったこのイベントは、1954年に上映された初代ゴジラの映画本編をスクリーンに映しつつ、伊福部が魂を込めて作曲した音楽をオーケストラが演奏するという画期的なライブ・シネマである。指揮は伊福部の東京音大教員時代の弟子の和田薫。また、前半のトークショーと本編の「栄光丸船員の休息」のハーモニカとギター演奏には、いわゆるミレニアム・ゴジラ(1999年シリーズ第23作「ゴジラ2000ミレニアム」から2004年第28作「ゴジラFinal Wars」までの6作)のうち3作に出演した佐野史郎が参加した。
このシリーズには会場別の限定発売のフィギアの物販があり、それを目当てに全国を回っているファン、また、2016年のシン・ゴジラしか観ていない新しいファン、様々なファンで溢れており、会場には普段の札響のコンサートとはまったく違う祝祭的な雰囲気があった。なお、映画本編のセリフと効果音はスピーカーで流されたため、オーケストラがマスクされないようにオケにもPAが使用された。だが、これでも、効果音が入るとオケがほとんど聴こえない状態が続いてしまった。この点については会場から少々落胆の声も聞かれた。このイベントを熱烈なゴジラファンに向けるのであれば、1954年の映画の中から、伊福部の音楽が使用されたシーンの画像か映像のみを映写し、オーケストラを生音で演奏するという手もあっただろう。もちろん、映画本編の音声入りの上映は、あまり本編に精通していないファンに楽しんでもらうためには必要だった。色んな可能性があるなか、今回は音響面でこのマイナスが出てしまったのは確かだ。このライブ・シネマを「ライブ」として見た場合はやや疑問が勝ってしまった。このような事情から演奏内容について詳述することは難しいので演奏については簡易な紹介にとどめ、後半はこのイベントの意義について掘り下げたい。

TM&ⒸTOHO CO., LTD. (撮影:武田 博治)
とはいえ、映画がはじまり、メインタイトルの「ゴジラ」の演奏が始まったときの札響の金管の威圧感には鳥肌がたったファンも多かったはずだ。続いて映画本編では8小節に省略された「栄光丸船員の休息」が佐野によってギター+ハーモニカの完全な形で演奏された。「大戸島の神楽」は大戸島に古くから伝わる神楽。かつて大戸島では、ゴジラの荒ぶる魂を鎮めるために若い女を生贄に捧げていた。その祭事の音楽がこの神楽にあたる。日本人の生活感情に刻みこまれた祭囃子が懐かしさを伴って響いてくる。そうした日本人のDNAを呼び覚ますような太鼓や笛の使い方がいかにも伊福部らしい。伊福部はピアノ曲「日本組曲」やバレエ音楽「盆踊り」でも同様の音楽を書いている。娯楽のない北海道の片田舎で育った伊福部にとって祭りは数少ない楽しみだった。束の間の愉しみ、そしてすぐに戻ってくる日常、伊福部が見ていたそんな風景が舞台から響く。あくまでも素朴な色調を大切にしたフルート、そして打楽器の素晴らしさがPA越しでもはっきり伝わってきた。続いて調査船出航のフリゲートマーチは快速調。次にこのマーチが出てくるときよりもテンポを速めることで、希望に満ちた勇ましい雰囲気を巧く出した。整然とした札響の管が快調だ。これは映画やすでにCDになっている同シリーズでも同じだ。「水槽の恐怖」ではヴァイオリンのトーン・クラスターが身を引きちぎるような響きを発する。1950年代当時の最先端の現代奏法を伊福部が映画に取り入れた成果なのだが、これがオーケストラの音だと舞台を見てはじめて気づいたファンも多かったことだろう。ステージからは、視覚ではっきりと確認できるようにという配慮も感じられた。札響の弦が少々きれいに弾きすぎた感はあったがこれはこのオケの個性だろう。破壊神のごとき凶暴な音楽に続く「帝都の惨状」から、そこから立ちあがろうとする「平和への祈り」には心を打たれた。伊福部は、映画の制作に際し、この作品がゲテモノ怪獣映画と見られることを何よりも警戒した。この「帝都の惨状」以降の伊福部の音楽は、破壊の恐怖と絶望から徐々に立ち上がってゆく人間側の叡智を歌い上げるように展開してゆく。こうした伊福部の矜持があったからこそ、この映画にはある種の宗教色が加わった。ゴジラが日本人にとって神の領域を開いたのはこの音楽の力に拠るところが大きい。シン・ゴジラしか観ていない観客には、東日本大震災の記憶が重なるシン・ゴジラが、太平洋戦争と第五福竜丸事件が重ねられた1954初代ゴジラへの原点回帰であったことがはっきり伝わっただろう。「平和への祈り」では札幌の山の手高校合唱部が参加した。女声23人。ただ、せっかく原作に近い世代の女声合唱だったが、マイクを通した地声が響いてしまい、原作の、あの、世界の悲しみが匿名のまま大地から湧きあがってきて世界を覆い尽くすような雰囲気には遠かった。舞台にこれ以上の人数が乗らないなどの事情があったのかもしれないが、人数を増やしPAを使わずに舞台後方から湧き上がるように歌ってほしかった。

TM&ⒸTOHO CO., LTD. (撮影:武田 博治)
とはいえ、札響と山の手高校合唱部、そして指揮の和田薫の真摯な演奏は、伊福部と映画製作者である田中友幸、本多猪四郎らのメッセージを多少なりとも伝えたことだろう。帝都の惨状から立ち上がるこの映画は、99%が破壊し尽くされても、なおそこに希望を見出す人間の強さを描いている。あるいは、99%が破壊し尽くされない限り、本気では考えない人間の怠惰も同時に描かれている。シン・ゴジラには終盤に、竹野内豊扮する内閣総理大臣補佐官による「スクラップ&ビルドでこの国はのし上がってきた、だから今度もやれる」という復興を期す言葉がある。しかも、この直前には「せっかく」すべて壊れたんだからというセリフがある。この、ゴジラという映画を象徴する「スクラップ&ビルド」という言葉には二重の意味が響いているのだ。一つは、先に述べた形骸化した悪しき慣習を壊すことで初めて新しいものが創れるという意味。もう一つには、高度成長期以降、サブカルチャーの分野でしか正面から描くことが難しくなっている、人間の本質的な二面性がある。それは、「巨大な力への恐怖」が同時に「陶酔」でもあり「破壊の快楽」でもあるという点。シン・ゴジラの「スクラップ&ビルド」という言葉にはこの二つの要素が響いているのだ。

TM&ⒸTOHO CO., LTD. (撮影:武田 博治)
このゴジラvs札響という催しは実のところ、「サブカルチャー」でしか描けなくなっていた人間の内奥の暴力性や破壊願望を、文化芸術劇場を名乗るこの劇場で「サブ」を落とし「カルチャー」として問うという可能性を持っていた。1954ゴジラは太平洋戦争で教科書を黒塗りするくらい世界観が転覆されたのにまた数年で浮ついた空気が支配し始めたことへの警鐘がある。こんなウソ臭いものは壊れてしまえという願望が投影されている。他方のシン・ゴジラに重ねられている東日本大震災は、日本を大きく揺るがしはしたものの、本質的に日本を変えることはなかった。誤解を恐れずに言えば、シン・ゴジラという作品を衝き動かしているのは、もしあの災害が東京を直撃していたら、私たちは「ちゃんと」スクラップ&ビルドできたのではないかという想像力である。これは「世界を」変えるのではなく「世界の見方を」変える思考実験だ。だから、現実に東京が滅んだほうがいいというわけではもちろんない。あくまでもフィクションのなかで思考実験を繰り広げることで現状の問題点を炙りだすことに意味がある。「世界の見方」に留まっていることができず「世界」を変えようと現実に染みだしてしまったのが他ならないオウム真理教である(その意味でオウム真理教は本質的にサブカル的である)。
伊福部の音楽はたしかにこうした想像力が動きはじめるための力を持っている。しかし、このゴジラvs札響は、伊福部の音楽が持つこの力を十全に発揮させるところまではいかなかった。内面の心理の変容を描きだすために伊福部が細心の配慮で配置した重要なモチーフが何度も埋もれたままになった。終演後に母親に連れられた少年が母親から「オーケストラすごかったね」と声をかけられ「スピーカーうるさくて聴こえなかった」と答えていた。だが、SNS等でいわゆる大人が発信した投稿は「感動した」、「よかった」という内容ばかりだった。こうした少年の虚心な感受性を大切にすべきだ。映画などの「サブ」カルチャーでは、受け取り手が何十回も観ないと理解できないほどの伏線の網の目が張り巡らされ、制作者は細部まで完全に納得するまで命がけで詰める。観客も少しでも緩いと容赦なく批判する。しかし、「サブ」がとれて「カルチャー」という土台に乗せられたとたん、少々詰めが甘くても誰も非難しないということがしばしば起こる。今回もゴジラというサブカルチャーから文化芸術劇場というカルチャーへ舞台が移された途端それが起こった。なぜなのか。最後にこれについて少々考えてみたい。
つい最近Kitaraが制作した初心者向けの印刷物にこんな文言があった。
「クラシック音楽[は]音楽の老舗のブランド品なのです。だから私たち誰もが楽しめるのです。」
何度か読んでみてほしい。「老舗のブランド品」からなぜ「誰でも楽しめる」が帰結するのか。仮に、バッハのマタイ受難曲やブルックナーの交響曲を初心者が予習なしでコンサートホールで聴いたことを想像してほしい。数時間ただ座り続ける苦痛に耐えることになる。それで「ブランド品だから誰でも楽しめる」とでも言われようものなら、自分の理解力を呪い二度とコンサートには来なくなるのではないか。この「~だから~である」という推論が成立するためにはある前提を認めなくてはならない。それは、主催者側の「自分たちは立派なコンテンツを提供している。だから、もし楽しめなかったらそれは催しの内容のせいではなく観客の能力のせいだ」という思惑だ。この前提なしに「老舗のブランド品」から「誰でも楽しめる」は決して出てこない。こうした言葉をまき散らせばまき散らすほど、自分の正直な感受性をそのまま言葉にすることが憚られるようになってしまう。少年は今回のライブ・シネマに接し素直に「聴こえなかった」と感じているが、ものの分かるはずの大人のほうは「つまらなかった」と言えば自分の芸術理解力が疑われるのでそれを警戒して「よかった」と発言するようになってしまうのだ。それを繰り返すうちに感受性そのものが本当に麻痺してしまう。子供でも大人でも、誰であっても、もっと自分の感受性を大切にすることができるようでなくてはならない。つまらなかったら「つまらない」と言い、どこがつまらなかったのかも正直に発言できるような土壌を作らなくてはいけない。もし本当に自分の理解力不足で楽しめなかったとしても、数年後に同じ作品に接して魅力に気づいたら「あのときと自分の感じ方がどう変わったのか」が自分で分かるようになる。そうしてより深く文化芸術は血肉になる。
そもそも、自分の想像力を超えた隔絶されたものとの出会いなどそうそう起こることではない。だが、だからこそ自己が絶対的に変化させられてしまう体験となり得るのではないか。この印刷物は一見初心者向けを謳ってはいる。しかしその実、初心者を、それどころか批判や意見を排除し自らを権威づけようとするグロテスクな構造を突きつけてしまっている。いやそんな意図はないと言うかもしれない。だが世界の外部を抹消しようとする意図とは往々にして無自覚なものであり、ひとはそこに大義をつけ加えたがるものだ。自由に感じ、自由に考え、自由に言葉を紡ぐ、それを肯定するのでなくして何のための文化芸術なのか。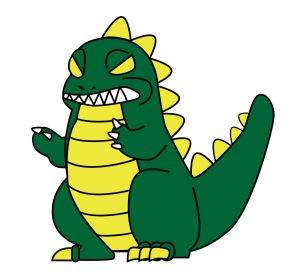 現実社会においてこの自由を保持することが難しいからこそ、文化芸術のなかだけでもこの自由な想像力を大切にすべきではないのか。悪しき権威主義がどれほど文化芸術受容の妨げになっていることか。”ゴジラvs札響~伊福部昭の世界~”は、こうした自由な感受性を押しつぶすブランド志向こそがスクラップ&ビルドされねばならないという強烈なメッセージを札幌に残した。99%諦めるしかないような現状でも、1%の希望へ向けて言葉を紡ぎだすべきだ。伊福部の畏怖すべき音楽はそれが「愛」だと訴えている。
現実社会においてこの自由を保持することが難しいからこそ、文化芸術のなかだけでもこの自由な想像力を大切にすべきではないのか。悪しき権威主義がどれほど文化芸術受容の妨げになっていることか。”ゴジラvs札響~伊福部昭の世界~”は、こうした自由な感受性を押しつぶすブランド志向こそがスクラップ&ビルドされねばならないという強烈なメッセージを札幌に残した。99%諦めるしかないような現状でも、1%の希望へ向けて言葉を紡ぎだすべきだ。伊福部の畏怖すべき音楽はそれが「愛」だと訴えている。

