【リレーエッセイ<STJ接触篇>➃】切断と跳躍 ―本当の<つながり>を求めて(執筆:多田 圭介)

(1)<つながり>の空洞化
コロナ禍(下)での文化活動をめぐって始まったこのリレー・エッセイ。第3走者までバトンが渡ったところで、一度問題設定を巻き戻してみたくなった。というのも、自分で主催しておいてこう言うのもなんだが、筆者は、このコロナ騒動が文化的想像力に与える影響は微弱なものにとどまると考えている。あらゆる面で過大評価されているこのコロナ騒動をきっかけに、もし文化的想像力が更新されるとしたら、それはどのような点なのか。問題はどこに設定されるべきなのか。再考したくなった。
まず、このコロナ騒動が経済や政治に与える影響が甚大であることは論をまたないが、こと文化的想像力についてはどうか。グローバリズムの拡大とその反動としての終焉やNetflixの隆盛、コミュニケーション形式の変化(非対面への)などは、今回のパンデミック以前から語られていたことばかりだ。つまりもともと存在していた要素がコロナをきっかけにさらに押し進められたにすぎない。思えば、20世紀のスペインかぜも文化史的にはほぼ何も残していない。第一次大戦とは比較するまでもない。
しかし、コロナをめぐる文化的言説の大半が、すでにあった言説の追確認にすぎないとしても、筆者にはそこに見過ごすことができない<言葉の空洞化>の加速があるように感じられる。それは、<つながり>の美化、空洞化である。
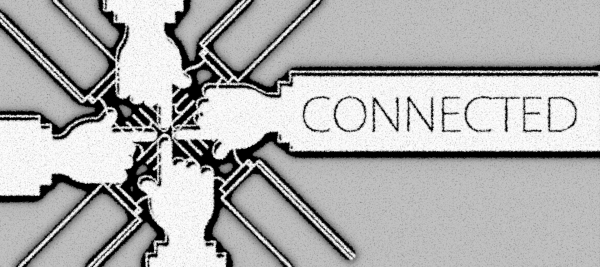 もちろん、これにしても、2016年のトランプ現象以来、(いわゆる)リベラル派の言論人は、つながりや融和のイメージをイージーに語るようになっていた。メディアや出版業界も喜んで追従していた。だが、その空洞化は、コロナをきっかけに爆発的に拡大した。人は被害者の立場から留保なく<共に生きよう>というメッセージを発することができるようになった。ためらうことなくカタルシスのある言葉に寄りかかるようになった。誰もそれを批判できない空気が蔓延した。このパンデミックは、人々の往き来が国境を越えて自由になり、そのことによって引き起こされたものであるにもかかわらず。いや、なにより、このパンデミックは、情報技術の発展によって私たちが<つながりすぎた>ことによって引き起こされたInfo-demicに下支えされた現象であったというのに。私たちはどうつながるべきなのか。いや、そもそも<つながり>はよいことなのか。本当の意味で文化が生まれるような<つながり>とはどのような想像力なのか。伸びすぎた釣り糸をもう一度巻き戻したい。
もちろん、これにしても、2016年のトランプ現象以来、(いわゆる)リベラル派の言論人は、つながりや融和のイメージをイージーに語るようになっていた。メディアや出版業界も喜んで追従していた。だが、その空洞化は、コロナをきっかけに爆発的に拡大した。人は被害者の立場から留保なく<共に生きよう>というメッセージを発することができるようになった。ためらうことなくカタルシスのある言葉に寄りかかるようになった。誰もそれを批判できない空気が蔓延した。このパンデミックは、人々の往き来が国境を越えて自由になり、そのことによって引き起こされたものであるにもかかわらず。いや、なにより、このパンデミックは、情報技術の発展によって私たちが<つながりすぎた>ことによって引き起こされたInfo-demicに下支えされた現象であったというのに。私たちはどうつながるべきなのか。いや、そもそも<つながり>はよいことなのか。本当の意味で文化が生まれるような<つながり>とはどのような想像力なのか。伸びすぎた釣り糸をもう一度巻き戻したい。
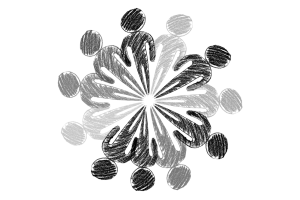
(2)「感染」と「梗塞」
 ドイツの哲学者(韓国出身)のハン・ビョンチョルは、“Müdigkeitsgesellschaft“(『疲弊社会』とでも訳せようか)という近著のなかで、病気のタイプを「感染」(infection)的なものと「梗塞」(infarction)的なものに分けて分析している。そのなかで、精神疾患に注目が集まる現代社会では後者が優勢だと述べている。疫病的な意味だけではなく、近代文学以降、文化的な想像力が捉えてきた病理が、主に梗塞的であったことはここで注目に値する。そして、社会の流動性が上昇するポストモダン情況において、この傾向には拍車がかけられた。日本の文化現象では、90年代に社会現象化した「新世紀エヴァンゲリオン」にその頂点を見出すことができよう。かの作品でリアルに描かれたのは、生きる意味を誰も保証してくれなくなった時代の<引きこもり症候群>である。そこに「梗塞」的な病理の雛型がある。そして、この状況は臨界点を迎えると180度回頭する。承認や生きる意味を自前で用意しなければならない自由競争社会が、人々の「心」に「辛いもの」、「耐え難いもの」として映し出された瞬間、人は<自由だが冷たい社会>よりも<暖かいが不自由な社会>のほうをより魅力的に感じてしまうからだ。こうして、病理は「梗塞」から「感染」へと、より強く表現するなら「自閉」から「つながり」へと転回する。そこへ、人々の承認の欲求をダイレクトに叶え過ぎるSNSの登場が重なりInfo-demicは引き起こされた。私たちは、1人1アカウントを持たされた状態で、歴史上、初の世界規模の災厄を迎えた。<つながり>と<承認>に飢えた餓鬼にこの燃料が投下されたとき、私たちは抵抗する術を持たなかったのだ。
ドイツの哲学者(韓国出身)のハン・ビョンチョルは、“Müdigkeitsgesellschaft“(『疲弊社会』とでも訳せようか)という近著のなかで、病気のタイプを「感染」(infection)的なものと「梗塞」(infarction)的なものに分けて分析している。そのなかで、精神疾患に注目が集まる現代社会では後者が優勢だと述べている。疫病的な意味だけではなく、近代文学以降、文化的な想像力が捉えてきた病理が、主に梗塞的であったことはここで注目に値する。そして、社会の流動性が上昇するポストモダン情況において、この傾向には拍車がかけられた。日本の文化現象では、90年代に社会現象化した「新世紀エヴァンゲリオン」にその頂点を見出すことができよう。かの作品でリアルに描かれたのは、生きる意味を誰も保証してくれなくなった時代の<引きこもり症候群>である。そこに「梗塞」的な病理の雛型がある。そして、この状況は臨界点を迎えると180度回頭する。承認や生きる意味を自前で用意しなければならない自由競争社会が、人々の「心」に「辛いもの」、「耐え難いもの」として映し出された瞬間、人は<自由だが冷たい社会>よりも<暖かいが不自由な社会>のほうをより魅力的に感じてしまうからだ。こうして、病理は「梗塞」から「感染」へと、より強く表現するなら「自閉」から「つながり」へと転回する。そこへ、人々の承認の欲求をダイレクトに叶え過ぎるSNSの登場が重なりInfo-demicは引き起こされた。私たちは、1人1アカウントを持たされた状態で、歴史上、初の世界規模の災厄を迎えた。<つながり>と<承認>に飢えた餓鬼にこの燃料が投下されたとき、私たちは抵抗する術を持たなかったのだ。

さて、「感染」も広義での<つながり>を意味する。<つながり>がただちに称賛されることでないことはここからも分かるだろう。同時に、コロナ禍で語られた人々の「分断」という言葉にもある種の価値評価が含まれている。よりニュートラルには「分断」は「切断」、「つながり」は「接続」と表現できよう。「切断」は悪しきことなのか。接続は無条件に望まれるべきことなのか。
(3)切断と跳躍
「つながり」(=接続)と「承認」を何より欲する人にSNSを与えるとどう使うか。人は、シェアされやすい話題、リツイートされやすい話題、コメントがつきやすい話題だけを発信するようになる。つまり、皆が関心を持っている話題だけを発信するようになる。この発想はマーケティングと親和的である。マーケティングは「接続」を換金するシステムだからだ。発信者は多かれ少なかれ「いいね」が欲しいしフォロワーを増やしたいと思っている。そこでは、皆が関心を持っている問題以外を話題にするインセンティブは必然的に低くなるのだ。 こうして人々の関心は、感染症であったり、マスメディアがgoを出した「やらかした人」に集中することになる。こうなると、もうポジティブな議論はできない。言葉は「このメッセージに賛同するか否か」、「この人を叩きたいか叩きたくないか」のように、ゼロかイチに平板化されてゆく。世界がA or Bという二者択一に見えてくる。接続することが目的になったコミュニケーションでは、言葉は本質的なレベルでデジタルな信号に接近せざるを得ないのだ。筆者はSNS上ではある程度以上の規模で本質的な議論が行われることは不可能だと考えている。その理由はこれである。
こうして人々の関心は、感染症であったり、マスメディアがgoを出した「やらかした人」に集中することになる。こうなると、もうポジティブな議論はできない。言葉は「このメッセージに賛同するか否か」、「この人を叩きたいか叩きたくないか」のように、ゼロかイチに平板化されてゆく。世界がA or Bという二者択一に見えてくる。接続することが目的になったコミュニケーションでは、言葉は本質的なレベルでデジタルな信号に接近せざるを得ないのだ。筆者はSNS上ではある程度以上の規模で本質的な議論が行われることは不可能だと考えている。その理由はこれである。

この事態について経済学者のダニエル・カーネマンは、恐怖や不安という「早い思考」は「遅い思考」である理性を一瞬で駆逐すると述べている。いまの問題で言うなら、カーネマンがいう「早い思考」には「共感」も追加できるだろう。皆が関心を持つ話題=共感によってつながろうとすればするほど理性は脇に追いやられ、言葉はデジタルな信号と化すのだ。共感に下支えされたシェアやリツイートという言葉のウイルスは、ときに現実のウイルスよりも早いスピードで社会を蝕んでゆく。そのことを、私たちはこの一年、目の当たりにしてきた。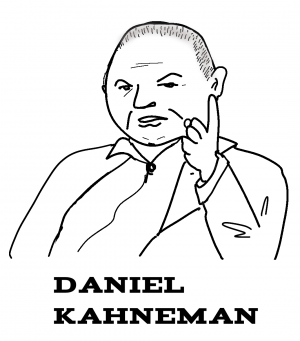
カーネマンがいう「早い思考」が「接続的」であるのに対し、「遅い思考」は本質的に「切断的」である。理性によって熟考された言葉には、「誰が共鳴してくれるか知らないが自分は世界をこう切り取る」という強さがあるからだ。文化を生み出す言葉というものは、こうしたところからしか生まれないのではないか。それは、本質的な意味で「切断的」なところだと言える。
誰かの心に何か変化を起こすような表現。それは、究極的には思い込みや独断でしかない可能性を引き受けて、それを敢えてパブリックな場に問うという営みによって引き起こされよう。そして、もしかしたら、世界のどこかで、誰かが、自分の表現に触れて心に変化が生じているかもしれない。しかも自分はそのことを知りえない。しかし、それでいいんだ、そういう命がけの跳躍が本当の意味での文化が生まれる場所なのではないか。一方では、完全に閉じられていながら、他方では無限に開かれている。まるで、瓶に詰めた手紙を海に流すような、そんな営みである。
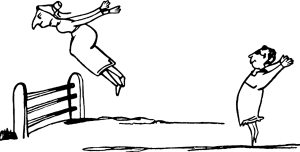
(4)本当の意味で<つながる>ということ
 『1417年、その一冊がすべてを変えた』という書物がある。著者はスティーブン・グリーンブラット。アメリカの新歴史主義の文芸評論家である。ちなみに存命中。同書では、古代ローマ時代、エピクロス派の思想家、ルクレティウスが紹介されている。ルクレティウスは原子論を唱えた思想家だ。原子論とは、世界には原子や分子のような究極的な要素があるという近代以降の物理的な世界観を先取りした学説である。その説を唱えた『物の本質について』は、同時代のローマカトリックの思想に抵触したため発禁となっていた。それが1500年ほどたって、ドイツの修道院の山奥で発見され、それが当時の言語に翻訳されヨーロッパ中に広まった。そして、それでルネサンスが起こった。
『1417年、その一冊がすべてを変えた』という書物がある。著者はスティーブン・グリーンブラット。アメリカの新歴史主義の文芸評論家である。ちなみに存命中。同書では、古代ローマ時代、エピクロス派の思想家、ルクレティウスが紹介されている。ルクレティウスは原子論を唱えた思想家だ。原子論とは、世界には原子や分子のような究極的な要素があるという近代以降の物理的な世界観を先取りした学説である。その説を唱えた『物の本質について』は、同時代のローマカトリックの思想に抵触したため発禁となっていた。それが1500年ほどたって、ドイツの修道院の山奥で発見され、それが当時の言語に翻訳されヨーロッパ中に広まった。そして、それでルネサンスが起こった。
文化が持つ、本当の接続する力、あるべき<人と人のつながり>とはこういうことなのではないか。リアルタイムでシェアされ認められる言葉というのは、多かれ少なかれその時代のトラフィックに合致した結果であろう。今のSNS上の空気とルクレティウスの時代のローマカトリックの権威とは、ある種、同じ機能を持ってしまっている。科学主義が日の目を見るのに1500年の切断を要したことには意味があったはずだ。

もちろん、しっかりマネタイズできるようにマーケティングされた表現のなかに、メタ的にこのようなメッセージを含意させたコンテンツが立派なのは言うまでもない。ただ、その手前で、切断的に世界と繋がる覚悟がなければ、そうした表現も生まれようがない。科学主義が日の目を見るのに1500年の切断を要した。現代の私たちも、考えなくてはならないのではないか。<つながりすぎた世界に、禁書だけの図書館をどう確保するか>を。もちろんテクノロジーは悪ではない。情報も悪ではない。そうではなく、情報をシェアすることで自分を粉飾しようとする根性、世間(世界ではなく)に接続することで安心を得ようとする根性の卑しさが、問題なのだ。

時間的には無限に開かれているが、空間的には途絶した場所。そこへ命がけで跳躍する態度表明。それこそが文化を生む。<つながりすぎた>世界の只中で、知らない誰かにいつかこの言葉が届くことを願いつつ、リレー・エッセイのバトンを第5走者に託す。
多田圭介
※「投げ銭」するための詳しい手順はこちらからご確認いただけます
この記事はこちらの企業のサポートによってお届けしています



