【寄稿】同じ窓から世界を見るということ‐21世紀の同窓会論(執筆:多田圭介)

1:同窓会の現在
高校の同窓会から「同窓生の活躍」という記事の執筆依頼を頂戴しましてこれを書いています。「もっと他に相応しい奴がいるだろうに」と内心ちょっと訝しみつつ、でも実はちょっと嬉しかったりしつつ。簡単に自己紹介しますと、私は哲学・倫理学の研究者をやっております。東京の私立大学を経て北大の大学院で博士号を取得して、今は札幌の藤女子大学で教えています(研究はサボりぎみ)。それから、クラシック音楽や舞台芸術の評論を書いています。新聞や専門誌に寄稿していましたが、マス向けのメディアではあまり本当に書きたいことが書けないので、2018年に独立して「さっぽろ劇場ジャーナル」という批評誌を創刊しました。さらに、朝日新聞やNHKなどが開講している生涯教育機関での市民講座にも力をいれています。あちこちに分散しているように見えるかもしれませんが、これらの仕事に共通するのは、皆が同じ方向を向いているときに「それ、ちょっと違うんじゃないの?」と”いちゃもんをつけること”と言えるかもしれません。まあ、そういうことをするからソクラテスも死刑になったわけですが、この汚れ仕事を大切な自分の役割だと信じて頑張っています。
というわけで、この寄稿でも、せっかくなので同窓会に”いちゃもんをつける”ことにしました。SNSですでに繋がりすぎた現代において、同窓会にはどんな意味があり得るか。ちょっと考えてみませんか。
 高校を卒業してから20数年。これまでに高校や大学の友人と集まる機会は、皆さんも少なくなかったと思います。「お、東京にいるの?ちょっと集まろうか」という具合に。あまり友人のいない私もたまにお呼ばれしました。私は、昔の友人たちと集まるとこんなことを感じていました。
高校を卒業してから20数年。これまでに高校や大学の友人と集まる機会は、皆さんも少なくなかったと思います。「お、東京にいるの?ちょっと集まろうか」という具合に。あまり友人のいない私もたまにお呼ばれしました。私は、昔の友人たちと集まるとこんなことを感じていました。
久しぶりに集まって楽しく話せるかどうかは、当時同じ部活だったかどうか、当時趣味を通じて仲がよかったかどうか、当時どのグループにいたかどうかに、意外と関係がないんです。20数年たって楽しく話せるかどうかの基準はたった一つです。それは、社会に対するリアリティを共有しているかどうか、この一点なんです。社会に対するリアリティとは何でしょうか。例えば、同じマンションの隣のおばさんは、僕にとって空間的には無限に近い存在だけど、心理的には無限に遠い存在です。終身雇用で、家に専業主婦がいて、さらに郊外に戸建てを買っていていつかはクラウンみたいな。そんな戦後中流神話を信じているような人とは無限の隔たりがあるわけです。そんな隣のおばさんより、海外に住んでいるけど同じ問題に関心がある人のほうがよほどリアリティを共有できる。インターネットがあると当然そうなりますよね。こうしたリアリティの乖離って、いつからどのように生じてくるんでしょうか。ちょっと角度を変えてみましょう。
 社会に出て初々しい頃、仕事で世の中に何かを残そうと思っていたやつも、時間が経つにつれてだんだんそう思わなくなっていく。そして、自分の人生にばかり興味がいくようになる。これ、自分でも友人でもいいのですが、実感したことありませんか。あんまり言いたくはないけど、お勤めの人は特にそう。少なからぬ人が、35歳くらいで社会に何を残すかを考えなくなる。そして、自分の人生にどう見栄を張るか、自分の自意識にどう決着をつけるかばかり考えるようになる。自分の社会的・経済的保身とプライドの維持にしか関心がなくなっていく。実際、日頃大学生と接していても、若いマスコミ志望の学生なんかは、9割がた、就職活動している時点でfacebookに「どこどこのテレビ局に内定もらいました」、「どこどこの広告代理店の内定ゲットしました」と書きたいだけの奴が多い。いますぐ全員側溝に流したくなるけれど、そのなかでも1割くらいはものが作りたいと思ってる人もいる。だけど、その1割のうちの9割が35歳までに脱落する。悲しい。
社会に出て初々しい頃、仕事で世の中に何かを残そうと思っていたやつも、時間が経つにつれてだんだんそう思わなくなっていく。そして、自分の人生にばかり興味がいくようになる。これ、自分でも友人でもいいのですが、実感したことありませんか。あんまり言いたくはないけど、お勤めの人は特にそう。少なからぬ人が、35歳くらいで社会に何を残すかを考えなくなる。そして、自分の人生にどう見栄を張るか、自分の自意識にどう決着をつけるかばかり考えるようになる。自分の社会的・経済的保身とプライドの維持にしか関心がなくなっていく。実際、日頃大学生と接していても、若いマスコミ志望の学生なんかは、9割がた、就職活動している時点でfacebookに「どこどこのテレビ局に内定もらいました」、「どこどこの広告代理店の内定ゲットしました」と書きたいだけの奴が多い。いますぐ全員側溝に流したくなるけれど、そのなかでも1割くらいはものが作りたいと思ってる人もいる。だけど、その1割のうちの9割が35歳までに脱落する。悲しい。
 もちろん、自分の人生以上に大切なものなんてないというのは、正しいと言えば正しいし、常識といえば常識。でも、その常識を超えて、自分の人生はせいぜい80数年しかないけれど、作品は永遠かもしれないというところに賭けるから、人ってものを作るんだと思うんです。本を書くのもそう。自分が生きている間は陽の目を見ないかもしれないけれど、本当に大事なことが書いてあれば、自分が死んだ後、いつかどこかで誰かの心を動かすかもしれない。そこに賭けるから人は本を書く。もちろん、具体的な作品じゃなくても仕事の成果でもいい。例えば、学校の先生になってみたら、現場で何十年もただ因習的に続けている実効性ゼロの行事があったとしましょう(学校にはたいがいありますね)。それを改革したら、現場で村八分にあって職場を追われることになるかもしれない。でも、そんな憂き目に遭ったとしても、その因習を断ち切ることに成功したなら、それは社会に作品を残したことになります。疑問に感じながらも、自分が損しないだけのために、ずるずる因習を引きずることに加担する人生よりずっとよいとも言えます。でも、ほとんどがそこから脱落する。僕が感じる、最も大きな社会に対するリアリティの齟齬はこの辺にあります。
もちろん、自分の人生以上に大切なものなんてないというのは、正しいと言えば正しいし、常識といえば常識。でも、その常識を超えて、自分の人生はせいぜい80数年しかないけれど、作品は永遠かもしれないというところに賭けるから、人ってものを作るんだと思うんです。本を書くのもそう。自分が生きている間は陽の目を見ないかもしれないけれど、本当に大事なことが書いてあれば、自分が死んだ後、いつかどこかで誰かの心を動かすかもしれない。そこに賭けるから人は本を書く。もちろん、具体的な作品じゃなくても仕事の成果でもいい。例えば、学校の先生になってみたら、現場で何十年もただ因習的に続けている実効性ゼロの行事があったとしましょう(学校にはたいがいありますね)。それを改革したら、現場で村八分にあって職場を追われることになるかもしれない。でも、そんな憂き目に遭ったとしても、その因習を断ち切ることに成功したなら、それは社会に作品を残したことになります。疑問に感じながらも、自分が損しないだけのために、ずるずる因習を引きずることに加担する人生よりずっとよいとも言えます。でも、ほとんどがそこから脱落する。僕が感じる、最も大きな社会に対するリアリティの齟齬はこの辺にあります。
でも、それって誰かが悪いわけじゃない。お爺ちゃんみたいな言い方になるけれど、人生ってそういうものだとしか言いようがない。なので、ズレたらズレたなりの適切な進入角度でどう人と付き合うかは、人が歳をとっていくなかでとても大事な問題であるのはたしか。というわけで、世界観が完全にズレてしまった人とどう付き合うべきなのか。それを考える場が、現代の同窓会の意味になり得るんじゃないか。なんてことを考えたわけです。決定的に生き方が違ってしまったけれど、それでも大事な人というのは、やはりいる。そういう人と出会い直し、そういう人とどう付き合うかを考える。それが現代の同窓会の意味だと考えられないでしょうか。
2:オリンピックのリアリティ
さて、せっかくの寄稿なので、私たちが今直面している社会的なリアリティを何か取り上げてもう少し掘り下げてみましょう。何にしましょうか。コロナはさすがに嫌なのでオリンピックはどうでしょう。2021年4月現在のオリンピックのリアリティ。皆さんはどこに見出していますか。
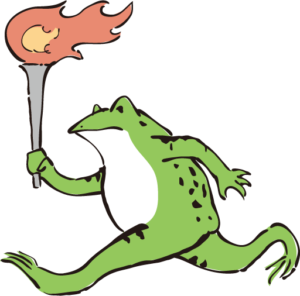 オリンピック以前に、僕、そもそもなんですが、学校の体育が苦痛でした。その理由を遡ってみましょう。80年代は、田舎の小中とかには体育できないやつはイジメられて当然という空気がありました。体育の授業っていうのは、クラスの統治をスムーズにするために最適化されていた。ヒーローを生んで人の輪の中心と外側ができるように。先生もそれを黙認していた。いや、積極的に加担していた。当然、子供たちに身体を動かす楽しさを教えるためのものにはなっていなかった。言葉の最悪な意味で、世間に適応するためのノウハウを詰め込むためのものになっていました。今、オリンピックについて考えるべき最重要課題は、日本の公(ダメ)教育によって奪われてしまったスポーツの魅力を取り戻すこと、こう言えると思います。そもそもなんですが、今のスポーツは改善の余地が多い。今のスポーツは、大半の競技が健康で若い成人男性を基準につくられていて、それ以外は劣った身体だという根深い前提があります。僕が、子供の頃から体育がいまいち好きになれなかったのは、この五体満足男性中心主義が見え隠れするからなんです(ちなみに僕の父親は体育教師でした。びっくりですね)。
オリンピック以前に、僕、そもそもなんですが、学校の体育が苦痛でした。その理由を遡ってみましょう。80年代は、田舎の小中とかには体育できないやつはイジメられて当然という空気がありました。体育の授業っていうのは、クラスの統治をスムーズにするために最適化されていた。ヒーローを生んで人の輪の中心と外側ができるように。先生もそれを黙認していた。いや、積極的に加担していた。当然、子供たちに身体を動かす楽しさを教えるためのものにはなっていなかった。言葉の最悪な意味で、世間に適応するためのノウハウを詰め込むためのものになっていました。今、オリンピックについて考えるべき最重要課題は、日本の公(ダメ)教育によって奪われてしまったスポーツの魅力を取り戻すこと、こう言えると思います。そもそもなんですが、今のスポーツは改善の余地が多い。今のスポーツは、大半の競技が健康で若い成人男性を基準につくられていて、それ以外は劣った身体だという根深い前提があります。僕が、子供の頃から体育がいまいち好きになれなかったのは、この五体満足男性中心主義が見え隠れするからなんです(ちなみに僕の父親は体育教師でした。びっくりですね)。
 でも、人間の身体って実際はもっと多様ですよね。例を挙げて考えてみましょう。南アフリカにオスカー・ピストリウスっていう義足の陸上選手がいます。彼は義足でパラリンピックではなく、オリンピックに出場してメダル一歩手前まで行きました。ここから何が分かるかというと、競技用の板バネの性能が上がっていったら、短距離走や跳躍種目では、義足のほうが有利になるということです。考えてみたら、人間の足なんて速く走るために最適化されていません。なので、競技用の板バネのほうがスピードが出るというのは当然なんです。このとき、義足の選手を、そんなものインチキだとオリンピックから追い出すのは、僕にはどうしてもフェアだと思えない。ちょっと前に抵抗の少ない水着が問題になりましたね。あれは、本当はシューズやウェアだって同じはずです。もっと言ってしまえば、メガネだって広義でのサイボーグ化であるはずです。広義の身体改造。こう考えると、いま私たちが信じているスポーツというものは、何か、ものすごく狭くて暴力的な、人間の身体というものはこうあるべきという思想に基づいたものに見えてきませんか。少なくとも、すごく一面的なカッコよさとか憧れに依拠したものであるということは、どこかで頭に入れておく必要がある。本当は、もっと幅広い身体観に基づいたゲームがあってよいはずです。
でも、人間の身体って実際はもっと多様ですよね。例を挙げて考えてみましょう。南アフリカにオスカー・ピストリウスっていう義足の陸上選手がいます。彼は義足でパラリンピックではなく、オリンピックに出場してメダル一歩手前まで行きました。ここから何が分かるかというと、競技用の板バネの性能が上がっていったら、短距離走や跳躍種目では、義足のほうが有利になるということです。考えてみたら、人間の足なんて速く走るために最適化されていません。なので、競技用の板バネのほうがスピードが出るというのは当然なんです。このとき、義足の選手を、そんなものインチキだとオリンピックから追い出すのは、僕にはどうしてもフェアだと思えない。ちょっと前に抵抗の少ない水着が問題になりましたね。あれは、本当はシューズやウェアだって同じはずです。もっと言ってしまえば、メガネだって広義でのサイボーグ化であるはずです。広義の身体改造。こう考えると、いま私たちが信じているスポーツというものは、何か、ものすごく狭くて暴力的な、人間の身体というものはこうあるべきという思想に基づいたものに見えてきませんか。少なくとも、すごく一面的なカッコよさとか憧れに依拠したものであるということは、どこかで頭に入れておく必要がある。本当は、もっと幅広い身体観に基づいたゲームがあってよいはずです。
 例えば、アメフトはヒントになります。あれは、マッチョな人とか足の速い人とかバラバラの個性が同じチームにいるほうが強いゲームですね。あの延長線上で、もっと多様な身体観を許容するルールの競技があっていいはずなんです。この観点に基づくと、いま私たちが身近に親しんでいるスポーツはほとんどがクソゲーということになる。若くて五体満足で健康な男性がひたすら有利っていうものすごく単純なルールになっていることに気づかされざるをえない。仮に、ゲームセンターで、健康で背が高くて若い成人男性だけが有利なゲームがあったら流行りませんよね。それと同じです。もし、こうした多様な身体観に基づいたスポーツが当たり前の世の中で、学校の体育教育もそうした観点で行われていたなら、僕はもっとスポーツが好きになっていたかもしれません。2021年のオリンピック。これだけ、男女平等とか叫ばれる割に、スポーツが持つこうした根深い問題にリアリティを感じている人がいるようには思えないんです。テレビで議論されることはまずないでしょう。
例えば、アメフトはヒントになります。あれは、マッチョな人とか足の速い人とかバラバラの個性が同じチームにいるほうが強いゲームですね。あの延長線上で、もっと多様な身体観を許容するルールの競技があっていいはずなんです。この観点に基づくと、いま私たちが身近に親しんでいるスポーツはほとんどがクソゲーということになる。若くて五体満足で健康な男性がひたすら有利っていうものすごく単純なルールになっていることに気づかされざるをえない。仮に、ゲームセンターで、健康で背が高くて若い成人男性だけが有利なゲームがあったら流行りませんよね。それと同じです。もし、こうした多様な身体観に基づいたスポーツが当たり前の世の中で、学校の体育教育もそうした観点で行われていたなら、僕はもっとスポーツが好きになっていたかもしれません。2021年のオリンピック。これだけ、男女平等とか叫ばれる割に、スポーツが持つこうした根深い問題にリアリティを感じている人がいるようには思えないんです。テレビで議論されることはまずないでしょう。
 オリンピックのリアリティを考える上で今出たテレビの役割も避けるわけにはいきません。よく言われることですが、日本のマスメディアは、こうした大きなスポーツイベントがあると、ゲームの面白さではなく、物語で共感を集めようとしますね。競技の専門的な解説よりも、選手の苦労話にフォーカスして、日本に感動をありがとう!という。でも、現代社会の生活実感として、同じ国籍だという理由で感動するのはちょっと無理がありませんか。現代では、国家よりも市場のほうが生活に与える影響は明らかに大きくなっています(今はコロナでちょっと違いますが)。こうなると国籍が同じ人より、ライフスタイルが近い海外の人により近さを感じるのは当然でしょう。こんな時代に国民的なスポーツイベントでみんな一つになんてどだい無理な話。ただ、それでも今はグローバル化に対するアレルギー反応で、やっぱ国家が提供する物語が大事だよねっていう反動が起きているのも確か(ネット右翼)。だから、一時的には国威発揚的なオリンピックは復権する可能性がある。日本は高齢社会だからなおさらその可能性はある。一時的には国民的スポーツで一つに!ってのはウケる可能性があるんです。でも、だからこそ、その反動に注意深くならなければいけない。そのリアリティはたんなる反動現象だよ、と。ここで、オリンピックのもう一つのリアリティが浮上してきます。
オリンピックのリアリティを考える上で今出たテレビの役割も避けるわけにはいきません。よく言われることですが、日本のマスメディアは、こうした大きなスポーツイベントがあると、ゲームの面白さではなく、物語で共感を集めようとしますね。競技の専門的な解説よりも、選手の苦労話にフォーカスして、日本に感動をありがとう!という。でも、現代社会の生活実感として、同じ国籍だという理由で感動するのはちょっと無理がありませんか。現代では、国家よりも市場のほうが生活に与える影響は明らかに大きくなっています(今はコロナでちょっと違いますが)。こうなると国籍が同じ人より、ライフスタイルが近い海外の人により近さを感じるのは当然でしょう。こんな時代に国民的なスポーツイベントでみんな一つになんてどだい無理な話。ただ、それでも今はグローバル化に対するアレルギー反応で、やっぱ国家が提供する物語が大事だよねっていう反動が起きているのも確か(ネット右翼)。だから、一時的には国威発揚的なオリンピックは復権する可能性がある。日本は高齢社会だからなおさらその可能性はある。一時的には国民的スポーツで一つに!ってのはウケる可能性があるんです。でも、だからこそ、その反動に注意深くならなければいけない。そのリアリティはたんなる反動現象だよ、と。ここで、オリンピックのもう一つのリアリティが浮上してきます。
先に書いた、多様な身体観を許容するスポーツとは、主にライフスタイルスポーツについて考えるべきことです。ただ、オリンピックは競技スポーツの場。競技スポーツで、世界最高水準が更新される現場というのは、やはり、おそらく人間にとって原理的な感動の現場になり得るのです。マスメディアが提供する選手の苦労話は、所詮は文脈依存的な感動にすぎません。オリンピックをマスメディア主導の(文脈依存的な)感動物語から解放し、原理的なスポーツの感動が生起する場に変換する可能性を今年のオリンピックは持っています。それは何か。この原稿を書いている4月現在、2021年の東京オリンピックは無観客になる可能性が高くなっています。ここにヒントはあります。オリンピックスタジアムでは選手なんて豆粒くらいにしか見えません。しかも日本の選手が勝つとワッと盛り上がってしまうので、結局ナショナリズムを確認する場になってしまいます。そうではなく、例えば5GとVRを駆使して、目の前で100mを9秒台で駆け抜けてゆく選手たちをお茶の間で目の当たりにする。その感動は、たんなる文脈依存的なものではなく、例えば、巨大な滝をみて心を打たれるのと同じような原理的な感動を呼び覚ますものになり得ると思います。無観客になることで、オリンピックを皆でナショナリズムを確認するための儀式から解放し、スポーツの原理的な感動を復権するきっかけにするのです。

こうした、オリンピックについてのリアリティというのは、僕の身近でもほとんど共有されていないし、ましてやテレビなどで話題になることはまずありません。ほとんどは、コンサートが中止なのになんでオリンピックはやっていいんだ!レベルの議論ばかりです。こうした、社会的なリアリティの共有の難しさはなぜ起きるのでしょうか。なぜ、共有されるリアリティはこうも画一化されてしまうのでしょうか。最後に、それを現代の情報環境から読み解き、同窓会論に繋げてみましょう。
3:同じ窓から世界を見るということ
さて、現代の私たちは、インターフェイスを介して世界を見ています。PC、スマホの画面。そして、その情報を集積するAIの高次の眼を通して。2000年代初頭くらいまで、インターネット上には、今よりテキストサイトが多かったですね。私と同世代の人は思い当たるでしょう。そこには、今より、色んな考え方がありました。そして、高度に構築された理論や物語を世間に対してぶつけてゆくという雰囲気が(今よりは)ありました。しかし、東日本大震災以降、潮目が変わりました。SNSの爆発的普及による、いわゆる「動員の革命」です。「絆」、「連帯」の大号令、アラブの春、現在進行形の香港の民主化運動です。2010年代は、SNSを用いて、とにかく人を動員した時代でした。音楽産業の中心はCDからフェスに移動しました。これがある面で非常にまずかった。インターネットとSNSというのは、ちょっと分けて考える必要があるのです。

SNSの何が悪いかというと、アカウントを持つ全員が発信者であり、かつ受信者であるということです。発信者というものは、多かれ少なかれ「いいね」が欲しいし、フォロワーを増やしたい。そうすると、いま皆が関心を持っているテーマ以外を話題にするインセンティブは低くなる。問題についての複雑で専門的に構築された理論は難しいので「いいね」を集めない。結果、問題そのものより、問題についての人間関係(疑似問題)に終始することになる。最近では森喜朗の差別発言で森の人格批判にばかり関心が集まりましたね。他にも、例えば、シングルマザーがネグレクトで子供を死なせてしまったとしましょう。問題は、再発させないために行政や地域社会の役割を再考すること等ですが、SNSでは、その母親の人格批判に集中します(疑似問題)。

加えて、現代ではテレビがそれに加担しています。テレビは視聴率主義なので、SNSから情報を吸い上げて、共感を呼ぶ話題を精査して放送します。コメンテーターの役割は、自分が訴えたいことを構築して視聴者にぶつけるのではなく、視聴者がこう思っているんだろうという
 医療従事者に感謝しても原発廃炉作業員に感謝する人がいないのはなぜか。東京都知事や大阪府知事をディスるだけで、私権の制限が民主主義と矛盾しないのはどのような条件の下においてかを論じる人が視界に入らないのはなぜか。私たちは能動的に世界にアクセスしていると自分では理解しているのに、実際は窓の「外」を遮断された世界に動員されているのです。まさに同じ窓の会です。
医療従事者に感謝しても原発廃炉作業員に感謝する人がいないのはなぜか。東京都知事や大阪府知事をディスるだけで、私権の制限が民主主義と矛盾しないのはどのような条件の下においてかを論じる人が視界に入らないのはなぜか。私たちは能動的に世界にアクセスしていると自分では理解しているのに、実際は窓の「外」を遮断された世界に動員されているのです。まさに同じ窓の会です。
AIはこの「窓」のなかで私たちが関心を持ちそうな話題を先回りして提供します。世界の棲み分けはどんどん進んでいきます。同じマンションの隣人よりも、海外のライフスタイルの近い人のほうがリアリティを共有できるというのはこういうことです。ですが、僕は、最初にこう書きました。同窓会では、社会に対するリアリティが決定的に異なってしまった友人と出会い直すことができると。同じ学校の出身という「窓」は、現代では、国籍がそうであったように、社会に対するリアリティを共有する装置にはなり得ません。逆に言えば、棲み分けが加速的に進む現代の世界で、その画一化を攪拌することは、「同じ窓の会」である同窓会でこそ可能なのです。しかも、同窓会で会うのは、古い友人。かつてのコイツはこうではなかった、というズレの実感を伴った経験が生じます。この経験は、たんに世界観の違う人間とどう接するかという問題にすぎないわけではありません。そうではなく、徐々に価値観や生き方がズレてゆく人と、私たちは、どのような進入角度で接するべきかという問題です。これは、人が歳をとってゆくなかで避けることができない、真剣で切実な問いであるはずです。
もう一度、書きます。完全に生き方が違ってしまったけれど、それでも大事な人というのは、やはりいる。そういう人とどう付き合うか。どう出会い直すか。それを考えることが、すでに過剰なほど繋がりすぎたこの世界で、敢えて同窓会を実施する意味になり得るのではないでしょうか。インターフェイスという「同じ窓から世界を見ること」を無自覚に、しかも徹底的に強いられている現代の私たちにとって、逆説的に、「同窓会」こそが、その外部へと私たちを連れ出してくれるきっかけになり得るのです。
以上、「同窓生の活躍」というタイトルでの執筆依頼でしたが、「21世紀の同窓会論」を展開してみました。めんどくさい奴なので今後同窓会に呼ばれなくなるとしたら、それでも本望でございます。ソクラテスも死刑になったことですし。
(多田圭介)
※「投げ銭」するための詳しい手順はこちらからご確認いただけます
この記事はこちらの企業のサポートによってお届けしています


