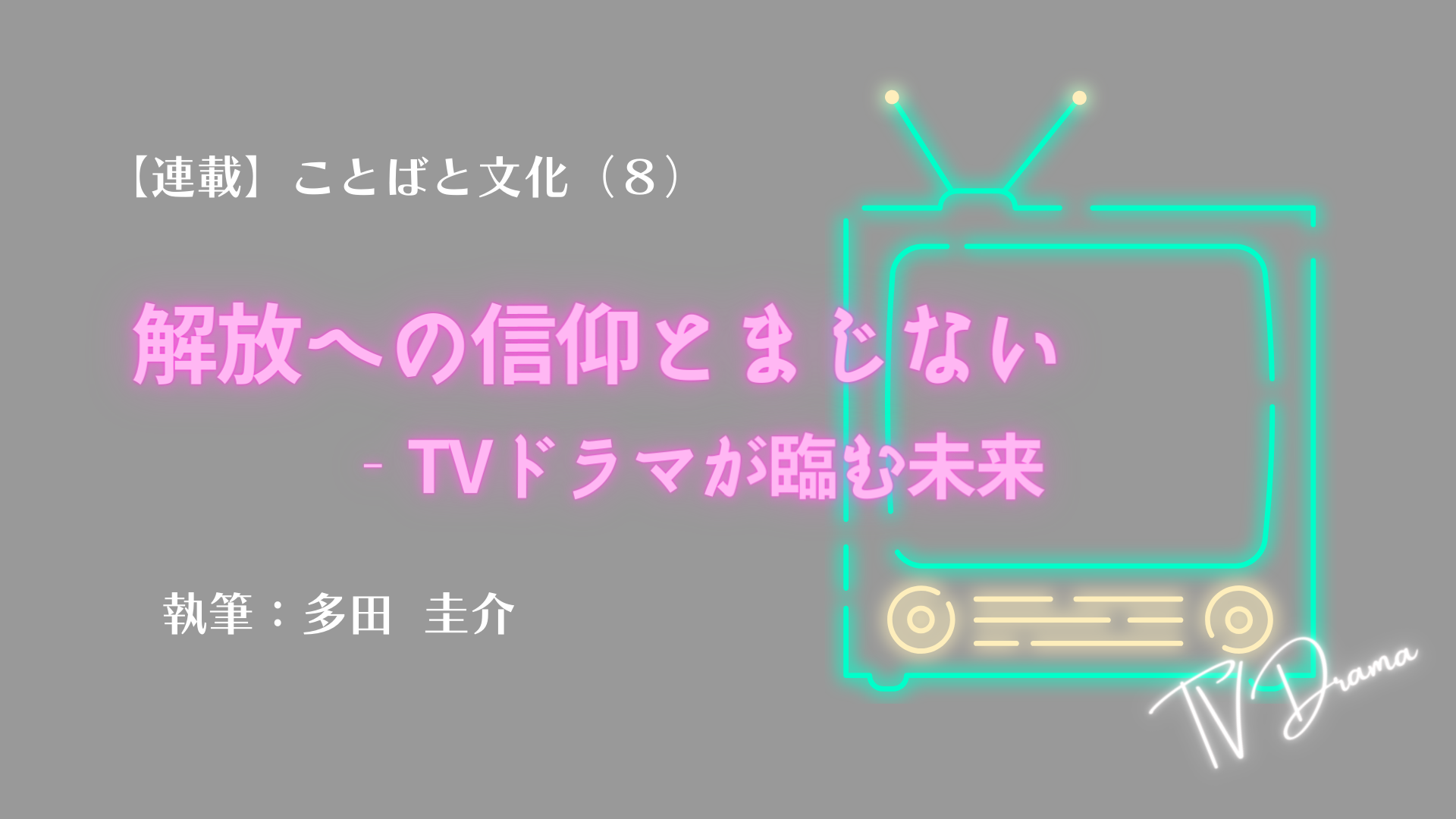ことばと文化(8)解放への信仰とまじない‐TVドラマが臨む未来
「誰から産まれたかなんてそんなに大事なことかな?」
(坂元裕二脚本「anone」第2話より)
「子供にはね、母親が必要なんですよ」、「母親がそう思いたいだけでしょ。」
(是枝裕和監督「万引き家族」より)
「血なんてつながってなくたって、一緒に暮していたら情は湧くし、似てくる」
(是枝裕和監督「そして父になる」より)
この10年ほど、邦画とテレビドラマの分野で人々の心を大きく揺さぶっている映画監督の是枝裕和と脚本家の坂元裕二にはある共通点がある。「子供は誰が育てるのか」。彼らの関心はここに集中している。そしてその関心の原動力には、人と人のつながりについての根本的な懐疑がある。それはおそらく、<成熟社会において血縁によって人が繋がるのは果たして正しいことなのか?>という懐疑である。血縁や地縁は(多くの場合)自分で選べない。自分で選べないものによって人生が決定されることに私たちはどこまで無反省でいるべきなのか。2人の作品からはこうした人と人との<つながり>をめぐる手探りの思考が溢れている。

もちろんこうした物語が必要とされる背景には、現代の喫緊の社会問題への応答という意図があることも無視できない。平成初期にはかつての家父長制的大家族は解体され、核家族化が進行した。その結果、家族は地域コミュニティから切断され、かつて家族を取り巻いていた(良くも悪くも濃密な)地域コミュニティは子育ての機能を果たさなくなった。そこからさらに30数年。長引く不況と女性の社会進出の社会的要請がそこに重なり、血縁者だけが子育てを担うシステムは既に破綻して久しい。こうした状況で「子供は誰が育てるのか」という物語が人々の関心を集めるのは自然なことだ。だが、そこで問われているのは、実はもっと根本的な問題、つまり血縁という自分で選べないものによって人がつながるのは正しいことなのか?これである。少なくとも坂元と是枝の2人が自覚的にこの問いにコミットしているのは間違いない。

人は自分で選べないものに聖性を見出す。天皇制やナショナルアイデンティティから、農村のムラ社会や血縁まで。場合によっては会社や学校でさえそう機能する。こうした共同性は人を強く支える。だがそれ以上に人を強く縛る。そして、その共同性の外部に対して不合理な排除性を行使する(たいてい無自覚に)。多くの人は家族や会社を守るためなら、その外部の人にどれほど不利益が降りかかろうとも顧りみなくなる。こうした共同性が持つ強い排除性に敏感なほど繊細な人はそうはいない。だが人間に共同性が不可欠であることも確かだ。ならば、外部に対して濃密に閉じられた共同性ではなく、中距離に保たれ、外部へも適度に開かれた共同性に足場を移すことはできないのか。「子供は誰が育てるのか」という社会的な要請から彼らが問い進めているのは、こうした共同性の新たなビジョンである。坂元と是枝がそれをどう探っているか。

坂元の最新作は「大豆田とわ子と3人の元夫」(2019)。主人公”とわ子”(松たか子)とすでに離婚した3人の元夫が、特定の誰かと再婚することも、関係を断つこともなく、ゆるゆると付き合い続ける。物語の終盤、会社経営者が新たに登場し、ついにとわ子の4回目の結婚を匂わせる。ハッピーエンドを予感させつつ、坂元はとわ子にその結婚を足蹴にさせ、3人の元夫たちとの中距離の人生を選ばせる。その3人の元夫たちがとわ子の長女を少しずつ支える。これは、坂元による旧来のハッピーエンドへの、そして濃密に閉じられた共同性を前提とするロマンチック・ラブイデオロギーへの強烈なアンチテーゼである。最終話には豊かな希望が溢れている。
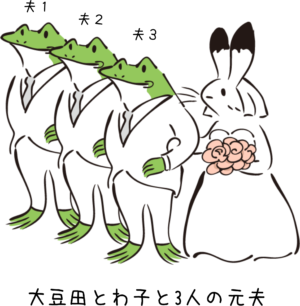
坂元がこうした問題意識を前面に押し出した最初の作品は「Mother」(2010)である。子供嫌いを公言する研究者の鈴原奈緒(松雪泰子)は、極寒の室蘭でゴミ袋に入れられて文字通り捨てられている虐待児童の怜南(芦田愛菜)を保護し、いや誘拐し、継美(つぐみ)という新たな名を与え2人で逃亡する。奈緒は逃亡する中で、かつて幼少のときに自分を捨てた産みの母・葉菜(田中裕子)に再会する。葉菜には30年前に夫を殺害した前科があった。奈緒は葉菜を強く恨んでいる。奈緒の子供嫌いや人間不信にも大きく影響している。だが、物語の終盤で、その殺人は葉菜の夫のDVから葉菜を守るために幼い奈緒が起こした事件だったことが仄めかされる。奈緒にはその記憶がない。だが、葉菜は幼い奈緒を守るためにその殺人の罪を被り、奈緒のことも捨て、<子を捨てた母>という烙印を受け入れて生きていた。奈緒は葉菜に捨てられたのではなく守られたのだということが、暗に仄めかされる最終話は感動的である。

だが坂元はこのMotherでも葉菜によって守られた奈緒と怜南2人の閉じた関係性によるハッピーエンドを置かない。奈緒が誘拐の容疑で逮捕された後、怜南は施設に引き取られる。執行猶予がついた奈緒は、最終第11話で怜南に、20歳になったら読むようにと手紙を手渡し2人は別れる。ここで物語は終わる。別離のエンディングであるがやはりあくまでも希望に溢れているのは不思議でもある。物語を単純に終わらせるのであれば、エンディングは第10話の最後になるはずだ。第10話は、施設から怜南(継美)が(産みの親ではなく)奈緒へ電話するシーンで終わる。そこでの「お母さん、もう一回誘拐して」という怜南のセリフは涙なしには見ることができない。だが、坂元はそこをクライマックスにしなかった。あくまでも閉じた関係性の「外部」を志向しようとしている。坂元は本作でその具体的なビジョンという宿題を自身に課した。

坂元がその宿題に初めて回答を試みたのが「カルテット」(2017)である。同作では4人の主人公たちが登場する。AはBのことを、BはCのことを、CはDのことを、DはAのことを愛している。だが誰の想いも成就することなく、4人の関係は中距離のまま保たれる。濃密に閉じるのではなく、もっと緩やかで、かつ外部へも開かれている共同性がどの程度人を支え得るのかという坂元の思考実験である。「大豆田とわ子」はその別の解答例と言える。

是枝の「万引き家族」(2018)はどうか。やはり産みの親から虐待を受けていた少女”ゆり”を治(リリー・フランキー)が連れ帰り、妻・信代(安藤サクラ)と育てる。だが治の家族は実はまったく血のつながりがない疑似家族であることが分かってくる。一家は年金目的の死体遺棄など次々に犯罪に手を染め、終盤で遂に逮捕され疑似家族は解体される。冒頭で引用したのはその際の取調官と信代の会話だった。「子供には母親が必要なのよ」と<常識>を語る取調官に対し、信代は「母親がそう思いたいだけでしょ」と悪態をつく。是枝がここで投げかけた問いに、坂元は具体的に回答しようとしているのだ。2人は呼応しつつ、たしかに同じ世界に臨んでいる。

家族<から>いったん自由になった者が家族<への>自由を手に入れる。言い換えると、自分で選べない共同性<から>自由になった者が自分で選べる共同性<への>自由を獲得する。自分で選べないものとは、入れ替え不可能なものと言うこともできる。社会が成熟するほど、入れ替え不可能なものはなくなってゆく。だが「入れ替え不可能なかけがえのないものがなくなった」という自覚と、本当に入れ替え可能になってしまうこととは同じではない。前者には「なくなった」という痛切な自覚がある。断念したけど断念した記憶は忘れない。それは苦しいことだけど希望なんだ。是枝と坂元の作品にはこの思考の運動がある。だから、血縁は悪!もう古い!以上!とは決してならない。本当に入れ替え可能になってしまうことをぎりぎりのところで決して許さない。そこが心を打つし、真に思考を喚起する。自由になることへの憧れと重荷へと痛ましいほど引き裂かれつつ、ほんの少しだけ憧れが勝つ。だから彼らの別離の物語は希望のエンディングに見えるのだ。
「誰から産まれたかなんてそんなに大事なことかな?」。この言葉にはもっと大事なものがある<はず>というこの世界の外部を<信じる力>がある。冒頭に引用したセリフの数々には、そう<信じる>ことで世界と自分の<関係性>に変化が生じるはずだという<信仰>に近い何かがある。「世界」を変えてしまうのは「革命」である。「自分」を変えてしまうのは「ドラッグ」か何かだろう。もちろんどっちもアウトだ。では、世界と自分の「関係性」を変えること、それはどうか。それこそが「文化」の力に他ならない。是枝や坂元の作品にはその力が漲っている。

こうした文化の力こそが本当の意味での「愛」だと言える。誰かに対する愛ではなく世界に対する愛である。この意味での愛は誰かと何かを共有することを、むしろ「諦める」ことではじめて成立する。自分が世間(つくづく嫌な言葉だ)と一切関係なく何かを信じることがその成立条件だといえる。何かを信じ、そのために何かを諦めることで成立するような愛。だから是枝と坂元の物語は常に「出会い」ではなく「別離」の物語となる。だから、いかにして手を繋ぐか、ではなく、いかにして手を離すかが描かれる。あくまでも希望として。その別離の物語はゆるやかに交わり続けるのだが、決して一つの物語に収斂しない。それは不幸なことなのではないのだという確信が彼らの作品を支えている。こうした「愛」の可能性は、現代では少しずつではあるが確実に変化してきている。まだ誰にもはっきりとは見えていない。坂元の近作はそのどれもが手探りでエンディングを迎えている。坂元自身にもまだ答えが見えていないからだ。冒頭に引用したようないくつかのセリフは、今はまだ「まじない」みたいなものでしかない。だがそうした言葉を私たちが臆せず発し、そして思考し続けることによって、そのまじないがやがて世界と自分の「関係性」を変えてゆくはずなのだ。少なくとも筆者はそのことを「信じている」からこうして何かを書いている。
(多田圭介)
※「投げ銭」するための詳しい手順はこちらからご確認いただけます