ことばと文化(5)- この世界の「片隅」とはどこか
映画監督の片渕須直が2016年にクラウドファンディングで制作資金を募り公開に漕ぎつけ大きな話題となった映画「この世界の片隅に」(以下「片隅」と略)に別カットを加えた「この世界の(さらにいくつもの)片隅に」が2019年暮れに公開され、この原稿を書いているいま現在ロングランを続けている。この映画の何がそれほど共感を呼ぶのか。おそらく、大きな問題や難しいことから目を背けて目の前の小さな幸福を大切にすることで自分の心を守るこの作品の世界観に観るひとは安心を覚えるのではないか。「わたし、これでいいんだ」と自分を肯定することができるからではないだろうか。SNSの登場によって一時も途切れることなく他者の心とダイレクトに接続され、そのことによる破壊や暴力に心を晒され続ける現代だからこそ、これほどの共感を集めるのだろう。
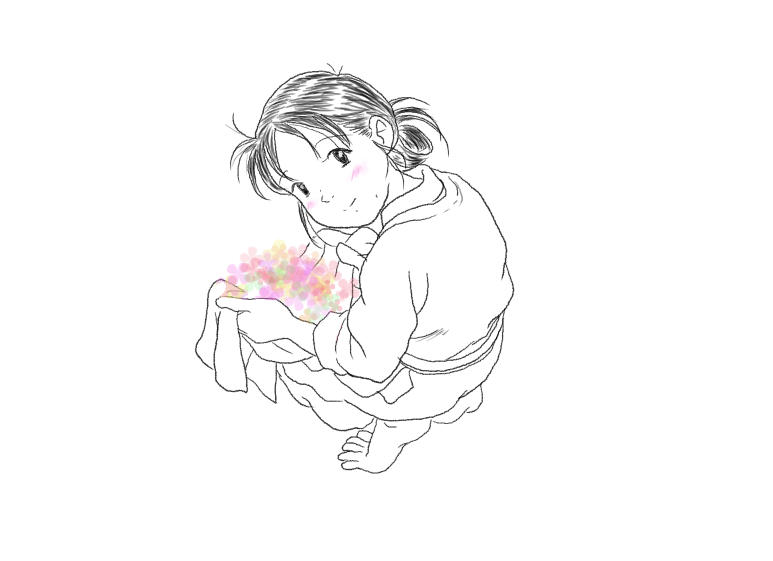 片渕は、小市民的な幸福というものが、破壊から自己を守るためにどう機能するのかを反復して描いてきた作家である。しかし、筆者はこの「片隅」を観たとき、最初は「なんて不甲斐無い映画だ」と感じた。自分の心なんかよりもっと価値のあるもののために戦え、世界を見ろ、自分の気持ちなんかより本当に大切なものを守ることを説け、そう苛立った。この映画で肯定されている感性は、欺瞞から目を逸らしてバカなフリをすることが成熟であるという、まさに戦後民主主義的な感性である。目の前の欲望に忠実に、世界からは目を逸らし、終わりなき日常を生きる。そう、高橋留美子の「うる星やつら」の世界、同時に、それとコインの裏表である全共闘的な自分探しの感性である。「片隅」の主人公、”北條すず”は、高橋留美子の思想的な「母」だ、そう感じた。そして、この映画がこうした文脈で共感を集めることに落胆も感じた。ただ、そう言って済ませるには、この映画はあまりにも美しい。精確に言えば、「美しい偽り」に心が抗いがたく惹きつけられるのだ。片渕という監督は何を考えている作家なのか。
片渕は、小市民的な幸福というものが、破壊から自己を守るためにどう機能するのかを反復して描いてきた作家である。しかし、筆者はこの「片隅」を観たとき、最初は「なんて不甲斐無い映画だ」と感じた。自分の心なんかよりもっと価値のあるもののために戦え、世界を見ろ、自分の気持ちなんかより本当に大切なものを守ることを説け、そう苛立った。この映画で肯定されている感性は、欺瞞から目を逸らしてバカなフリをすることが成熟であるという、まさに戦後民主主義的な感性である。目の前の欲望に忠実に、世界からは目を逸らし、終わりなき日常を生きる。そう、高橋留美子の「うる星やつら」の世界、同時に、それとコインの裏表である全共闘的な自分探しの感性である。「片隅」の主人公、”北條すず”は、高橋留美子の思想的な「母」だ、そう感じた。そして、この映画がこうした文脈で共感を集めることに落胆も感じた。ただ、そう言って済ませるには、この映画はあまりにも美しい。精確に言えば、「美しい偽り」に心が抗いがたく惹きつけられるのだ。片渕という監督は何を考えている作家なのか。
「片隅」は、太平洋戦争へと向かう時期、広島に生まれた主人公”北條すず”が、敗色が濃厚になる頃に呉に嫁ぎ、そこで終戦を迎えるというストーリーだ。すずの目は、自分から半径数メートルしか見ない。戦禍によってどれほどおぞましいものが露出しようとも、ずっこけた笑いに回収され、世界は日常に回帰し、すずの心は救済される。今風に言えば、スルースキルだが、すずは処世術としてそうしているのではない。すずは、発達障害的な面があり、大きなものや複雑な世界が見えない天然キャラなのだ。画面は、ときおりその日常を断絶させるように死の予感を漂わせはするが、それもすぐに背景化する。戦争は表象の遥か上空に薄っすらと重なっているだけなのだ。すずは、終戦の日に一度だけ声を荒げ政権批判をする。が、すぐにそれも忘れ、戦後の長く欺瞞に満ちた平和な日常が始まり物語は幕を降ろす。この映画の本質を一言で表すなら、戦後という長すぎた偽りの時代がいかに始まったのか、その本質を抉り出しただけ、そう済ませてしまうこともできる。
しかし、片渕は、半径数メートルの生活圏しか把握できないすずの目を通してこの世界を描くことになぜここまで執着したのか。たんに自分の心を守るためと言って済ますことができないような、信念、いや執念を感じさせる何かがこの映画にはある。どうしても引っかかり、片渕のエッセイやインタビューを読んだ。すると、こんな一文が見つかった。「不甲斐ないといえば不甲斐ないんですけど、今まで世の中で描かれてきた物語が”不甲斐がありすぎちゃってる”ことへのアンチテーゼなんです」。こう言うのだ。この「不甲斐ありすぎ」というのはもちろん皮肉である。「片隅」ではなく「この世界」へ目を向けることが大事だなんて言っても、身の回りをよく見ろ、世界に発言している連中は何をやっているか、と。
彼らは「戦争がなくなればいい」、「差別のない世界を」といったものすごくロマンチックな社会批判をする。しかし、どうやってそれを実現するのか、あるいは、「差別」が本質的にどういった事態であるのかすら答えられない。戦っているフリをしているだけなのだ。彼らの発言からは、そうすることで文化的で知的な自己像を維持しようという動機以外見出すことはできない。アメリカの哲学者、リチャード・ローティが「文化左翼」と呼んで批判した幼児性の特徴だ。では”右”のほうはどうかと言えば、デカイ何かに自分を重ね合わせて自分が大きくなったような錯覚に浸っている。要するに、世界へ目を向けると言っても、右は自信のない奴の上げ底、左は文化系の自分探しにしかなっていないのだ。SNSで見かける社会的な発言はほぼこのどちらかに回収できる。片渕が述べる「不甲斐がありすぎちゃってる」という言葉にはこうした世相を痛切に皮肉る意図がある。
私たちにとっての、「この世界」(=現実)と「片隅」(=日常=虚構)では、どうしたって、「片隅」=日常が勝ってしまう。私たちは現実にアクセスすることができない。私たちにとって、「この世界」と「片隅」はイコールでしかない。それでは、片渕は、現実には触れられないから諦めろと言いたいのか。どうもそれも違うのだ。この映画では、たった一度だけ、「この世界」が圧倒的な力で「片隅」を侵食し、「片隅」が敗北するシーンがある。
すずは、とりたてて取り柄がない女性なのだが、絵が得意だ。だが、そのあまり、空襲の空すらパレットに見えてしまい、空襲のさなかにふと絵の世界に入り込んでしまい死にかけるというシーンがある。すずにとって「絵を描くこと」は「生きること」と等号で結ばれている。しかし、すずは、空襲でその絵を描く右手を吹き飛ばされる。連れていた姪っ子も失う。直視し難いシーンだが、すずの周囲は、「命が助かってよかったね」、「治りが早くてよかったね」と慰めの声をかける。それに対してすずは、「よかった?」「よいとは?」という身体の底から疑問の叫びを発する。これは、「この世界」が「片隅」に侵食し、「片隅」から、その底を破り「この世界」へと言葉が到達した瞬間だ。
所詮、戦争なんてものは誰も認識できない。私たちは「この世界」の現実に触れることができない。その認識できない「この世界」という「外部」は、すずのように稀な体験によって開かれることはある。だが、すぐに扉は閉じる。扉が閉じた安全圏から「この世界」へアクセスすることは原理的に不可能だ。すずは、たしかに片隅でしか生きていない。だが、右手を失う前のすずは、外部が存在することを知らなかった。しかし、右手を失った後のすずには、外部は確実に存在するのだが、私たちはそれに触れることができないという自覚が生じているはずなのだ。つまり、人間には触れられない外部があるということを自覚すること、それが倫理だという世界理解が生じているはずなのだ。
映画の終盤に、原爆の後の広島市内の描写がある。そこで、原爆で母親を失った女の子が出てくる。母親は、すずと同じように爆撃で右手を吹き飛ばされて死んでいる。その子は、瓦礫の山となった市内を彷徨うなかで、右手がない”すず”に死んだ”母親”を重ね合わせ、すずの残った右腕の上腕部にぶら下がる。すずは、その子に、自分が爆撃を受けたときに助けることができなかった姪っ子を重ね合わせ、その子を我が子として受け止める。そうして、疑似家族がもたらす小市民的な幸福へと回帰し、平和な日常が回復される。あまりに美しい嘘だ。戦後という美しい偽りのプロローグにすぎないこのシーンがなぜこれほど美しいのか。それは、すずが、右手を失うという経験によって、「この世界」という接触できない外部が存在することを知ったからではないか。だから、たんなる疑似家族に収斂するあの結末があれほど美しい余韻を残すのではないか。
この映画は、やっぱり自分の半径数メートルだけ見て、自分の幸せを守る、それでいいのよね、という映画だと受け止められることだろう。あるいは、誰も傷つけない善良なひとの小さな幸福を破壊する戦争の恐ろしさを描いた映画だ、と。そう観るなら、この映画は、その場の「空気」が和やかに流れることが最優先で議論の価値は認めない日本的「空気を読む社会」の原点を描いただけになる。であれば、この映画のタイトル「この世界の片隅に」は、私は「片隅」で慎ましく暮らすだけで誰も傷つけないので責めないでください、という卑屈な臭気を放つことになる。が、このタイトルは、人間は誰であれ「片隅」でしか生きられなくて、原理的に「この世界」という「現実」には触れられないのだ、という世界論を展開したとも解しうるのだ。その自覚が生じたとき、つまり、その自覚を失うことなく、「片隅」から、それでも「この世界」にコミットしようという覚悟を持ったとき、「片隅」は至るところ「世界の中心」に転化しうる。この映画、「片隅」には、そんなポテンシャルがたしかにある。

