ことばと文化(7)- ハイカルチャー、カウンターカルチャー、サブカルチャー、そして・・・
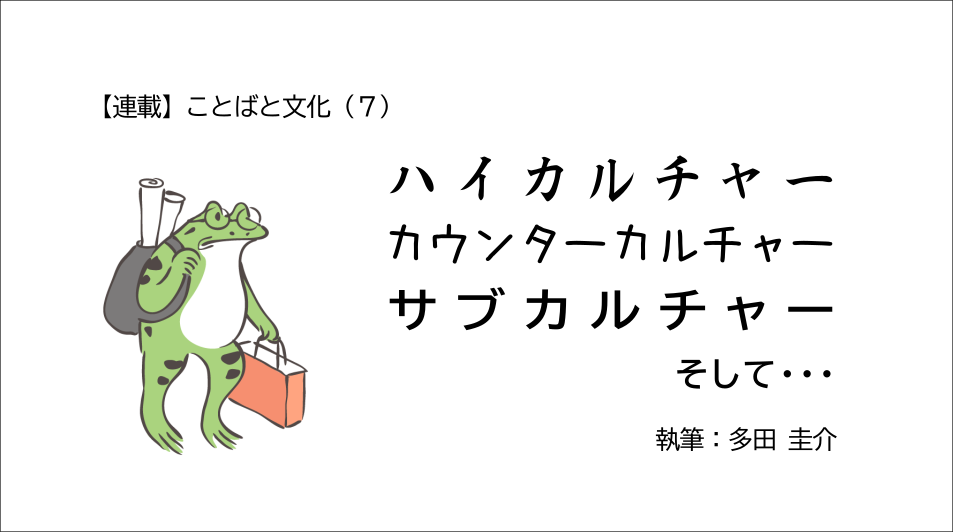
渋谷で道に迷った。急速に再開発が進んだ東口はどっちを向いても高速道路と超高層駅ビル。かつて、消費社会の過剰さと凝縮性の高さゆえに疑似的なカウンターカルチャーとして機能していた広告都市・渋谷は、今や完全に郊外化・匿名化している。渋谷の風景の変貌は、昨今の文化と地理性との関係の変化を象徴している。

かつて銀座はハイカルチャーを体現していた。文化の中心はカウンターカルチャーを象徴する新宿、渋谷へ移り、90年代にサブカルチャーの秋葉原へ移った。そして、ゼロ年代以降のケータイ小説やニコ動は特定の都市性を持たない。文化=カルチャーという言葉は土地と密接な関係を持っている(cultureはラテン語のcolere=耕すが由来)。だが、現代のカルチャーは地理性と切断されている。オタク系文化はその記号性の高さから元来地理性が希薄だから、銀座から秋葉原への文化の中心の移動は、文化から地理性が後退してゆく過程でもあった。これは「中央フリーウェイ」(という地理性)を歌っていたユーミンが、誰でも自分を重ねられる自意識だけを歌うようになっていった過程と重なる。

今は大きな権威に反権威が立ち向かうのではなく、フラットな平面に小さな物語が乱立する時代だ。現代においてカウンターカルチャーを気取ることは簡単(存在しない敵に対してシャドウボクシングをしていればよい)だが、実現するのは不可能である。個人主義と相対主義が浸透し、美醜は趣味の、善悪は法の問題に変換されてしまう現代において表現の強度を生んでいるのは、むしろ市場の過剰な流動性だろう。
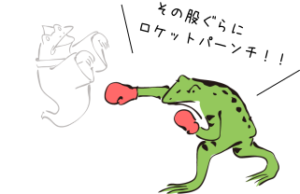
大塚英志が「不良債権としての『文学』」で語ったように、かつて純文学は商業的には成立しないジャンルだとされてきた。それでもこの分野は出版社などの体面の維持につながるから社会的に保護されてきた歴史がある。しかしハイカルチャー的なものの権威がフラット化された現在、ハイカルチャーとサブカルチャーの奇妙な逆転現象が起きている。川上未映子が2009年に発表した小説『ヘブン』はそれをうまく可視化している。
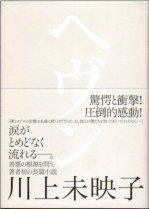
川上未映子(2009).『ヘヴン』、講談社
同作の主人公は14歳の男子中学生「僕」。僕は斜視にコンプレックスがあり苛烈にイジメられている。そんな僕の前に少女「コジマ」が現われる。コジマは僕に「斜視の目が好きだ」といい僕のすべてを承認する。そこへもう一人「百瀬」が登場する。百瀬はいじめっ子。百瀬は僕とコジマに、「社会がまとまるためにはスケープゴートが必要でたまたま僕がそれをあてがわれただけ」という。同作では、身体性に表現の強度(斜視という市場では不利なもの)を認め、それを自己確認の根拠とする「コジマ」は、ハイカルチャー的なものを、そしてすべての価値が偶然的なものにすぎないとする「百瀬」はサブカルチャー的な市場の流動性を象徴している。そして「僕」は「コジマ」の聖性に惹かれながら、そこに独善の匂いを嗅ぎ取り距離を置くようになる。「コジマの独善」は「社会的に保護されたハイカルチャーの独善」に重なる。
海外の日本文化への関心が圧倒的にサブカルチャーに寄っているのはなぜか。それは文化と地理性の切断と関係がある。地域や階級といった世の中を差異化する力が弱くなると、それが表現を構成する「外部性」として機能しにくくなる。すると過剰さゆえの「誤配」に開かれている、肥大化した市場のダイナミズムのほうがまだ(相対的にではあるが)「外部性」として機能することになる。市場が肥大化した社会とはすべてがコミュニケーションで決定されるフラット化された社会である。市場から切断されたハイカルチャーは必然的に衰退し、否応なく市場に対峙させられるサブカルチャーが隆盛する。ただ、一般的に前者(ハイカルチャー)の担い手や愛好家は、後者(サブカルチャー)をマーケティング的な迎合であると批判しがちだ。だが実際には、今は前者の担い手・愛好家のほうがフラット化された社会のなかで、より閉鎖的なコミュニティを形成している。そこで評価される作品は閉鎖的なコミュニティの嗜好に対する傾向と対策に準じたものになりがちだ(純文学新人賞のパターンは簡易に大別できる)。反対に、過剰な市場に晒されるサブカルチャーのほうにユニークな存在感を放つ想像力が生まれているのはまぎれもない事実だ。

特定の共同性に奉仕する現在のハイカルチャー的想像力は、閉じられた共同体の内部には強い求心力を放つが、そこでは共同性を攪拌するノイズは忌避され、共同性に奉仕するもののみが評価されることになる。現代の文化的言説はその自覚が足りない。例えば『映画秘宝』は、TV局主導のメディアミックス作品を否定的に扱う一方で、特定ジャンルの映画史に大きく依存したマニアックな作品(タランティーノ作品など)を擁護する。読者層は中年男性。彼らは自己憐憫的で明確かつ単純なイデオロギー性を帯びた共同性を形成してしまっている。この状況で相対的にメジャーな作品を相対的にマイナーな立場から批判してもヒエラルキー上下での応答にはなりえない。せいぜい相対的に小さい共同体から相対的に大きい共同体を攻撃することで共同性を内部で確認し合う効果しか生まない。
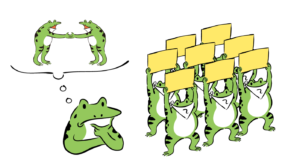
カルチャーのフラット化は言葉のフラット化でもある。言葉には「真理の言葉」と「機能の言葉」がある。フラット化した世界で私たちは「真理の言葉」を、無自覚に「機能の言葉」として使う。つまり「真理を言う(ように自分を見せる)と信用されるから真理を言う(フリをする)」、すべては突っ込み芸だと知りながら政治的にガチンコ芸のフリをする。例えば、著名人のトークイベントのスタッフなどをみると、彼らは登壇者の話なんか聞いていない。イケてるイベントを手伝いイケてる自分になるのが目的で、登壇者もそれを承知している。すべてがフラット化されるということは自分の外側が消失するということである。どんなにレジームが変わろうが、錦の御旗がどっちに立つかがすべてを決する鳥羽伏見状況。何もかも変えても何も変わらないから何もかも変えることができる。こうした特殊日本的文化性は元来からハイカルチャーの権威や普遍性を脱臼させるゲームであった。だが、それを悪しき日本文化と罵るよりも、そこに文化資本としてのアドバンテージを認めるほうが実効的である。「そろそろ正史を」とホザく連中が戦前は動員の片棒を、戦後ならオウムの片棒をかついだわけだし。市場の徹底した流動性のほうに新しい想像力が生まれる特殊日本文化は相応しく成熟したのかもしれないのだ。
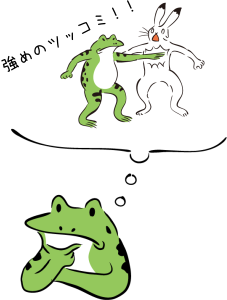
この視点は情報環境から見るなら、私たちが否応なく世の中にコミットメントしてしまっている事実に目を向けることにつながる(「大人になる」のではなく「なってしまっている」)。昔は世の中に対してなにかアクションを起こそうと思ったら、ある権利を手に入れる代わりにある責任を負うというそれなりの手続きを踏む必要があった。だがネットワークに常時接続されて生きている現在はただ生きているだけで責任主体とされてしまう。いま何をポチったかさえAIに回収される。小さな権力を分散して持たされる。この主体像の変化は、文化と地理性の切断のもう一つの変化を浮上させる。それは、「作品」から「環境」への変化である。ニコ動に投稿された二次創作のうちのかなりの割合のものが純粋な趣味として、あるいは同人活動として制作されている。彼らの「消費」はそれ自体「作品」となるシステムが作動してしまっている。そこでは動画を制作した「制作者の作家性」と同等かもしくはそれ以上に、彼らの創作意欲を刺激した「環境=システム設計者」という<潜在性の次元>が作家性を帯びてくる。同じことは他の文化ジャンルにもいえる。例えば「M1」などの個性的なアーキテクチャがタレントの作家性より存在感を増しているお笑いがそうで、それは文学、また建築領域にも波及している。
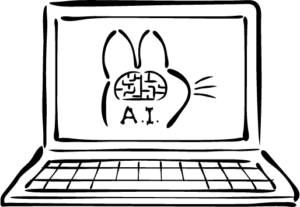
藤村龍至が述べるように、現代の建築は、市場の流動性から作家性を守る「アトリエ派」と、批評知によって創作を理論化することを放棄し徹底して市場に応える「組織派」に二極化している。そして、ここにおいても、アトリエ派による反市場主義が、当事者の自意識とは反対にミニマムな市場へのマーケティングにしかなっておらず、むしろ組織派のほうに、システムレベルの工学知を導入することで市場性を強力な外部性として機能させ巨大な影響力を振るう作品が生まれている。これは藤村が述べるように、たんなる市場主義でも、閉鎖的な反市場主義でもない、上書きされた市場主義=批判的工学主義と言い得る。

ゼロ年代に進行したネットワーク化によって、人と物語テクストの関係は変化した。ライトノベルやケータイ小説ブームはこの事実を突きつけるものだった。だが国内文学の世界はその意味を真剣に考えようとしない。文学の定義を揺るがすような存在は黙殺しておきながら、純文学の勝利を仲間内で謳歌する。村上春樹の『1Q84』も現実に追いついていない。9.11以降の暴力を扱うと述べながら、未だに自分はコミットメントする資格があるのかと煩悶している。悩むのはいいが結論が分かり切っているのに悩んだフリをするのは倫理でもなんでもない。不可避的に世界に接続され、誰もが小さな父としてコミットメントしてしまうのが現代だ。せめてなんの自覚もないのに子供がいて自分がそれに戸惑っているところから始めなければ。さて、我らがクラシック音楽、舞台芸術はどうか。

文化が地理性から切断され文化は市場の海を漂い始め、ハイカルチャーの権威は失効し、そして「作家性」は作家の内面から(少なくとも何割かは)環境に、システム領域に移行した。この変化を受け入れ、多くの表現が消費財でしかないことを逆手にとって、市場の流動性をシステムに取り込むことで、その過剰さゆえの誤配によって淡白な表現を抜け出したものへの視点なくして現代の文化は語り得ない。あらゆる人が文化の(小さな)担い手であり得るという視点から、真に普遍的なもの、質の高いものが蘇生する可能性は閉ざされていない。時代に追い抜かされたルサンチマンから失効した権威に寄り掛かって新しい世界を批判する(ネトウヨ)のではなく、今ここから生まれるものに目を向けることなくして文化を語る資格はない。
(多田圭介)
※「投げ銭」するための詳しい手順はこちらからご確認いただけます



