新国立劇場バレエ団「眠れる森の美女」レビュー(11月14日@札幌文化芸術劇場hitaru)
2020年11月14日(土)札幌文化芸術劇場 hitaru
 11月14/15日にhitaruで開催された新国立劇場バレエ団「眠れる森の美女」の初日を観た。劇場がオープンした2018年から継続されたチャイコフスキーの3大バレエがこれで一応の完結をみた形となる。各公演は、いずれも古典的な舞台であった。だが、「眠れる森の美女」(以下、「眠れる」と略記する)は他の2作以上に古典的であることそのものに意味がある作品だ。それゆえに、ごくわずかに施された演出が舞台の解釈を多様化させる分岐点になっていたところも興味深かった。
11月14/15日にhitaruで開催された新国立劇場バレエ団「眠れる森の美女」の初日を観た。劇場がオープンした2018年から継続されたチャイコフスキーの3大バレエがこれで一応の完結をみた形となる。各公演は、いずれも古典的な舞台であった。だが、「眠れる森の美女」(以下、「眠れる」と略記する)は他の2作以上に古典的であることそのものに意味がある作品だ。それゆえに、ごくわずかに施された演出が舞台の解釈を多様化させる分岐点になっていたところも興味深かった。
さて、ここでいう「古典的」とはいかなる意味か。まずは、初演時のプティバの振付との連続性を指す。ただ、「眠れる」は、作風そのものが古典を志向している点も無視できない。まず、本作はバレエの起源である宮廷文化に立ち返った「品性」にこそ本質がある。例えば「ライモンダ」からベジャールの「バクチ」に至る一連の作品群はどうか。これらの作品群に目立つエキゾティシズムの介入は、「眠れる」においては、あえて、徹底的に引き算されている。舞台は、混じり気のないクラシック・ダンスの規範性が一貫する。そのなかにあくまでも踏み外しのない品格や優美さを求められる。この意味でも「眠れる」は「古典的」なのだ。ゆえに、hitaruオープンから継続された3大バレエ公演がいずれも「古典的」舞台であったとはいえ、「眠れる」においてはその意味は異なってくる。
ただ、「眠れる」という作品、さらには当日の公演も視野に収めるなら、この「古典的」という言葉には、ギリシャ以来の西洋舞台芸術の継承という意味も響いてくる。ここに注目しなければならない。それは、「リラの精」と「カラボス」の対比の意味である。ギリシャ文化に通じていれば自明なことであるが、リラの精とは、ギリシャ神話において知恵を司る女神アテネの姿をとる。また、長い歴史を経て19世紀末のロシアでは「光」を象徴する花の名前となっている。知恵を司る「光」。清朗に晴れ渡り、混沌と闇に秩序をもたらす光。このニュアンスが「リラの精」という名前には響いているのだ。では、カラボスのほうはどうか。”boss”とはフランス語で背中の「こぶ」を意味する。西洋の演劇やオペラで、伝統的に「こぶ」は、忌むべきもの、混沌、カオスの象徴である。ここに、光と闇、秩序と混沌、生と死という、ギリシャ以来の二元論的な世界観の反映を見てとるのは容易であろう。「眠れる」は最も本質的にはこの意味で「古典的」なのだ。
まとめると、第1にプティバの継承、第2に宮廷文化への立ち返り、第3に西洋的な二元論的世界観。「眠れる」を論じるときに使われる「古典的」という表現は、本質的にはこの3つの意味を包括することになる。そして、19世紀末にこの「古典性」を描くことは、舞台にある「ねじれ」をもたらすことになった。そして、当日の舞台は、幕が上がるとすぐに、この「ねじれ」を可視化してみせた。いや、制作者は無自覚かもしれない(おそらくそうなのだろう)。だが、当日の舞台は、作品が抱え込んだ「ねじれ」、そしてそれに対する自己言及的な展開までを高い純度で提示するに十分な出来だったと言える。それは、作風がエキゾティシズムを排したがゆえに、制作した(上演した)バレエ団の文化風土をストレートに反映した結果だったとも言える。いずれにしても、ある文化現象を「古典的」であるままに維持することそのものの「意義」を考究させる内発的な力がある舞台だったことは間違いなかろう。
プロローグの幕が上がると、舞台の最上部にリラの精、そしてその垂直下にカラボスが位置していた。オーケストラによって序奏(カラボスのモチーフ)が奏されると、リラの精がゆっくりと降下し、舞台中央最前部で、カラボスと火花が散るように対峙し、物語は始まった。ここで観衆は、この物語はオーロラ姫とデジレ王子の物語なの
しかも、カラボスをマイム役ではなく、トゥシューズを履いたダンサーが演じたこともこの解釈を強調することになった。マイム役だと、やがてリラの精の光によって世界が一元論的に呑みこまれてゆくような弱さが出てしまうからだ。カラボスを踊ったのは本島美和。長い手足を蜘蛛のように操り、リラの精と対等に舞台を彩る(現に後の幕でカラボスは巨大な蜘蛛の装置に乗って舞台を駆け巡った)。
この開始は、物語の展開を何重にも攪拌した。まず、通常の本作の解釈である「オーロラ姫のビルドゥングスロマン(成長物語)」としての「眠れる」、そしてリラの精と人々の愛が混沌に完全勝利する祝福された世界という「眠れる」。この作品理解を徹底的にエポケーした。古典に徹するがゆえに、そうであったことが重たい。
プロローグに続いて第1幕。ようやくオーロラ姫が登場する。舞台に姿を現わした瞬間の華。周囲に次々と挨拶する仕草のデリケートな品格。無垢な輝きがオーロラ姫を中心に水面の輪のように広がる。オーロラ姫を踊ったのは小野絢子。日本人らしい小柄な体型が、プラスに作用している。謙虚で皆から愛される第1幕のオーロラ姫像に相応しいのだ。
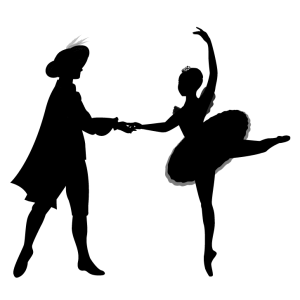 ローズ・アダージョでの技術の高さも申し分ない。ここでオーロラは、ポワントのままアチチュードの姿勢を続ける。しかも、エスコート役が交代するそのたびに、エスコートの支える手から完全に離れ、アチチュードでバランスをとることを要求される。小野は、全身が揺れないのは当然のことであるが、それ以上に、両腕を基本ポジションに揃える際の余裕のある手の動きが見事だった。ここで慌てて手を降ろすように見えてしまうと、オーロラの品格を損なうからだ。「眠れる」が宮廷作法の古典回帰だというのは、こういうところに典型的に表れている。派手な身振りよりも、基本動作の完成度と優雅さが何より重視されるからだ。
ローズ・アダージョでの技術の高さも申し分ない。ここでオーロラは、ポワントのままアチチュードの姿勢を続ける。しかも、エスコート役が交代するそのたびに、エスコートの支える手から完全に離れ、アチチュードでバランスをとることを要求される。小野は、全身が揺れないのは当然のことであるが、それ以上に、両腕を基本ポジションに揃える際の余裕のある手の動きが見事だった。ここで慌てて手を降ろすように見えてしまうと、オーロラの品格を損なうからだ。「眠れる」が宮廷作法の古典回帰だというのは、こういうところに典型的に表れている。派手な身振りよりも、基本動作の完成度と優雅さが何より重視されるからだ。
第1幕では、オーロラ姫の正対(客席に向かって正面を向くこと)が多用されたことも印象に残った。例えば、「白鳥」のオデットなどは、アラベスクの際に正対することはほぼない。客席正面から見て斜めの角度が多用される。長いラインを見せるためでもあるのだが、オデットという役の内省的な性格を示すことになっている。それに対する、オーロラの太陽に照らされたような歪みのない精神を思わせる正対は、プティバの振付のオーロラ像を美しく引き継いでいる。ただ、プティバの振付と比較すると「掌(てのひら)」は見えなかった。普段隠れている掌を正面に見せることは、オーロラのオープンな性格を強調することになるのだが、あるいは小野がそう踊ったのかもしれない。こうした、明るく澄みきったオーロラの性格描写は、オーロラがリラの精のミクロコスモスであることをよく表現していたと言える。
さらに興味深かったのは、第2幕以降も小野が踊るオーロラは、その基本性格を変えなかったことだ。オーソドックスな解釈では、オーロラは徐々に王妃へと成長するように踊る。まず、第2幕でリラの精がデジレ王子に見せるオーロラ姫の幻影も健康そのものだった。決して男性目線の願望を投影したような妖艶なイメージは見せなかった。第3幕でも、小野のオーロラに成熟したエレガンスを認めることはできない。あくまでも初々しい。
オーロラ姫はなぜ成長しないのか。成長しないこと、そのものに意味はあるのか。大アリなのだ。第2幕で、デジレ王子は、リラの精が見せるオーロラの幻影に魅せられる。そしてカラボスを打ち負かし、姫の眠る城へ向かう。一見、デジレ王子が姫を愛の力で救出する物語に見えよう。しかし、デジレ王子の冒険は、実際には、リラの精の手中でコントロールされている。「眠れる」というバレエのデジレ王子の冒険は、実のところ、リラの精の胎内で安全に守られた「ごっこ遊び」にすぎないのだ。「眠れる」は、リラの精という、デジレ王子を庇護する偉大な母性の胎内で完結した冒険にすぎない。演出によっては、デジレ王子がカラボスの前を通り過ぎるだけでカラボスが勝手に消滅するものもある。古くから、こうしたデジレ王子の「勝利」は出来レースだと批判されてもきた。シルヴィ・ギエムも、「眠れる」は第1幕までで終わっていて、第2幕以降は面白くないと公言している。だが、出来レースであることそのものに意味があることになぜか多くの論者は気づかない。当日のイーグリングによる振付でも、デジレ王子は客席に向かって投げキッスをする。それだけで、舞台最後方でカラボスが沈んでゆく。デジレ王子はオーロラ姫への(世界への)愛を表現しただけなのだった。ここに、「愛が世界を救う」という表面的なメッセージを超えて、この対決がリラの精によって安全に護られた「ごっこ遊び」にすぎないというメッセージを二重に読み取るのは容易ではないか。
安全に庇護された「ごっこ遊び」の冒険で誰が真に成長できようか。デジレ王子が成長しないはずであるのと同様に、その愛を受けたオーロラ姫が成長しないのは当然ではあるまいか。第3幕では、カラボスの混沌の力、闇の原理は消失し、舞台はリラの精の完全勝利に包まれる。当日の舞台ももちろんそうだった。だが、よく考えてほしい。リラの精とカラボスは、共に二元論的世界の両極の原理であったはずだ。カラボスをマイム役ではなく、トゥシューズで踊らせたこともその強調になるはずだ。なら、闇の原理はどこに消えたのか。愛によって文字通り消失したのか。消失する原理なら原理ではない。そう、闇の原理は第3幕では、見えなくなったのだ。消えたのではなく、勝利の光の下で見えなくなったのだ。リラの精の勝利は実は完全勝利ではなく、一時的な政治的な勝利でしかないはずである。光の原理と闇の原理の拮抗において、一時的に政治的勝利を収めたにすぎない。冒頭で両者を対峙させたイーグリングのこの舞台では殊にそう解さざるをえない。
実のところ、当日の演出はこの「眠れる」という作品が抱え込んだ「ねじれ」を可視化している。本作の成立の事情から読み解こう。「眠れる」は、19世紀末にバレエ化されるときに、政治的理由で内容をかなり歪曲されている。原作にあたるシャルル・ペローによる「いばら姫」には、祝宴で終わる「眠れる」の「その先」がある。ペロー版では、祝宴の後、王子の母が人喰いであることが発覚し、世界は再び混沌に落ちる。「眠れる」の第3幕は、本来は一時的で政治的な勝利でしかない。ペローの原作からは、あらゆる結論は暫定的なものでしかないという思想を読み取ることができる。しかし、「眠れる」は帝政ロシアのアレクサンドル3世を喜ばせるために、ここに手を加え、リラの精の完全勝利の物語に変えているのだ。かつ、帝国が、精たちに護られ永劫繁栄するという設定を3世は好んだ。だから、デジレ王の冒険も、第3幕の祝宴も、精たちに安全に護られた「ごっこ遊び」にすぎないように描かれたのだ。
チャイコフスキーはこの設定に納得していなかった可能性が高い。なぜなら、光と闇の原理を指示するライトモティーフが、第3幕ではまったくといっていいほど使用されなくなるからだ。もし、光の完全勝利の物語にするなら光のモティーフが使用されなくなる理由が説明できない。楽譜を読む限り、2つの原理の拮抗というこの世界観を大切にするがゆえに、その構造を第3幕では棚上げしたように思える。
だが、この改変された「眠れる」という作品、そして、当日のイーグリングの演出を施された舞台は、現代の私たちにとっての「舞台芸術」という分野の「これから」を展望したように感じられる。最後にまとめよう。
近代的な19世紀の舞台芸術や文学というジャンルは、「発信者」と「鑑賞者」が分かれており、鑑賞者は創作に介在できないところにその特徴がある。20世紀の劇映画もそうだ。こうした近代的な文芸は、このような条件の下で、鑑賞者に「これって、もしかして俺の物語かも?」と錯覚できるようなアクロバティックな操作を施すことによって成り立っていた。しかし、それゆえに、本質的に「他人の物語」であらざるを得ないという限界も持っている。それが他人の物語である以上、そこに鑑賞者にとっての当事者的な「痛み」を織り込むことは原理的に困難である。これは、「眠れる」でいうなら、デジレ王子の男性的な自己実現が、リラの精の胎内から一歩もでることなく完結していることに対する批評的な視座をもたらす。「眠れる」におけるデジレ王子の冒険には安全な痛みしか用意されていない。だが、それゆえにこそ、このデジレ王子の安全な冒険は、19世紀的な舞台芸術に、観客にとっての「当事者的な痛み」を織り込むことの難しさをメタ的に記述したとも解しうるのだ。
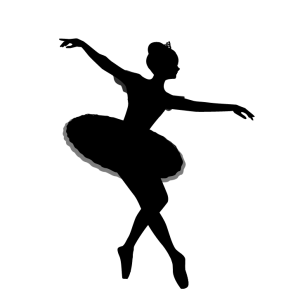 イーグリングの振付でカラボスは、なぜ、たかだかデジレ王子の投げキッスだけで、戦わずして沈没したのか。なぜ、誰も「痛み」を引き受けることなくリラの精は完全勝利するのか。これは、見方を変えるなら、リラの精の完全勝利の、その「外部」を示唆しようにも、19世紀的舞台芸術の手法ではどうやっても「安全な痛み」に回収されてしまうということ、これに対する、19世紀舞台芸術の側からの自己批評的な応答と解しうるのではないか。では、19世紀的な舞台芸術の限界に現代の私たちはどう対応すべきか。もし、これからも「古典」のまま維持し上演し続けることに意味があるとするなら、その役割はどこに見出すべきか。
イーグリングの振付でカラボスは、なぜ、たかだかデジレ王子の投げキッスだけで、戦わずして沈没したのか。なぜ、誰も「痛み」を引き受けることなくリラの精は完全勝利するのか。これは、見方を変えるなら、リラの精の完全勝利の、その「外部」を示唆しようにも、19世紀的舞台芸術の手法ではどうやっても「安全な痛み」に回収されてしまうということ、これに対する、19世紀舞台芸術の側からの自己批評的な応答と解しうるのではないか。では、19世紀的な舞台芸術の限界に現代の私たちはどう対応すべきか。もし、これからも「古典」のまま維持し上演し続けることに意味があるとするなら、その役割はどこに見出すべきか。
まずは、舞台に接した現代の私たちの世界の見え方が、その舞台に触れることによってどう変わるか、ここに意味を見出すべきであろう。これは他人の物語であるがゆえに可能な19世紀的総合芸術の美質だ。すなわち、「他人の物語」でなければ、自己を絶対的に超えた、隔絶したものに出会い、自己が本質的に変容させられるという体験は生起しないからだ。しかし、社会が情報化された現代では、自分が介在できない分野(他人の物語でしかない分野)に価値はつきづらい。20世紀的な映画が消費形態を変えつつあることもそれへの対応だ。ディズニーを始めとする現在の映画産業は、世界同時公開することによって、鑑賞者たちがその体験をシェアするこという仕方で消費されるようになってきている。鑑賞者自身が何らかの形で介在できる形で延命している。
舞台芸術は今後どのように生き残るべきか。19世紀的な総合芸術は、他人の物語だからこそ可能な、自己から隔絶したものとの出会いをその芸術性の本質としてきた。このありようをどう残すか、まず一つ目の回路はここにある。それがどれほど困難であっても、この回路を根絶すべきではない。「眠れる」でいえば、カラボスのようなキャラクターの「他者性」の保持であろうか。ただ、自分が介在できない物語に値段がつかなくなるのもたしかだ。であれば、19世紀的な舞台芸術が「ごっこ遊び」に回収される回路を受け止めて、決して当事者にはなり得ない、共感の不可能性のようなものを19世紀的舞台芸術のなかにいかに織り込んでゆくか。このあたりになるのではないか。もし19世紀的な舞台芸術が、情報化された社会のなかで、現在の上演形態を維持しつつ、かつ舞台芸術のレゾンデートルを示そうとするなら、方向性はこの2点に絞られるだろう。総合芸術の他者性を粘り強く温存するか、あるいは、共感の不可能性を作品に織り込んでゆくか。これらの視点が抜け落ちるなら、イベント消費化することで、たんに情報化における価値の転換を追随するしかなくなるであろう。舞台に上がる演者や演出家は言うまでもなく、主催や制作サイドにも、そのレベルの教養と文化的資質が求められるようになる。
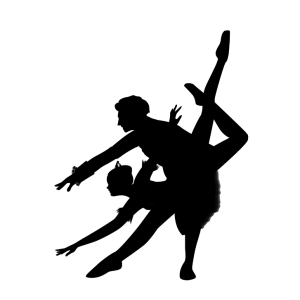 そして批評も変わらなくてはならない。現在の音楽評論をはじめとする文化批評の多くは、すでに確立されたジャンルの意識に捉われて、業界の空気のなかで「イケてるもの」と「イケてないもの」を峻別することくらいしかできていない。その「空気」を攪拌するのが批評の役割であるにもかかわらず、である。いずれにしても、ただ「文化だから」というだけで、無反省に同じことを続ける惰性を肯定する回路はとっくに切れている。「古典」であるがゆえに変えてはいけないものもあれば、変わるべきものもある。hitaruオープンから、足かけ3年かけてチャイコフスキーの3大バレエの上演は完結した。地ならしはもう十分だ。hitaruのバレエ公演は、ただ「文化だから」というだけの理由で形式的な「古典」の上演を続けていてはもういけない時期に来ている。11月14日、「眠れる」の幕があがったときにリラの精とカラボスの対峙が現前したその瞬間、劇場はその課題を「自分の痛み」として抱え込むべきだったのだ。最後に、hitaruやKitaraで公演を企画する団体に、そしてすべての批評家に、ラインホールド・ニーバーの次の言葉を贈りたい。
そして批評も変わらなくてはならない。現在の音楽評論をはじめとする文化批評の多くは、すでに確立されたジャンルの意識に捉われて、業界の空気のなかで「イケてるもの」と「イケてないもの」を峻別することくらいしかできていない。その「空気」を攪拌するのが批評の役割であるにもかかわらず、である。いずれにしても、ただ「文化だから」というだけで、無反省に同じことを続ける惰性を肯定する回路はとっくに切れている。「古典」であるがゆえに変えてはいけないものもあれば、変わるべきものもある。hitaruオープンから、足かけ3年かけてチャイコフスキーの3大バレエの上演は完結した。地ならしはもう十分だ。hitaruのバレエ公演は、ただ「文化だから」というだけの理由で形式的な「古典」の上演を続けていてはもういけない時期に来ている。11月14日、「眠れる」の幕があがったときにリラの精とカラボスの対峙が現前したその瞬間、劇場はその課題を「自分の痛み」として抱え込むべきだったのだ。最後に、hitaruやKitaraで公演を企画する団体に、そしてすべての批評家に、ラインホールド・ニーバーの次の言葉を贈りたい。
変えることのできるものについて、それを変えるだけの勇気を我らに与えたまえ、変えることのできないものについては、それを受け入れるだけの勇気を我らに与えたまえ。そして、変えることのできるものと、変えることのできないものとを識別する知性を、我らに与えたまえ。
-ラインホールド・ニーバー
(執筆:多田 圭介)
※「投げ銭」するための詳しい手順はこちらからご確認いただけます












