【STJ第9号掲載】特集「地方芸術祭の今」巻頭記事&編集長コラム「ことばと文化(9)」

ここ20年ほどで日本でも地方で開催される芸術祭が本当に盛んになってきた。音楽祭だけでも霧島、武生、金沢など数えきれないほどの地方がそれぞれに個性的な音楽祭を催している。他方で、現代において地方で芸術祭を開催する意義はどこに求められるのか、もっと言えば、地方=土地が持つ文化的な生成力とは何であるのか。この、より本質的な問題が問われることはあまりない。そこで本紙では、群雄割拠の地方芸術祭のなかでも際立ったコンセプトを打ち出している音楽祭の主宰者に声をかけてその趣旨を大いに語ってもらうことにした。まずはその前に先鋒として、筆者(多田です)が問題提起したい。
けれども先に断っておくべきことがある。筆者は衰退する地方に活気をもたらすために「ゆるキャラ」や「B級グルメ」で地方創生を目論むような運動には興味がない。そしてその反対の21世紀を席巻するメガシティ間の競争とそれに対応するためのビジョンにも同じように興味がない。ここで考えたいことは地方≒土地≒場所≒空間が持つ文化的な生成力それ自体についてである。それも「2020年代の今における」それである。
情報技術の発展はこの四半世紀で空間の定義を変えつつある。例えばこれまで「都市」と呼ばれてきたものはどうか。僕たちはそこへ接続することで自分が独立した「個」であることを確認してきた。「地方」はどうか。それはしがらみが多いムラ社会ではあるが私たちはそこで温かく人間を支える共同性を手に入れてきた。しかし、いま空間の移動はこの「個」と「共同性」の間の移動をかつてのようには意味しなくなっている。そもそも同じ空間にいることがその対象とコミュニケーションすることを意味しない(現に僕はいま札幌のカフェでこの原稿を書きつつ横浜の友人とチャットしている)。僕たちは、どこにいようともネットワークに常時接続され、家庭、職場、そして「世間」から襲いかかってくる通知から逃れられない。
あるいは、僕たちはかつて固有の土地に接続することで、目当てではないものに偶然出会ってきた。しかしこの前提も崩されて久しい。実際にコロナショックが席巻する前の10年間は、あらゆる文化的な現象がSNSと接続され、そしてその動員力によって人間を実空間に駆りだしてきた。インスタ映え、アイドルの握手会から音楽フェス、さらには政治運動まで。この10年は、実空間が実質的にサイバースペースの延長(一部)でしかなくなった10年だった。SNSによって動員されて街へ出た人は、そこにどれほど雑多なものが立ち現われていても、最初から目当てだった物以外、意識できなくなってゆく。実際に何を目で見、手で触れていようともそうなってゆく。2020年代の現在においては、地方も実空間も、検索とハッシュタグの先に存在する。これは「場所」の力が、爆発的に上昇した検索能力に負けてしまったことを意味する。ネットワークの整備と世界の情報化は、一方で土地や空間の力を低下させていった。さて、それではSNSの動員力によって土地へお客さんを集める「地方」の芸術祭とは果たして??当然この疑問が過ることとなる。
多くの人はこう考えているだろう。だからこそネットワークの外部の実空間が必要で、そこで人間と人間、そしてその土地の風習と接触することで豊かな公共性や文化を育むのだ、と。だがその認識は甘い。SNSを活用して人間を動員して祭りを盛り上げようとする限り、検索して辿り着いたその場所はサイバースペースを中心に展開することになる。ハッシュタグをつけてSNSにお目当ての物事を投稿して満足して終わる。そこで人は何事かに「出会う」ことができるのか?重要なことは、実空間に身体を運ぶことなの「ではない」。そうではなく、いま地方や土地の文化的生成力を問うために必要なのは、空間に接続することで逆説的に「時間的に」人間を自立させることだ。そうして、世界中の人間を否応なしに「同期」させてしまうネットワークの力に抗うことではないか。
プラットフォームの同期させる力が危ないのは、世界中の人間に同じタイミングで同じ思考を促してしまうことである。もちろんその力を利用することで初めて達成できることは少なくない。ゼレンスキーの政治戦略はその典型である。だが、その力の負の側面は無視できない。政治的にはポピュリズムの温床を整備し文化的には単なるコミュニケーションを超えた事物それ自体との出会いを人間から奪ってしまう。
もう少し前提へ遡ろう。いま地方創生というと、なぜゆるキャラや地方初のスポーツチームを作ろう!となってしまうのか。それは大抵の人が「地方創生」というときの「地方」という言葉で、たんに高度成長期に生き生きしていたような、列島改造論的(田中角栄的)な国土の開発が盛んだった「あの頃の地方」を想定してしまっているからだ。だから日本中が同じような地方創生になってしまう。現在隆盛を極める地方芸術祭にも同じことが言える。だから、今「地方」について考えるためには、「あの頃の地方」ではなく、本来の地方≒土地の力を回復させることと、さらに2020年代の現在固有の空間の力を模索することが欠かせられないのだ。
個人的なことを言えば、筆者は土地を媒介とした人間の共同性をストレートには信じられない。共同性の裏面にびっしりと生い茂っている陰湿な排除性のほうが先に気になってしまう。同じ物語を信じる人同士で結束を強めるほどに関係性は閉じてゆくからだ。だが、個人主義や相対主義を掲げて共同性を批判すれば何かを言ったことになったのは80年代のことで、今はもう1周回っている。もう一度、共同性の価値を諦めずに探してみようというところにきている。いま芸術祭をきっかけに土地や空間の価値について「あえて」考えたいのはそうした背景がある。
さて、以下では、本紙が特に注目する音楽祭を主宰する2名に登場いただき、さらに他ならない札幌の地方音楽祭であるPMF2023の振り返りを交えつつ、最後にコラム「ことばと文化9」で筆者個人の考えを提示するところまで進めたい。
(多田 圭介)
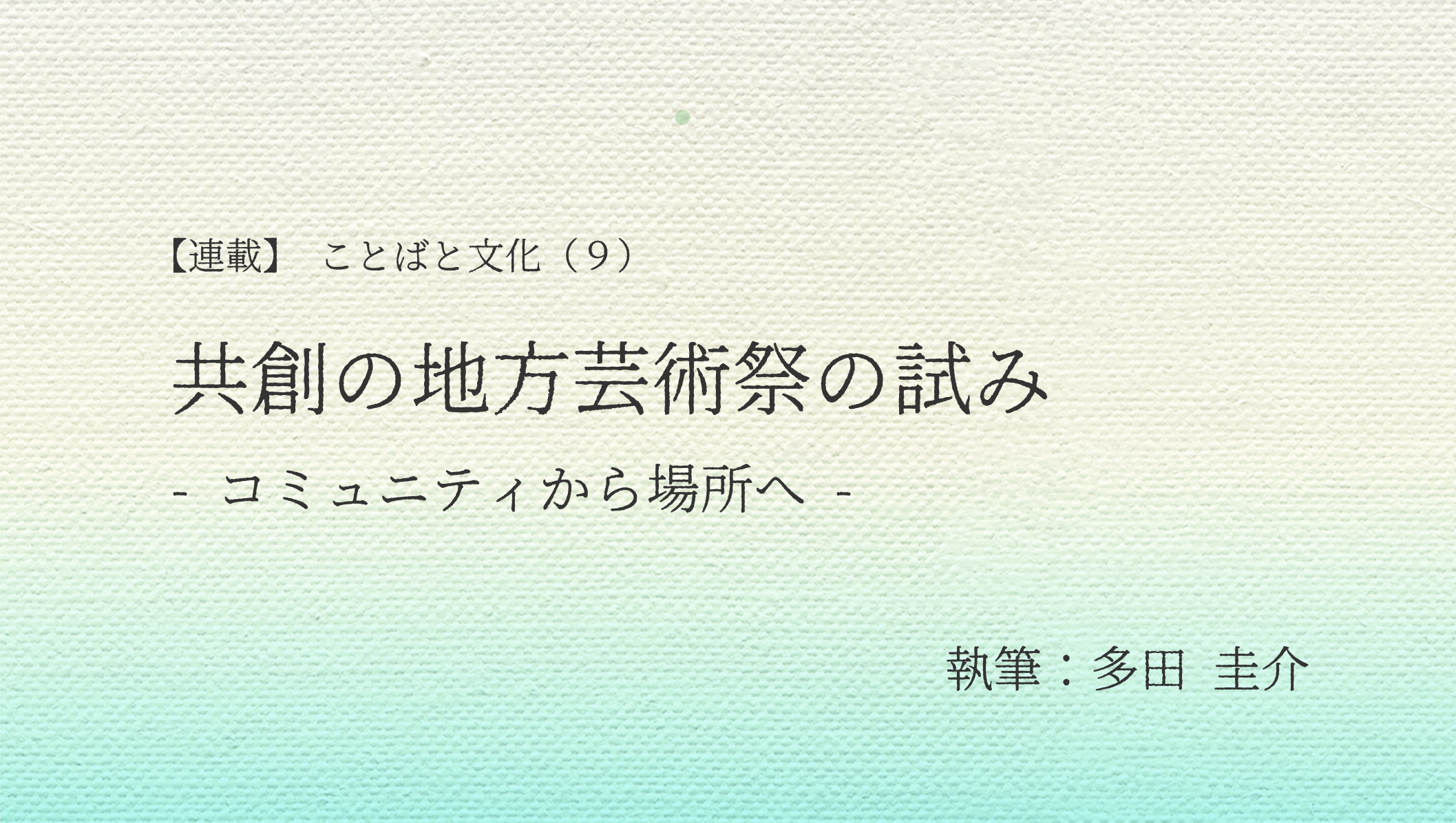
いま、地方芸術祭は何をなしうるのか、いま地方とは何か。柴田原稿と布施原稿に対して本紙から応答すべく問題提起したい。巻頭記事で「いま地方や土地の文化生成力を問うために必要なのは、空間に接続することで逆説的に「時間的に」人間を自立させることだ。そうして、世界中の人間を否応なしに「同期」させてしまうネットワークの力に抗うこと」と述べておいた。この「空間に接続することで時間的に自立させること」、これをもう少し具体化させてみよう。
着目したいのは「共創」という観点である。共創とは、複数の人間が関与することである種の偶然性がプラスに作用して表現が生成されるモデルを意味する。これまた文化だけでなくビジネスなどでもここ10数年ほどずいぶん叫ばれてきた。だがあまり成果をあげることなく収縮してしまった。それは、おそらくはネットワークの「同期させてしまう力」を侮ったからだ。複数の人間を同期させたままでは、結局のところは「今ならこうした意見を出せば100リツイートされて自分のマーケットが拡大する」など他人の顔色を窺がって実際の反応をみてまた次のポスト、となってゆく。それを続ければ続けるほど人間関係に埋没して事物の本質を見極めることからは遠ざかる。政治やビジネスでは有効性はあるのだろうが文化的には創造性を削ぐことになる。
共創そのものについて少し敷衍してみよう。共創とは複数の人間によるアクションの連鎖を意味する。そこである種の偶然性がプラスに作用し一人では決してなしえなかった作品が生成される。同じものは二度と生成されないから、私たちはその一瞬に奇跡を見出す。例えば、映画「アマデウス」に即興演奏の応戦のシーンがある。一人の演奏に対してまったく違う角度から他者性が差し込まれることで表現が生成される。こうした生成モデルは、例えば北は北海道から南は沖縄までをカバーするような文化形態には適用できない。共創は言語を超えたある種の身体性≒空間の共有を前提とするからだ。ここに土地を媒介とした文化の現代的なヒントがある。
元来、創作とは生成=共創的なものだったのだが、近代以降のここ200年ほどで、人間は一人一人バラバラで自立しており個性的なんだという約束事ができてきた。そうしてその個人が自分の内面をしっかりと発信することが確立した自我の表現であり、それは文化的にも民主主義的にも社会を成熟させるんだ、と。たしかにそうして文化的な表現のレベルが飛躍的に高まったのがこの200年だ。文学でも音楽でもそうだ。けれど、それは「受け手」と「送り手」をはっきりと切り分けることでもあった。著者と読者、演者と客のように。こうした二分法は極めて近代的なルールである。もちろんこの形態でなければ生まれない文化は多いし、そうしなければ到達できない世界はたしかにある。だけど、私たちはこの200年ほど、「文化とは元来は共創する快楽である」という原点を忘れつつある。
もちろん、共創にも問題はある。それはサイバースペースとは違う仕方で「閉じてしまう」ことだ。共創のその現場では自分たちの間で今なにか奇跡が起きているというたしかな感覚が舞い降りる。だがその感覚が第三者に伝わるかというとそれは運の問題になってしまう。共創されたものとは、第三者にとっても価値があるものなのか。それとも「僕たち」の間でだけ尊いものになってゆくのかは分からない。さらに共創の奇跡の感覚に一度心を揺り動かされた人は、その感覚を目的とするようになってしまう。そうすることでどんどん閉じてゆく。同じ人としか触れないということも起こってくる。これではネットワークの同期させてしまう力の縮小バージョンでしかない。共創に着目するにしても、それを「どう開いてゆくか」という意識がなければいけない。
余談だが陰謀論には夫婦でハマる人が多い。Qアノンや反ワクチンなどがその典型だ。これは社会心理学的に自明なことなのだが、夫婦の絆を確かめるためには共通の何かを信じていることが有効なのだ。共創の負の側面にも同じことが言える。共創は一人では決してなしえなかったような射程距離の長い力を発揮するのだけれど、反面、関係性を閉じてしまう性質があるのだ。
解決策は2つある。1つは、触れ続けないこと。誰かと触れてそうして何かが共創されることを恐れてはいけないが、同時に触れ続けたいと感じてしまったらそこにも罠があることを忘れてはいけない。もう1つは触れ続けても壊れてしまわないように自分を鍛えておくこと。ここで、共創と近代的な自己陶冶の接点、つまり土地を媒介とした共創の現代的な可能性が見えてくる。人と触れ合わなければ見えないものや辿り着けない場所は間違いなくあるしそれは共創によって生成されるのだけど、それと同時に一人にならないと見えるようにならないものもまた存在する。孤独にならないと気づけないものは絶対にある。その両方が必要で、その領域が交差するような空間(時間的に個々が独立した)が現代的な土地=場所の文化的ポテンシャルなのではないか。
地方での音楽祭だとどうなるか。例えば北海道にはアイヌの伝統的な楽器が存在する。ムックリや五弦琴などは西洋とは異なるイディオムを持っている。青森の津軽三味線などもそうだ。こうした楽器によって奏でられる音楽と例えば西洋音楽の楽器による共創などは、土地の固有の文脈による生成であり、かつその生成には閉じずに開かれてゆく可能性を認めることもできるだろう。それぞれの確固たるアイデンティティも問われる。異質な他者性に自分が侵入されて自分が心の奥から変えられてしまう。そのたびに世界の見え方がガラリと変わる。おおげさに言えばそのたびに人は死んで生まれ変わる。これこそ共創の本質だ。
もう一つは会場の空間性。筆者が参照しているのはフランスの思想家のジル・クレマンの発想だ。彼は「動いている庭」というコンセプトを提案している。例えば、よく分からない古い樹木が生えていてその周りに雑草が生い茂っているとしよう。クレマンは、それを伐採しない。むしろそのよく分からない土地の樹木を中心においてその植物の生成を生かした庭のデザインを考える。これは支配でもなければ放置でもない、生きた乱数の供給源としての空間性である。音楽祭をせっかくどこかの地方で開催するのであれば、会場にこうしたその土地の偶然性を取り込むことも面白い。こう考えると、日本中の津々浦々まで存在する清潔で管理が行き渡ったコンサートホールというものは、見方を変えると単細胞生物だけが異様に生い茂っていて他の生物が死滅した特異な空間のようにも見えてこないだろうか。これに対抗するためにこそ、それぞれの固有の土地の文脈が必要になるというわけだ。
プラットフォームは世界中の人間を同じ時間軸に同期するものだった。だが、こうした乱数供給源としての土地の空間性は、それぞれの存在(樹木、岩、無機物など)の時間軸のズレを持つ。ハッシュタグが付かないその土地の風景そのものを強く意識するとき、建物が、木々が、虫の声が、剥き出しで立ち現われる。そのとき土地と本当の意味で出会う。そうして驚きと出会う。もし土地を媒介とした現代的な共創の可能性を模索するとすれば、こうした「先」で生起するものになるのではないだろうか。青森の恐山のふもとで、それも朽ち果てた樹木の傍らで津軽三味線とヴァイオリンのスーパーソリストが即興の応戦を繰り広げていたら、どうだろうか。
心温まるコミュニティをつくる運動は山ほどある。もちろん大切な活動だとも思う。だが、そこで地域のお祭りに(半強制的に)参加して地元のおじいちゃんと地元の酒を酌み交わす、みたいなことに筆者は興味がない。こういうコミュニティを礼賛するのは、おそらくは東京の人間のファンタジーでしかないように思える(東京育ちの宮崎駿が農村を美化するような)。こうした活動が好きな(おそらく都会の)人は、閉鎖的で前近代的なこの種のコミュニティの弊害を過小評価している。だから、筆者は「コミュニティ」ではなく「場所」を足場に選んだ。事実上のムラ社会賛美に接近してしまっている昨今の地方創生論を乗り越え、さらにサイバースペース上での閉じた承認の「外部」としての、土地=空間が持つ文化的生成力はどこに求められるか。そしてその発想の上でどのような地方芸術祭がいまあり得るか。概ね筆者のコンセプトは固まってきた。
最後に、もしこうした形で地方芸術祭、特に音楽祭を筆者が主宰するとしたら、その会場にはドローンを飛ばし、それに搭載した電波妨害兵器”ECM”によって会場の全域をジャミングして、音楽祭の空間をサイバースペースから孤立させて運営するだろう(たぶん違法)。そして、そのドローンの躯体には”ULTIMA RATIO”という文字が刻まれていることだろう※。
(多田圭介)
※”ULTIMA RATIO”とは、映画「機動警察パトレイバー2」の劇中で東京全域を電波ジャックした飛行船の船体に書かれていた言葉で、「究極の理性」ないし「最後の手段」を意味する。


