【リレーエッセイ<STJ接触篇>③】いまはまだ聴こえない音を聴く――コロナ、アドルノ、批評理論の不在(執筆:相馬 巧)
何かを指し示すための名ではなく、そのことが不可能であることを示すための名が、聴くことには必要なのではないか。そして、その名付けの営みは必然的に挫折する。しかも、その挫折は失敗ではない。挫折を余儀なくされる事態へと自己を差し向け続けることを、アドルノとともに相馬は要求している。(編集:多田)
▼第1回と第2回の記事はこちらからご覧ください。
リレーエッセイ第1回「コロナ禍が可視化したもの―クラシック音楽の生存とは(執筆:平岡 拓也)」
リレーエッセイ第2回「感染する音楽‐世界を祝福 / 埋葬するために(執筆:布施 砂丘彦)」
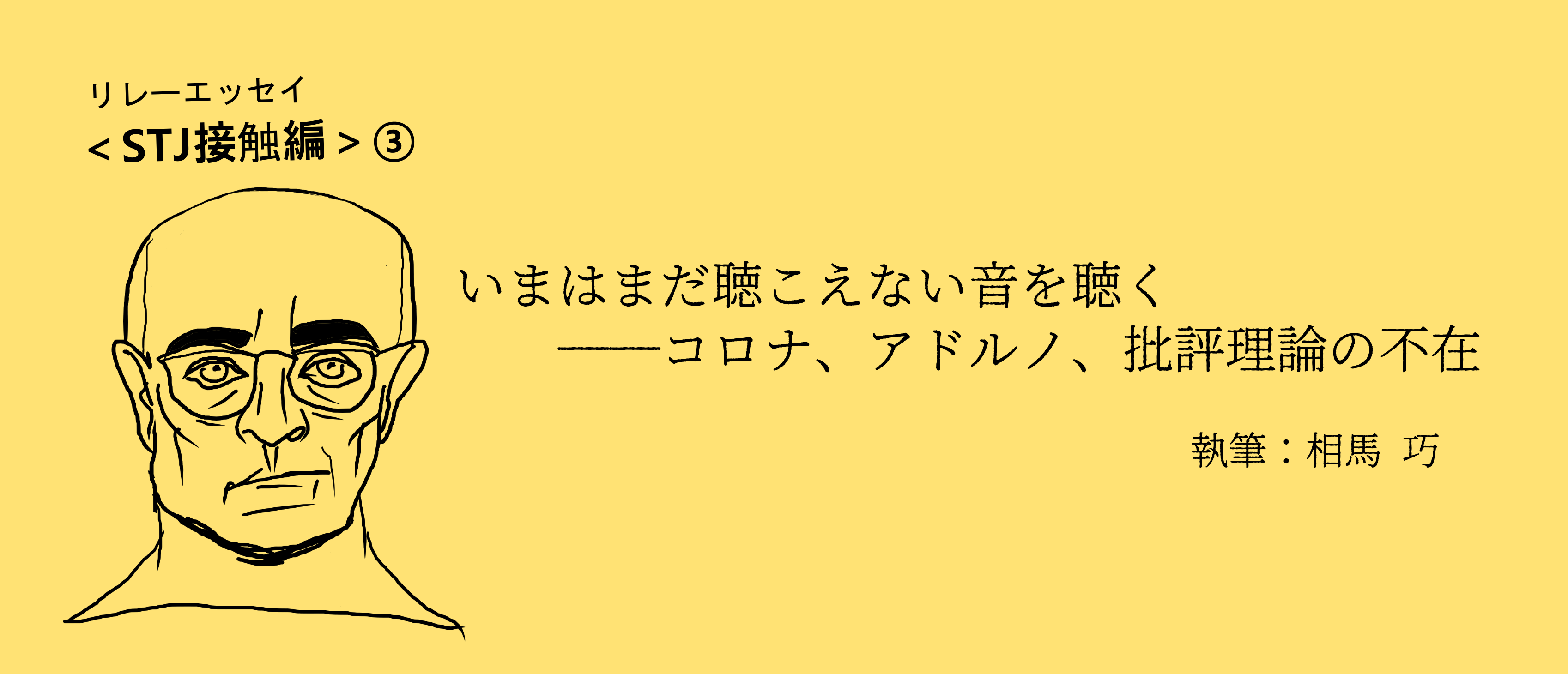
1.いまアドルノを読む
いかなる分野の批評にも論述を下支えする理論などありはしない。しかし少なくとも、小林秀雄、蓮見重彦、柄谷行人らによる傑出した批評の仕事を見ると、実のところベルクソン、ヴァレリー、デリダなどの思想が理論的な役割を担っていたことが分かる。ところが、音楽批評の理論をめぐる状況は今も昔も変わらず、根本的な問題提起すら行われていない。音楽批評は、いまでも19世紀的な芸術至上主義のうちでの仕事を余儀なくされている。それは主として、批評家が作曲家や演奏家たちの代弁者となること、そして作品または演奏に内在する魅力を熱心に語ることにほかならない。こうした言説が――演奏者の仕事のモチベーションにつながることはあっても――、独立した芸術的活動としてなにものも生みだしはしないことはすでに明らかである。打開策も見つからないままに、音楽批評を志す者は減少し、さらにクラシック音楽業界全体は経済的に逼迫してきた。いまや音楽批評は完全に袋小路に入り込んでいる。このことは、現在のコロナウイルスの蔓延を境にしてより顕著になった。
まずもって、作曲や演奏の仕事と批評の仕事はその性質を全く異にしているにも拘わらず、両者の相違が明確に把握されていない。それは偏に、音楽批評家や音楽学者らが、これまで音楽を聴くとはいかなる行為であるかを真摯に問うてこなかったことに起因する。しかし、これが先人たちの怠慢であったと批難することは筆者の意図するところではない。後に詳述するが、これはむしろ、音楽のフェティシズムがもたらす構造的な必然として把握されなくてはならない。
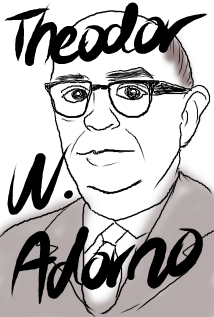 ドイツの著名な思想家テオドーア・W・アドルノの音楽論が、ほかのどの論者よりも精密にそうした現状分析の多くを提供している。アドルノといえば、楽譜に基づいて演奏を聴く「構造的聴取」、もしくは精神を集中させる「集中的聴取」を要求した人物、というクリシェ(決まり文句)がいまだに健在である。しかし、これは全くの誤解でしかない。たしかに彼は、『音楽社会学序説』の「聴取の類型」の章にて「構造的聴取」について語っている。だが、ケーススタディの一例として取り上げられているに過ぎないこの聴取のあり方に、彼が全面的に与している記述はどこにも見当たらない。また「集中的聴取」に関しても同様で、たしかに彼は、「音楽の物神性と聴取の退行」という論考のなかで「軽やかな聴取」を一方的に批判しているかのように振る舞う。しかし、この論考の末尾およそ10頁のなかで、彼はその論旨を大胆に転換させ、「軽やかな聴取」によって知覚される雑多な音の集積のうちに――マーラーの作曲法と重ね合わせながら――、まだ存在していない音の配列を聴き取る可能性を見出そうとする。
ドイツの著名な思想家テオドーア・W・アドルノの音楽論が、ほかのどの論者よりも精密にそうした現状分析の多くを提供している。アドルノといえば、楽譜に基づいて演奏を聴く「構造的聴取」、もしくは精神を集中させる「集中的聴取」を要求した人物、というクリシェ(決まり文句)がいまだに健在である。しかし、これは全くの誤解でしかない。たしかに彼は、『音楽社会学序説』の「聴取の類型」の章にて「構造的聴取」について語っている。だが、ケーススタディの一例として取り上げられているに過ぎないこの聴取のあり方に、彼が全面的に与している記述はどこにも見当たらない。また「集中的聴取」に関しても同様で、たしかに彼は、「音楽の物神性と聴取の退行」という論考のなかで「軽やかな聴取」を一方的に批判しているかのように振る舞う。しかし、この論考の末尾およそ10頁のなかで、彼はその論旨を大胆に転換させ、「軽やかな聴取」によって知覚される雑多な音の集積のうちに――マーラーの作曲法と重ね合わせながら――、まだ存在していない音の配列を聴き取る可能性を見出そうとする。
このようにしてアドルノは音楽の構造から溢れ出る音への注意を促す。彼にとってあらゆる音楽作品は予め完成されたものではあり得ず、構造からあふれ出た音の知覚によってその作品全体の構造を絶えず変化させる。そのため作品とは、聴取が成されて始めてかたちを持つものであって、作曲者や演奏者による表現の段階とはまだ作品の生成過程の途中にあるものとされる。彼にとって作品とは、作曲・演奏の行為とともに聴き手の知覚のなかで生成変化するものにほかならないのだ。このことは、現在のほとんどの音楽批評家が与している、表現者を絶対視する音楽観とは全く異質なものであろう。アドルノは、音楽を聴くという行為を思考した最もラディカルな音楽論者のひとりであった。音楽批評は、アドルノを読まずして、そして乗り越えることなくして、なにかを言うことはできないのではないか。
思想史研究のこれまでの成果によって、アドルノの音楽観には大幅な修正が成されてきた。しかし、このことが音楽批評の実践のレベルに敷衍されているとは到底言うことができない。だからこそ、音楽批評はいまだに作曲家や演奏者の論理に寄り掛かることでしか仕事ができていないのではないか。これはアドルノ受容の遅れが引き起こした重大な損失と言わざるを得ない。
 たしかに、渡辺裕の『聴衆の誕生』や岡田暁生の『音楽の聴き方』といった、アドルノの音楽論を参照しつつ音楽の聴取を論じる優れた著作は、すでに何点か存在している。しかし、いずれの著作もアドルノの論述それ自体における音楽聴取の問題に十分に踏み込んではおらず、基本的に従来のクリシェを踏襲するに留まる。音楽批評の理論を部分的に彷彿とさせてはいるものの、理論構築への決定的な転換点にはなり得ていない。このときに重要となるのは、音楽を聴くという行為がいかにして相対主義的ななんでもありの状態を乗り越え、表現者の論理とは別の位相において芸術的な役割を担うことができるかを問うことにある。
たしかに、渡辺裕の『聴衆の誕生』や岡田暁生の『音楽の聴き方』といった、アドルノの音楽論を参照しつつ音楽の聴取を論じる優れた著作は、すでに何点か存在している。しかし、いずれの著作もアドルノの論述それ自体における音楽聴取の問題に十分に踏み込んではおらず、基本的に従来のクリシェを踏襲するに留まる。音楽批評の理論を部分的に彷彿とさせてはいるものの、理論構築への決定的な転換点にはなり得ていない。このときに重要となるのは、音楽を聴くという行為がいかにして相対主義的ななんでもありの状態を乗り越え、表現者の論理とは別の位相において芸術的な役割を担うことができるかを問うことにある。
なによりコロナウイルスが蔓延する現在の社会において、音楽批評の理論の不在がクラシック音楽文化の大きな痛手となっていることは明らかだ。コンサートの中止が相次ぐなか、クラシック音楽を聴かない層からは厳しい意見が述べられ、それに対抗して演奏家や音楽愛好家からはその存在意義が盛んに主張された。これほど大規模に音楽の存在が見直されることは、少なくとも前衛音楽が盛り下がった1980年代以降には見られ無かったことだろう。しかし、この問題は決して作曲家や演奏家らの表現者の論理によっては解決され得ない。にも拘らず、ここで生まれた主張のいずれもが芸術至上主義にすがり寄る表面的なものに終始してしまった。なにより危惧すべきことは、音楽のより強固な神話化を志向する論者が多くいたということである。いま多くの人々が音楽をめぐるセンチメンタルな感情に振り回されている。それも良書『音楽の聴き方』を書いた岡田暁生がその中心にいるのだ。しかし、いま必要とされることはむしろ、芸術の脱神話化にあるのではないのか。
2.音楽の脱神話化へ
現在の緊急事態において、クラシック音楽の存在意義をめぐりふたつの立場から言説がなされた。それが、芸術至上主義に回帰することを唱える立場、そして音楽の有用性を唱える立場である。前者は、このような状況下であるからこそ市場原理に囚われずに芸術の理想を追求し、現代音楽を中心とするプログラミングやブルジョワ的な慣習を持つコンサートホールでの演奏・鑑賞の見直しを促す。それによって芸術の力が復権するのだと言う。そして後者は、音楽は精神の栄養、ウイルスに対する身体の免疫作用になるのだから、より広い層に感動を届けることが芸術の使命であると唱える。
 当然ながら、両者の立場は容易に論破することができる。まず前者の立場を実践するなら、世界の音楽家の大半が仕事を失うことになるだろう。ウイルスの蔓延によってただでさえ演奏の機会を失っている音楽家たちがこのような立場を取るならば、音楽業界はいよいよ壊滅的な状態に陥る。また後者の立場に対しては、音楽の美とウイルスに対する身体の免疫作用が論理的になんの脈絡もないことを厳密に指摘しておきたい。「美しいものに対する適意は一切の関心を欠いている」という『判断力批判』でのカントの定義にいま一度立ち返るならば、音楽の美を有用性や利害関心に見出すことはできない。もちろん、そんなことは百も承知かもしれないが。
当然ながら、両者の立場は容易に論破することができる。まず前者の立場を実践するなら、世界の音楽家の大半が仕事を失うことになるだろう。ウイルスの蔓延によってただでさえ演奏の機会を失っている音楽家たちがこのような立場を取るならば、音楽業界はいよいよ壊滅的な状態に陥る。また後者の立場に対しては、音楽の美とウイルスに対する身体の免疫作用が論理的になんの脈絡もないことを厳密に指摘しておきたい。「美しいものに対する適意は一切の関心を欠いている」という『判断力批判』でのカントの定義にいま一度立ち返るならば、音楽の美を有用性や利害関心に見出すことはできない。もちろん、そんなことは百も承知かもしれないが。
しかしいずれにせよ、容易に論破できるからと言って、これらの言説を看過することは性急に過ぎる。まずはこうした言説を通した現状認識の精密化を試みなくては、次の方策を立てることすらできない。そして、緊急事態宣言下の2020年4月から6月にかけて書き下ろされた岡田暁生の著作『音楽の危機』が、特にこの現状認識の多くを与えてくれる。広範な知識を有する岡田らしく、本書では過去の作曲家たちやコンサートホールにまつわる豊富なエピソードがアンソロジー的に列挙される。ストラヴィンスキー、ヴェーベルン、シュトックハウゼンなど、さまざまな20世紀の作曲家の営為が、まるでそれらが現代において再び実践されれば音楽の復権が果たされるのだと断言するかのように、無批判なまま肯定的に挙げられているのだ。こうして岡田は、芸術至上主義に全面的に与する。
本書の目論見は、現在のコロナウイルスの蔓延をひとつの契機とみなすこと、すなわち音楽をコンサートホールの近代的な性質から離脱させる契機とみなすことにある。そうして、彼は脱近代的な音楽の場を構築する足掛かりを見つけようとする。ここで言う近代的な性質とは、舞台上の演奏者たちから観客へと一方向的にもたらされるトップダウン型の音楽の伝達のあり方を指す。岡田は現代の典型的なコンサートホールのかたちを「教室の空間」と揶揄し、そこでは演奏者が教師、観客が生徒の役割を担うと指摘する。そうして彼は、音楽がもたらす栄光のヴィジョンという意味での「近代の物語」を批難する。ここでは、ベートーヴェンの9番交響曲第4楽章のシラーの歌詞「歓喜に寄せて」が主な批判対象となり、「万人よ、抱き合え」という言葉に岡田は近代が孕む欺瞞を見て取るのだ。
しかし本書は、「音楽の危機」というタイトルを取るにもかかわらず、現在の音楽文化に対しては曖昧な姿勢を取るに留める。いわばコロナウイルスの蔓延をダシにすることによって、岡田は自らの理想である音楽の脱近代化を唱えようとするのだ。なによりの問題は、こうした狙いに基づき、過去の音楽が有していたとされる「神話」を芸術のうちに再起されようすることにある。音楽の復権とは、いまを生きる音楽家たちの営為を汲み取ることによってではなく、過去の作曲家の偉業を懐古することによってしか果たされないとでも言うかのようだ。しかしこれでは、アドルノが『新音楽の哲学』のストラヴィンスキー論において批判した「復古」と「退行」のうちにはまり込んでいるに過ぎないではないか。岡田は、脱近代を行う前衛芸術を懐古的に称讃することによって、逆説的にそれらの作品を近代的な「神話」へと退行させる。
このような緊急事態においても、音楽批評は作曲家たちの神話なくしてはなにも語ることができないのか。またこのことは演奏家の神話においても同様である。現在の音楽批評が表現者の神話に依存している現状には唖然とするほかない。団塊の世代の高齢化、グローバリゼーションの進展によってすでに西欧中心主義が過去の遺物と化した現在において、クラシック音楽はもう以前のような高級志向な価値観のもとに生き抜くことはできないだろう。そしてこの高級志向な価値観とは、表現者の神話と密接に結びつくことによって生きながらえてきたものであった。なぜピアノの音やヴァイオリンの音に対して高いチケット代が支払われるのかと言えば、それは神話に浴することが聴衆たちの快感となるためだ。
その意味で、音楽の神話化とクラシック音楽業界が利益を得る経済的な原理は、完全に一致している。これが音楽のフェティシズムFetischismsの効果にほかならない。カール・マルクスが用いたこの言葉は、神が宿るかのように崇められた事物という元々の意味を持つ「物神Fetisch」という言葉から派生する。このフェティシズムにおいては、モーツァルトの作品であろうがケージの作品であろうが、極端に言ってしまえば単なる音の配列のうちに作曲家の物語、つまり神話が見て取られていく。その証拠に、批評家や愛好家たちに目の前の音楽がなぜ素晴らしいのかを聞いたとすれば、ほとんどの回答は、天才的な作曲家の作品、天才的な演奏家の演奏であるからだといった向きに終始するだろう。しかしこれは単なる倒錯、答えにすらなっていない同語反復に過ぎない。
かと言って、このフェティシズムを消し去り、本来の音楽の魔力を取り戻そうとする疎外論に傾くことは筆者の意図するところではない。そうではなく、音楽の神話化によってフェティシズムを直接に打破しようとする岡田が、逆説的により深くフェティシズムへと陥っていることを指摘したいのだ。ここで岡田は、自らが批判している音楽の近代的な構造を逆説的に再生産していると言わざるを得ない。いわば、前衛音楽の高尚芸術化・近代化である。
いまやクラシック音楽は、その存在意義を文化的にのみならず経済的にも問われている。すでに述べたように、高尚芸術であることを唱えようともこの状況を打破することは出来ないだろう。その意味で、現在必要とされるのは、文化の内側にいる人間にのみ通用する言葉ではなく、外側にいる人間、つまりクラシック音楽を知らない人々にも通用する言葉だ。だからこそ必要な方策は、音楽文化がこれまで依拠してきた作曲家や演奏家の神話を強化することではなく、むしろ音楽を脱神話化する言説ではないのか。このとき批評家は、作曲家・演奏家の代弁者でも理解者でもない役割を果たさなくてはならない。
しかし、フェティシズムはどこであろうとも音楽の営みを捉えて離さない。それならばいま必要とされるのは、敢えて音楽のフェティシズムのなかに自律的な芸術作品を入り込ませることによって、作品のうちにそのフェティシズムを内破させる契機を見出すことである。つまり、コンサートホールという文化装置から離れることなくクラシック音楽が自らの近代的な制度を換骨奪胎していくことから、現状を打開する契機を見出せるのではないだろうか。このことはアドルノの音楽哲学に一貫した論法でもあった。
3.アンフォルメル音楽の理念から批評理論へ
フェティシズムを内破させる契機とは、決して作品のうちに予め内在するものとみなされてはならない。というのも、それがある確定されたものとして作品のうちに含まれているとするならば、その契機もまたフェティシズムに取り込まれざるを得ないためである。なのでアドルノの論述は、直接にこの契機を目指すのではなく、つねに聴き手の知覚へと迂回する経路を取る。つまり、作品と批評家とのあいだの動的な知覚・認識の過程のうちにこの内破の契機が立ち現れるとするのだ。
注目すべきは、アドルノのこの思考が実際の音楽の現象から乖離した机上の空論とは言えないことである。特に、晩年にあたる1966年の論考「アンフォルメル音楽の方へ」のなかで彼は、このフェティシズムを内破する音楽のあり方として、タイトルにある通り「アンフォルメル音楽musique informelle」という理念を掲げる。このエッセイにて彼は、60年代においてすでに行われていたブーレーズやシュトックハウゼンらによるセリー音楽、ならびにケージらによる偶然性の音楽や実験音楽の興隆を盛んに取り上げる。アドルノはこれらの同時代の傾向に基づきながら、絵画の分野のアクション・ペインティングなどに向けて用いられてきた「アンフォルメル」という言葉を借用し、自らの音楽論の理念を設定した。理念というのは、現実にはまだ存在しないし、特定の作品が念頭に置かれているのでもないが、いまある諸々の作品が志向している来たるべき理想像という意味である。
フランス語の形容詞informelは、否定の接頭辞in-、ならびに「かたち」を意味するformeによって構成される。「かたちを持たない音楽」、「不定形音楽」などとも訳すことができるだろうが、いずれにせよアドルノが接頭辞in-に含まれる否定の力に注目していることは間違いがない。アドルノがドイツ語で「形式Form」の概念に言及するとき、この言葉は一般的な意味での音楽形式とは異なる意味で用いられる。通常、音楽形式と言われれば楽譜上の音符の配列を指すだろう。それに対してアドルノは、楽譜に基づいて鳴らされた実際の音の配列の意味でこの形式の概念を設定している。「音楽と言語についての断章」という論考のなかでは次のように述べられていた。
「形式」の概念は、隠されたものについてはなにも語らない。そして、鳴り響きつつ運動する〔音の〕結びつきのなかで表現されるもの、つまり単なる形式以上のものへの問いを脇へと追いやる。形式とはただ形作られたものの形式である。
端的に言うならば、音楽の形式と述べられたとき、それがいかなる作品の音であろうとも、それらがただ形作られた音の配列であるという意味において、誰によって書かれた作品の音であるかは重要ではない。形式とは発せられた音が結びついて生まれるものであって、そこでの作者の意図などが同定される必要はないのだ。アドルノは同様の意味をフランス語のformeにも見て取っていたと考えられる。なので「アンフォルメルinformel」とは、音楽が「形式forme」を持つやいなや否定の接頭辞in-によってすぐさまに瓦解する様子を指すと言える。アンフォルメル音楽もまた音楽である以上、実際の音の配列という意味での形式から完全に切り離されることはない。形式のない音楽、音のない音楽などあり得ないのだ。ケージの《4分33秒》ですら、そこには無音という音が作品となる。しかしアドルノは、ケージの作品はその無秩序さゆえにフェティシズムに対して無力であると言う。そのためアンフォルメル音楽は、形式の秩序とその形式が否定されたところの無秩序とのあいだを動的に往還するものとして設定される。いわば、セリー音楽の秩序と実験音楽の無秩序のあいだを往還するのだ。
そのような音楽が果たして可能であるのだろうか。音楽作品のこの秩序の問題に関して、「アンフォルメル音楽の方へ」のなかでアドルノは興味深い考察を行っている。そこで彼は、音楽史上の作品群のうちに秩序と無秩序の往還を見て取るのだ。たとえばベートーヴェンは、全体が緻密に秩序付けられた交響曲5番を作曲したが、それとほぼ同時期に幻想曲のように楽想を連ねる交響曲6番を作曲している。またシェーンベルクにおいても同様で、無秩序な表現主義作品の時代から十二音技法の開発へと移行することによって、彼は秩序へと傾いていく。アドルノは、これらの現象にひとつの強迫観念を見出す。
なぜひとは、開かれた場所にたどり着くやいなや、《期待》が、いやそもそも《エレクトラ》が、もうすでに無事作曲されることができたと胸をなでおろす代わりに、「ここにもう一度秩序を打ち立てねばならない」などという感情を抱くのか、音楽においても一度よく考えておくべきだろう。(「アンフォルメル音楽の方へ」、『幻想曲風に』所収)
ここでアドルノが念頭に置いていることは、音の配列としての音楽が、主題労作、十二音技法、セリーといった秩序に基づいて作曲されることの是非である。つまり、1)音楽とは非秩序的に運動する音の連続であるのか、それとも2)秩序付けられた音の体系を指すのかというアンチノミー(二律背反)をここでアドルノは問題にしている。どちらかのテーゼが真であることはあり得ず、ふたつのテーゼが両立していなければ音楽という現象を説明することはできない。
 音楽のフェティシズムの問題をこの図式のうちで捉えることができるだろう。『音楽の危機』のなかで岡田暁生が行おうとしていた前衛音楽の高尚芸術化・近代化とは、先ほどのアンチノミーにおける前者のテーゼを捨象したことによって生まれた。つまり、岡田にとって音楽とは作曲家によって予め体系的に確定された音の配列を指すのであり、このことが神話的構造と結びつく。フェティシズムの内部においては、たとえ彼が問題としていた教室型のコンサートホールのあり方の見直しを行おうとも――岡田は古代ギリシアの半円劇場や古代ローマのコロッセオを肯定的に取材していた――、そこから生まれる劇場とは、芸術の神話を再生産する装置にしかなり得ない。
音楽のフェティシズムの問題をこの図式のうちで捉えることができるだろう。『音楽の危機』のなかで岡田暁生が行おうとしていた前衛音楽の高尚芸術化・近代化とは、先ほどのアンチノミーにおける前者のテーゼを捨象したことによって生まれた。つまり、岡田にとって音楽とは作曲家によって予め体系的に確定された音の配列を指すのであり、このことが神話的構造と結びつく。フェティシズムの内部においては、たとえ彼が問題としていた教室型のコンサートホールのあり方の見直しを行おうとも――岡田は古代ギリシアの半円劇場や古代ローマのコロッセオを肯定的に取材していた――、そこから生まれる劇場とは、芸術の神話を再生産する装置にしかなり得ない。
岡田の失敗の最大の原因は、音楽の文化が危機に瀕した現在の状況において、音楽という現象を捉え返すことなく音楽の神話的な秩序という「強さ」へとすがり寄ってしまったことにある。しかし音楽の現象とは、あのアンチノミーが示しているように、音の体系であると同時に音の非秩序的な運動でもある。つまり、音楽はその非秩序の「弱さ」から逃れることができない。アドルノはこの「弱さ」に正面から向き合うことを促す。
私は、図式化された秩序への欲求の永遠回帰のうちに、その真理の保証などではなく、むしろ果てしない弱さの症状を見てしまう。(・・・)自由であるために内在的に自分自身を見通すことのできる合法則性と、借り物の秩序への降伏とは互いに相容れない。(同上)
ここでアドルノは、決して音楽のうちに必然的に生じる弱さを否定してはいない。それ自体が存在することが問題なのでは無く、その弱さを認めずに「借り物の秩序」という強さへと降伏することを問題視しているのだ。つまり、真に重要な点は、岡田のようにその弱さを排除することでは無く、弱さを通して見えるこの社会における音楽の本性が如何なるものであるかということである。
もっとも、アドルノが言うここでの「弱さ」とは、シェーンベルクの作曲の変遷に向けられており、本稿が取り上げる音楽批評の問題とは相容れない様にも思われるだろう。しかし、この論考でのアドルノの目論見は、対象となる音楽作品を理解しようとすることではなく、作品の考察を通して「アンフォルメル音楽」という理念を構築することにあった。それは音楽とはいかなるものか、音楽を聴くとはいかなる行為であるかという根本的な問いに結びつくのであり、この点においてアドルノの思考とはつねに批評と一体になっていると考えなくてはならない。
こうしてアドルノは、主題労作、十二音技法、セリー、さらにはコンサートホールの空間といった諸々の秩序を、弱さの観点から捉え直すことを要求する。それは音楽という秩序を非秩序的な音という弱さから捉え直すことと言い換えてもいい。しかし、そもそも音とはどこにあるのか。フェティシズムのうちにおいては、音の集積がすでに自明化・既定化された体系のもとへと配置されることで音楽は生まれる。いわばそれは、音から音楽へという確立された経路を取る。それに対してアドルノは、次のように音楽という現象を捉える。
音楽は、単に音からできているのではなく、音と音との関係から成り立っている。ひとつの音は別の音なしに存在しない。そしてまさにこのことが、アンフォルメル音楽への移行を引き起こす。(同上)
一見何の変哲もない文章のように思われるかもしれない。しかしこの一節が音楽哲学の決定的な転換点を指し示している。アドルノは音と音楽の立場を逆転させようとするのだ。彼によれば、演奏においてまず生成されるものとは――優れた通奏低音の演奏が特にそうであるように――、音ではなく音と音との関係であった。このとき音楽はまず秩序へと向かう。しかし、ときに音楽が解きほぐれ、音が偶然に溢れ出てくることがある。それは予め決定された関係のうちには収まらない非秩序的な音である。その音が断片として知覚されたとき、音楽の形式は以前と同様のものではあり得ない。そして、決して自明のものでもあり得なくなる。だからこそ作品の全体性は、演奏され聴取される毎に変化を遂げる。ここで音は、直接に存在することのない、音楽のうちから溢れ出る「抽象的なものであり、切り取られて初めて現れる」(同上)ものとされる。そうしてアドルノはフランス語で次のことを語る。
音楽を作るのは音ではない。Ce n’est pas le ton qui fait la musique.(同上)
この言葉は、「本心は話し方に表れる」という意味のフランスの諺「調子が音楽をつくるC’est le ton qui fait la musique」をもじったものである。語順を反転させるならば、「音を作るのは音楽であるC’est la musique qui fait le ton」と言い換えることができる。この言葉が今後の音楽批評のスローガンとなるだろう。まさにあらゆる作品に対して、鋭い耳でもって抽象的に浮かび上がる音をつかみ取り、多様に変化する音と音の関係を演奏家とともに記述することが批評家に求められているのだ。
いま再び求められているのは、あの鋭い耳であると言わざるを得ないだろう。新しい、そして全き意味において、不意打ちの要素すら聴き逃さない、そういう耳である。この点でアンフォルメル音楽は、完全には表象できないものについての表象である。(同上)
音は、音楽のうちから瞬間的に現れ出てははかなく消え去っていく。ここでの形式の生成と消滅の連続のうちに音楽を聴くことによってこそ、音楽のフェティシズムを内破する契機を見出す可能性が生まれるのだ。あらゆる作品のうちに、いまはまだ聴こえない音を聴かなくてはならない。音楽批評はここから始まる。
(相馬 巧)
<著者紹介>
相馬 巧(Takumi Soma)
 専門領域はテオドーア・W・アドルノの音楽論を中心とした近現代ドイツ思想史。 東京大学大学院総合文化研究科超域文化科学専攻表象文化論コース博士後期課程に在籍中。研究のほかにも音楽批評の活動を行い、オペラ公演やコンサートに舞台監督、ドラマトゥルクとして参加する。2017年に早稲田大学創造理工学部総合機械工学科卒業。2020年に東京大学大学院総合文化研究科超域文化科学専攻表象文化論コース修士課程修了。修士論文のタイトルは「音楽言語の自己否定的な身振り――テオドーア・W・アドルノの演奏理論」。同年に第7回柴田南雄音楽評論賞本賞を受賞。
専門領域はテオドーア・W・アドルノの音楽論を中心とした近現代ドイツ思想史。 東京大学大学院総合文化研究科超域文化科学専攻表象文化論コース博士後期課程に在籍中。研究のほかにも音楽批評の活動を行い、オペラ公演やコンサートに舞台監督、ドラマトゥルクとして参加する。2017年に早稲田大学創造理工学部総合機械工学科卒業。2020年に東京大学大学院総合文化研究科超域文化科学専攻表象文化論コース修士課程修了。修士論文のタイトルは「音楽言語の自己否定的な身振り――テオドーア・W・アドルノの演奏理論」。同年に第7回柴田南雄音楽評論賞本賞を受賞。
過去のリレーエッセイはこちらから
リレーエッセイ第1回「コロナ禍が可視化したもの―クラシック音楽の生存とは(執筆:平岡 拓也)」
リレーエッセイ第2回「感染する音楽‐世界を祝福 / 埋葬するために(執筆:布施 砂丘彦)」
※「投げ銭」するための詳しい手順はこちらからご確認いただけます
この記事はこちらの企業のサポートによってお届けしています


